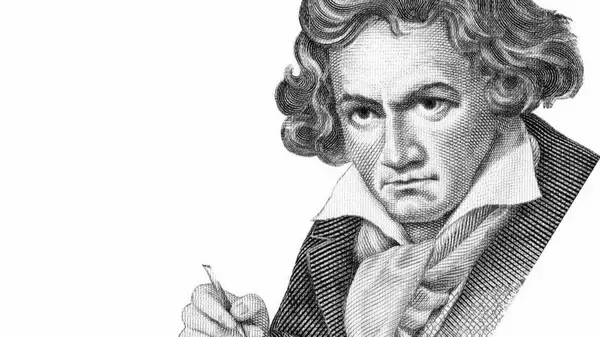
ベートーベンの代名詞ともいえる晩年の「耳が聞こえない」というハンデは、もともと気難しかった性格だった彼の人生をより困難にするものだった。しかし、彼はそれでも生きることをやめずに傑作の数々を生み出していく。
その晩年の姿を『涙がでるほど心が震える すばらしいクラシック音楽』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全3回のうち2回目〉
「耳が聞こえない」難聴の苦悩
僕たちが、ベートーベンの性格を知ることができるのは、彼がそれだけ多くの人と接していたからです。しかし、そんなベートーベンも、30歳になる頃から人との接触を避けるようになります。
その原因は、聴力の衰えにありました。
ベートーベンには多くの支援者がいましたが、彼が手紙に記したように、多くの敵もいました。彼は、敵に聴力の衰えを悟られることを恐れ、社交の場から距離を置くようになります。
人々との距離をとるようになってから2年が経った頃、ボンの親友ヴェーゲラーに宛てた手紙でこう書いています。
「私が惨めな日々を送っていることを告白しなければならない。ここ2年間というもの社交行事を避けてきた。なぜなら、私は耳が聞こえない、ということを誰にも言えないからだ。
もし私が違う職業の人間だったら、その告白はそんなに難しいことではないだろう。けれども私の職業ではそれは非常に不利なことなのだ。決して少なくはない私と敵対関係にある人がこれを聞いたら、いったいなんと言うだろう」(引用:ニューグローブ音楽辞典)
ベートーベンは自分の聴力の衰えに関して、あくまで一時的なものであり、いつかはもとに戻るだろうという希望を持っていました。
その頃、彼は少しでも耳への負担を減らすようにという医師の助言の下、ウィーン郊外のハイリゲンシュタットで過ごすことになります。
ここで、聴力は永遠に戻らないだろうと確信するのです。
そうして書かれたのが、「ハイリゲンシュタットの遺書」と呼ばれる遺言状です。弟のカールに宛てたもので、その中ではベートーベンが自殺を考えたことや当時の苦悩が告白されています。
しかし、彼はここで自殺という選択をとりませんでした。芸術家としての使命を果たさなければならない、と考えを改めたためです。遺書には、彼の使命感と強い意志が表れています。そしてそれはベートーベンを知る多くの人の心を打ちます。
気難しさが増すも音楽家として円熟した晩年
この手紙を境に、ベートーベンの音楽は非常に使命感を帯びたものへと変化していきます。
一方で、性格はさらに気難しく、疑り深いものへとなっていきます。かつては女性との関係に積極的で、結婚に対する憧れも持っていました。しかし、聴力が完全になくなる頃にはそれもあきらめてしまいます。
そして、その気持ちは甥のカールの養育権へと向かっていきます。
ベートーベンは弟のカールが亡くなった後で、弟の息子であるカールの養育権をめぐってその母親と激しく争うことになるのです。ベートーベンのカールへの執着ぶりはかなりのもので、カールの交友関係にまで口出しし、さらに甥に対して嫉妬までしてしまいます。
カールは、こうした苦しみから逃れるためか、ピストル自殺を図り、なんとか一命をとりとめますが、これはベートーベンにも大きなショックを与えることとなりました。
難聴を境に気難しさが増したベートーベンでしたが、その一方で亡くなるまでカリスマ的な人気を誇ります。次から次へと素晴らしい作品を発表するベートーベンの才能は、もはや誰の目にも疑いようがなく、多くの人がベートーベンと交流を持つのは価値があることだと感じていたのです。
ハイリゲンシュタットの遺書の後で生きる決断をしてから、ベートーベンは「ピアノ協奏曲第5番」や「ヴァイオリン協奏曲」「ピアノソナタ『熱情』」「交響曲第5番『運命』」といった傑作を次から次へと生み出しました。
そして晩年には「ミサ・ソレムニス」、さらには「交響曲第9番」といった音楽史に残る傑作が誕生し、後の時代の作曲家たちにとって超えるのが容易ではないほどの芸術的な高みに到達しました。
ベートーベンは晩年、肝硬変になり、ベッドでの生活を強いられますが、見舞いの客が途切れることはありませんでした。ベートーベンはその病が原因で、56歳で亡くなります。埋葬式には1万人もの人々が参列したと伝えられています。
音楽に渦巻く強く前向きなエネルギー
難聴を境にベートーベンの人柄はより気難しいものへと変わりました。耳が聞こえないため、コミュニケーションは筆談を使った限定的なものとなります。
自分の声が聞こえないため、その話し方は人々にさらにぶっきらぼうになります。そして時には荒々しい印象も与えたかもしれません。
一方で、ベートーベンの音楽は、耳が聞こえなくなるにつれて、より雄弁になっていきました。ベートーベンは自分が言いたかったことを音楽の中で雄弁に語ったのです。
ですからベートーベンの音楽には様々な想いが残されています。そうした想いに耳を澄ませると、彼が決して人前では見せることがなかった姿が少しずつ見えてきます。
ベートーベンはハイリゲンシュタットの遺書で自殺を考えたと告白しています。しかし彼は生きる決断をしました。その理由も遺書に記されています。それは芸術のためでした。
ベートーベンは芸術家として音楽を世に残すことが自分の使命だと考えていました。その使命を果たすまでは、どんなにつらくとも死ぬわけにはいかなかったのです。
現在、「芸術」という言葉は幅広く使われています。「芸術とは何か」を知りたければ、ベートーベンにとっての芸術がどのようなものだったのかを知る必要があります。
ベートーベンにとっての芸術、そして音楽とは、耳が聞こえないという苦しみを抱えながらも、生きていくほど価値があるものでした。
だからベートーベンの音楽の中では、彼の信じたものが表現されています。
彼が信じたもの、それは「希望」であり、「喜び」でした。
ベートーベンの作品の中でもとりわけ有名な交響曲第5番は、「運命」という名前で親しまれています。
「ジャジャジャジャーン」という衝撃的な出だしで始まるその曲は、恐怖や不安といった気持ちを聴衆に伝えます。
続く第2楽章では、生きるための希望というものが提示されるのです。しかし多くの人が人生で経験したことがあるように、その希望をすぐに信じることはできません。そこには疑念があります。ですが、そのような葛藤を乗り越えて最後に大きな希望が勝利するのです。
ベートーベンは音楽で、人間にとって不変のドラマのような、大きな理念を描こうとしました。
それらの音楽には強く前向きなエネルギーが宿っています。そうしてベートーベンはその音楽で聴衆にたくさんのエネルギーを分けてくれるのです。
なぜベートーベンの音楽に共感できるのか?
またベートーベンは芸術と同じくらい、正義や品性、そして徳の力も信じていました。
そのためベートーベンの音楽を聴いていると、「そんなことでくよくよしないで、もっとしっかり生きなさい」と、活を入れられるように感じる時があるぐらいです。でもそれは苦しみを乗り越えたベートーベンなりの激励の仕方なのかもしれません。
このように強烈な希望のエネルギーが込められている一方で、ベートーベンは人の弱さ、そして苦しみというものを理解していました。それは「緩徐楽章」と呼ばれるゆっくりとした楽章によく表れています。
おそらくベートーベンは、優しさを素直に表すことはほとんどなかったのではないかと思います。ベートーベンはそういう意味ではかなり不器用なタイプでした。しかし、彼は深い優しさを持った人物でした。
そうした優しさはピアノソナタ第8番「悲愴」やピアノ協奏曲第5番「皇帝」、交響曲第9番の第3楽章の緩徐楽章で聴くことができます。心の内側へと、深く深く入り込んでいくような音楽で、優しく聴き手の心に寄り添ってくれます。
大きな希望が外側へ向かうエネルギーとするならば、この優しさは内側へと向かうエネルギーです。そしてここに、ベートーベンの偉大さの秘密があります。内面的な感情から外面的な感情まで、その感情の幅がものすごく広いのです。
だから多くの人々がベートーベンの音楽に共感します。ベートーベンの音楽が現代人の心に共感します。そのようにして多くの人々の心をとらえるのです。
ベートーベンは50歳になってから「ミサ・ソレムニス」と「交響曲第9番」という大作を完成させます。その後、大作は作らず、「弦楽四重奏曲」を続けて作ります。
その「弦楽四重奏曲」に耳を傾けると、ベートーベンが芸術家としての使命を果たしたこと、そして耳が聞こえない自分との戦いがようやく終わったのだ、ということが聞こえてきます。
ベートーベンは耳が聞こえない自分を、そのまま受け入れたのでしょう。そこには和解のようなものが感じられます。心の安らぎが訪れたことが感じられます。
そうした音楽の心に耳を澄ませると、自然に涙がこぼれてきます。そうして芸術家としての使命を果たしてくれたベートーベンへの感謝の思いが沸き起こってくるのです。
文/車田和寿
涙がでるほど心が震える すばらしいクラシック音楽
車田和寿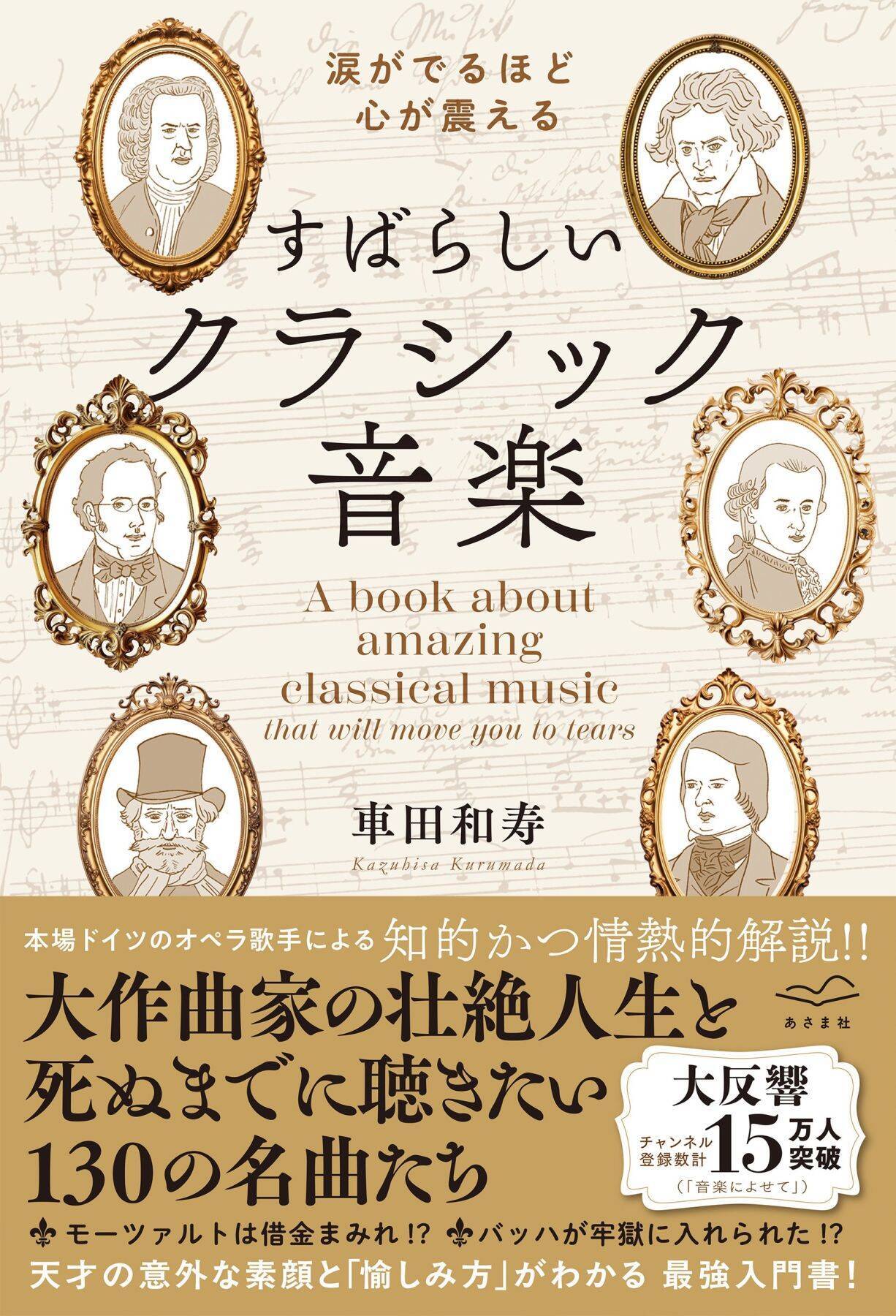
\発売たちまち重版!!/
ベストセラー第1位!
(Amazon.co.jp<�音楽一般>
15万登録! YouTubeで人気のオペラ歌手が解説!
クラシック入門書の決定版ついに登場!!
読めば必ず涙する大作曲家の壮絶人生と名曲の聴きどころ
人生に豊かさを求めるすべての人へ。
クラシックの奥深さを存分に味わう入門書が誕生しました。!
・バッハは刑務所に入れられた!?
・ブラームスの叶わぬ恋とは?
・モーツァルトは借金まみれ
「あっという間に読めました」
「読む前と読んだ後で曲の聴き方が変わった!」
事前の試読から圧倒的支持
もう挫折させません。
本書で紹介した曲が聴ける <公式プレイリスト>付き
聴きながら読める!
「これ一冊で十分だ」
家族に一冊、読み継げる、画期的なクラシック音楽本
(下記「はじめに」より)
音楽にはたくさんの魅力や大切なことがあります。
その一つが「音楽は心のコミュニ ケーションである」ということです。
作曲家は自分が感じたことを音にし、その感じたことが演奏家を通して聴衆に届けられ ます。
そして作曲家や演奏家の感情が聴衆のもとに届けられた時、そこでは化学反応が起 こるのです。
聴き手は様々な感情を受け取ることで、多くの刺激を受けます。
それによっ て聴き手の心の中には、様々な感情が巻き起こり、
やがて心の中で自分自身との対話へと つながります。
しかしこのような経験は、自分が感じたことを大事にして初めて体験できることでもあるのです。
































![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


