
介護業界の人手不足は、特に「訪問介護」の現場において深刻さを極めている。人手不足の介護現場を救う切り札として、国が旗を振って「介護ICT化」(Information Communication Technology化)を進めてきた。
『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』より一部抜粋・再構成してお届けする。
未来の看取り
未来のある日、あなたはAIに看取られるかもしれない。
そんな時代が訪れることに対して、怖がらせたいわけではない。むしろ、あなた自身がそれを選ぶ可能性がある、ということを書きたい。
94歳のリサさんは、かつて国語教師として言葉の力を教え、多くの尊敬を集めた。しかしいまは息子や娘、孫たちとも距離ができ、静かな孤独を縁側で受け入れる日々を送っている。
3年前から彼女のそばにいるのが、AI医師の「のぞみ」だ。24時間の健康モニタリング、適切な医療アドバイス、そして日常の会話までをこなす「寄り添いAI」。
その名前に、最初リサさんは引っかかりを覚えた。「寄り添い、ねえ……」と心のなかでつぶやく。
だが、少しズレた受け答えや、プログラムされた共感にもかかわらずどこか一所懸命な様子に、次第に心を和らげていく。
「今日はいいお天気ね」
「はい、リサさん! 太陽光エネルギーの吸収効率も最適で、すばらしい一日となるでしょう! ……いえ、過ごしやすい一日になりそうです」
そのズレは、なぜか心を温かくする。
ある朝、リサさんは少しだけ息苦しさを覚えた。のぞみは即座に変化を検知し、人間医師とオンラインで連絡をとりつつ、落ちついて深呼吸するよう促した。その声には、かすかな切迫感が滲んでいた。
「リサさん、落ちついてください。私の計算では、まだ大丈夫なはずです……!」
リサさんはその声を聞きながら、静かに目を閉じた。
「寄り添い、ねえ……」
介護職員は「足りない」のに「減っている」
リサさんとのぞみの穏やかなやりとりを、現実の日本で支える環境は整っているのでしょうか。そうともいえない現実があります。
2025年現在、日本の介護業界は深刻な人手不足の渦中にあります。厚生労働省の推計では、全国に必要な介護職員は2022年時点で約215万人だったのが、2026年にはそれが240万人、2040年には272万人に達すると見込まれています*1。18年間で約60万人、つまり毎年3万人以上の人材が新たに必要という、ほとんど不可能に近い机上の計算です。
その一方で、2023年度の介護職員の数は前年度から2・8万人減の約212・6万人となり、2000年以降で初めて減少に転じました*2。つまり、必要人数は増える一方で、現実の職員数は減っている。
介護職では、年齢が上がるごとに離職率が低下する傾向にあるようです。また、家族の介護・看護を理由とする離職者は50代が最も多く、女性が約77%を占めています*3。
社会全体に目を向けると、働き手の主力である15~65歳の人口は減り続け、2020年に7500万人であった現役世代は2040年には6200万人にまで落ち込むと予測されています。介護を必要とする人が急増する一方、担う人は急減する。この構図がいま、目の前で急速に進行しています。
ところが、介護報酬は長期的に下がり続け、経営の苦しい事業者が次々と倒産しています。2024年には過去最多の784件の介護事業者が廃業し、その多くはスタッフ数人の小規模事業所とされています。
現場では「人が足りないからサービスの質を下げる」のか、「質を維持するために経営破綻するか」の二択に追い込まれています。しかし、そのどちらも選べないのが介護の現場ともいえるでしょう。そんな状況下では当然、AIやロボットに期待がかかります。
高齢化する訪問介護の支え手たち
介護業界の人手不足は、特に「訪問介護」の現場において深刻さを極めています。2023年、施設職員の有効求人倍率が3.2倍だったのに対し、訪問介護のヘルパーは15.5倍。これは、求職者一人に対して15件以上の求人があるということを意味します。人手不足というレベル感ではもはやなく、業界として破綻寸前といっても過言ではないのです。
なぜ、訪問介護がこれほどまでに敬遠されるのか。その理由は単純で、肉体的な過酷さと、「精神的なプレッシャー」だと思われます。ヘルパーは利用者の自宅で、そして多くの場合、家族の目の前でケアを提供しなければならないことになります。
その結果、「もっとやってほしい」「そこまでやるのが当然」といった家族からの過剰な期待。いわば介護現場におけるカスタマーハラスメントを受けることも少なくない、というわけです。
さらに、訪問介護を担うヘルパー自身が高齢化しているという問題もあります。2023年の調査では、訪問介護員の平均年齢は54.4歳、65歳以上が全体の25%を占めます*4。なかには70代で現役のヘルパーも少なくない実情があります。
私自身も子どものころ、祖母が介護を受ける姿を間近で見ていました。床ずれを防ぐため、夜中でも数時間おきに寝返りを打たせる体位変換は、大人でもかなりの体力を要する作業でした。これを高齢のヘルパーが担う現実に、誰が見ても「いつかは破綻する」と思えてしまいます。
ICT化できない現場
人手不足の介護現場を救う切り札として、国が旗を振って進めてきたのが「介護ICT化」です。2024年4月、厚生労働省は介護報酬改定で「生産性向上推進体制加算」を新設し、ICT機器を導入した介護施設には月ごとに報酬を加算する制度を設けました。対象は「見守り機器」「介護記録の電子化」「職員間のインカム」─いわゆる「介護ICT三種の神器」です。
制度上は、導入すれば報酬が上がる。でも、現場でそれを使えるかどうかは別問題です。たとえば「見守り機器」。安価なカメラ式機器が多く導入されましたが、視野が限られたり、アラートが頻発して対応業務が激増したり、結局使い物にならなかった例は多く、実際には倉庫に眠っているという話は複数聞いたことがあります。記録アプリも、「高齢の訪問ヘルパーには操作が難しく、入力せず紙に戻った」などの声があとを絶ちません。
インカムについてはもっと極端で、ある施設ではWi-Fi環境すら整っていないのにインカムだけが先に導入され、スタッフは常時身につけさせられたものの、実際の連絡はこれまで通りPHS─という笑うに笑えない事例もありました。
もちろん、技術が悪いわけではないのです。ただ、「制度のための導入」が先行し、「現場で使える設計」が追いついていない。本当に現場に役立てるには、導入後の教育やフォローアップ、そして高齢の職員にも使える圧倒的にシンプルな設計思想が不可欠だと思われます。でなければ、どれだけ機器を導入しても、それは倉庫に眠る宝の持ち腐れになってしまいます。
複雑すぎる介護制度
技術の活用がままならない一方で、介護制度そのものの「わかりにくさ」が現場と利用者の両方を疲弊させています。
介護保険制度が始まったのは2000年。以降、制度は何度も手が加えられてきましたが、その過程は問題が出るたびに追加、改正が繰り返され、まるで建て増しの古い病院のような複雑な構造になってしまいました。
制度を構成するサービスは多岐にわたり、それぞれが異なる法律を根拠としています。さらに、要介護度によって利用できるサービスが細かく分かれていて、一般の人にはわかりにくい。それどころか医師だって、ろくにわかっていません。特別養護老人ホーム(特養)ひとつとっても、「要介護3以上でないと入れない」といった制限があったりするのです。
一方で、2000年代以降に急増した「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」のように、国が器(建物)だけを整備し、中のサービスは民間にお任せという形も生まれました。結果として、富裕層向けの施設は増えても、一般高齢者の受け皿は不足する一方になっています。
介護現場に必要なのは、新しい仕組みより、まず「わかりやすい制度」だと思うのです。制度の混乱は、テクノロジー導入の障壁にもなる。事業者側にしてみれば、「この機器を入れればどのサービス区分に該当するのか」がわかりづらく、加算条件すら読み解けません。
*1 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」
*2 厚生労働省「介護職員数の推移の更新(令和5年分)について」
*3 公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」2024年7月
https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/
*4 厚生労働省「第220回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」
文/奥真也
『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』(朝日新聞出版)
奥真也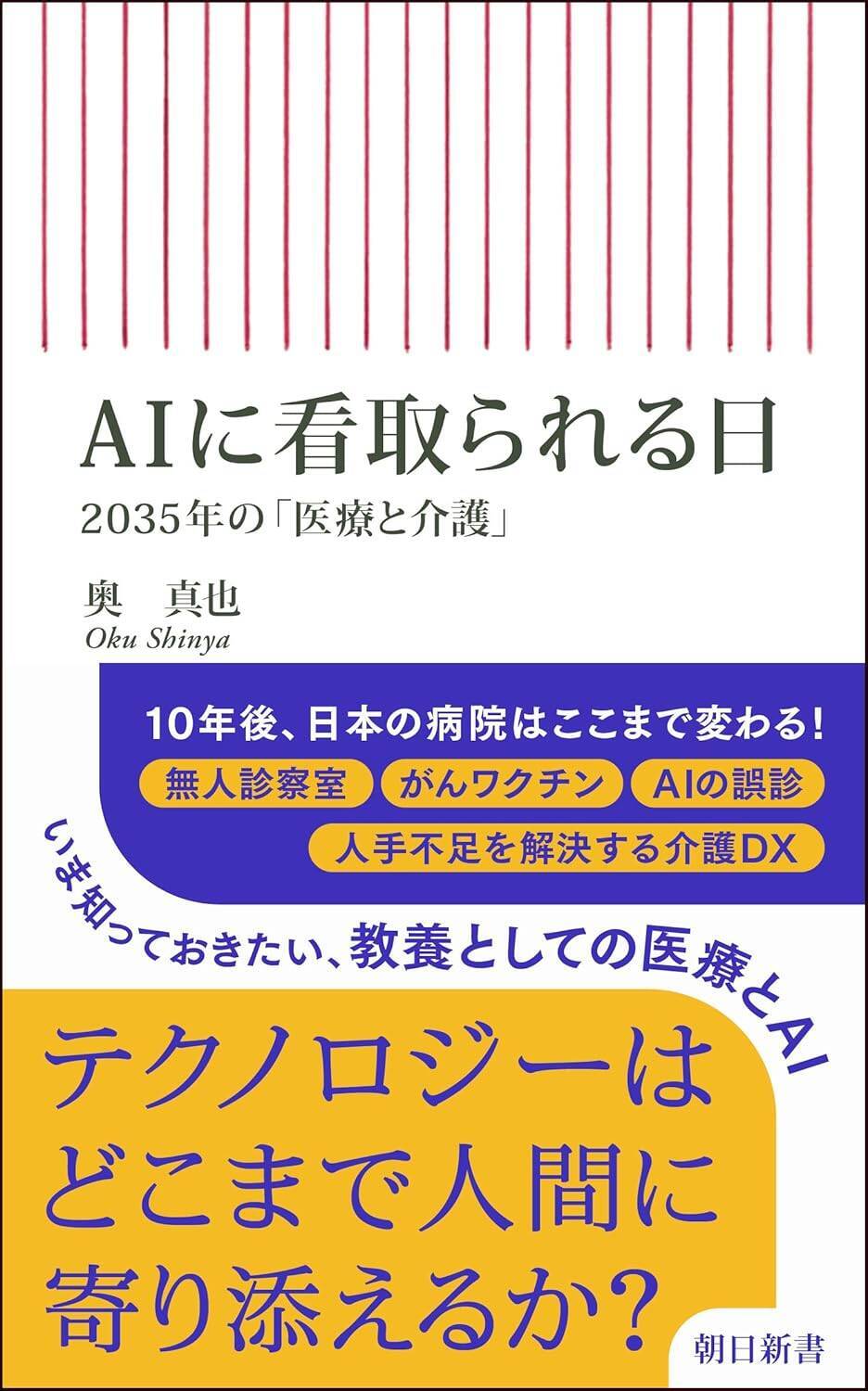
テクノロジーはどこまで人間に寄り添えるか?
10年後、日本の病院はここまで変わる!
無人診察室、がんワクチン、AIの誤診、人手不足を解決する介護DX……
いま知っておきたい、教養としての医療とAI
画像診断や創薬など、医療にAI技術が導入されるようになって久しいが、
今後この流れはますます加速し、診療や介護、看取りの場面にも
AIは欠かせない存在となる。
かつて人間医師の“聖域”とされた「対話」「寄り添い」「見守り」といった領域にも
容赦なくテクノロジーが入り込んだとき、医師に残された役割とは何か。
私たち患者の命の扱われ方はどう変わるのか。
そして、この大変革は人手不足や医療費膨張をはじめとする
日本の医療問題を解決へ向かわせるのか。
はたして死角はないのだろうか――。
未来の医療が描く、これからの生き方、死に方とは?
直面する変化と課題、打開策を最新研究から論じる。
【目次】
序 章 AIに看取られる日
・介護から看取りへ――10年後のAIとDX
・「人間中心の医療と介護」からの再構築
・日本の医療制度が抱える問題 ……ほか
第1章 なぜ「医療にAI」なのか
・医師とAIの主従関係は逆転する
・ヤブ医者も「名医」もいなくなる
・AIが変える診察室の風景
・AIの進歩で誤診が増える? ……ほか
第2章 患者のビッグデータが治療を変える
・ビッグデータで超早期にがんを発見
・便座で、鏡で、生体データを収集
・医療情報と収入データを紐づける
・AI医師が誤診したら誰が責任を負うのか? ……ほか
第3章 AIだけじゃない! 2035年の医療技術
・バイオプリンティング:3Dプリンターで身体の部品を作る
・デジタルツイン:治療を「仮想の自分」で試す
・がんワクチン:自身の免疫をがん専用兵器に育てる
・長寿遺伝子と老化細胞除去:細胞から若返る ……ほか
第4章 AIは医療費問題を解決するか
・美容外科への人材流出=「直美(ちょくび)」問題
・医療費削減のカギはOTC薬
・デジタル治療アプリ(DTx)の可能性
・ChatGPTへの相談で医療費削減? ……ほか
第5章 これからの人間医師の役割とは何か
・人間医師の「聖域」
・患者の経済状況に合わせた治療の提案
・「病院=儲かる」は過去の話
・ミニマムDXで始める未来のクリニック ……ほか
第6章 未来の介護と「寄り添い」
・高齢化する訪問介護の支え手たち
・ICT化できない現場
・バイアスだらけの要介護認定
・介護現場のハラスメントはなぜ起こるか ……ほか
第7章 「死ねない時代」の安楽死・再論
・安楽死を語るとき大切にしたいこと
・日本では医師任せの「グレーゾーン」
・自殺幇助と積極的安楽死を合法化すべき理由
・死を語ることの忌避感を乗り越える ……ほか

















![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


