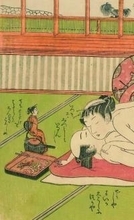今ではコンピュータで音を作れるし、ボタンひとつでエコーをつけたり、音の加工がかんたんにできるが、かつては職人たちがさまざまな工夫を凝らしていたのだ。
そんな技を駆使した効果音集「ザ・音職人」というシブイCDを入手した。元NHK音響効果チーフディレクターの大和定次さんの技術満載で、本人による「音の作り方の解説書」までついている。これをマスターしたら、宴会などで役立つかも(引かれるかもしれないけど)。さっそく、職人技を真似てみた。
まず、「犬の遠吠え」。これは小さなメガホンを使い、鳴くという手法で、時代劇などでよく使われるという。やってみた。…だめだ、私の声にしか聞こえません。ドン引き必至。
次に、赤貝の貝殻2枚を使う技「蛙」。「貝殻2枚の背中をすりあわせ、持っている指の隙間を開け閉めして交互に音色を変えます」という説明がある。
アサリ貝の貝殻二枚の背中を擦り合わせる方法で、応用編「クマゼミ」もできる。これは「最初は円を書くようゆっくり『ジ〜〜』というように擦り、次第にテンポを上げて『シャワシャワ』という擦りに変わり、スローに戻り終わります」というやり方。「蛙」よりもちょっと複雑だが、心地良い音である。いずれも注意は、ハマグリの表面はなめらかすぎるので、強めにこすったほうがいいというところか。
次に、「雪の足音」。適当な木綿の袋を作り、片栗粉を入れて手で「ギュッギュッギュッ」と揉む方法だが、手軽にビニール袋で代用してみた。ギュッギュッギュッ…確かに、それらしい音が出る。
そして、「心臓の音」。これはおおかた予想がつくかと思うが、「下敷きやボール紙を、両手を使い、上下に屈折させ鳴らします」という方法。授業中に「心臓の音!」とかやっていて、先生にぶたれた経験がある人も多いでしょう。プロの技も同じだったのですね。
他にも、ゴム風船をふくらまして水を少々つけた指でこする「お腹の鳴る音」や、プチプチのクッション材を小さなヘアーブラシでこする「線香花火」など、手軽に挑戦できる技はたくさんある。「音作り」をしていると不思議とリラックスした静かな気分になれるので、疲れたときに挑戦してみるのもいいかもしれません(危ない人に見えるかもしれないが)。(田幸和歌子)