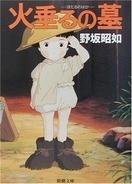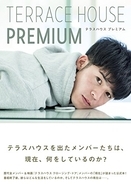名鉄バスセンターは、「名鉄バス・ターミナルビル」という建物のなかにある。このビルは、地下にある名鉄名古屋駅のホームの上に20階建ての高層塔屋が載るという形をとっていて、名鉄本社や名鉄グランドホテル、名鉄百貨店メンズ館が入るほか、3、4階がバスセンターに、5、6階と地下1階部分が駐車場にあてられている。バスセンターと5、6階の駐車場からはビルから南側に向かって斜路が伸び、大通り(広小路通)をまたいで笹島という街区にまでおよんでいる。建物本体の全長は約175メートル、斜路を含めるとじつに300メートルを超える。このバスセンターは私も子供のときから利用してきたけれど(ナガシマスパーランドへ行くときなど、ここから三重交通のバスに乗ったっけ)、バスに乗っていると斜路をあっというまに下ってしまうので、そのスケールをあまり意識したことはなかった。しかし、建物の外から回ってバスの出入り口まで歩いてみると、その大きさが実感できる。
堀田典裕『自動車と建築』によれば、1967年に竣工したこの建物は、1970年時点における一日あたりの乗降客を15万人として、一日最大3000台のバス発着を見込んで計画された日本で初の本格的なバスターミナルであり、当時、諸外国にも同じ規模の適当な事例が存在しなかったという。それだけに計画にあたっては、路線バス運行の現況や人の流れなどさまざまな方面から検討を重ねられた。その建設にあたっても、「高硬度遠心力鋳鋼管(Gコラム)」という、もともと地下鉄や高速道路の柱として用いられていた構造材が採り入れられるなど、どちらかというと建築物というよりは土木構造物というべき構造になっている(バスセンターはあくまでビルと一体になっているにもかかわらず、である)。設計を手がけたひとりである建築家の谷口吉郎が、「建築の形をした交通の立体ブロック」と表現したのも納得がゆく。
さて、前出の『自動車と建築』は、太平洋戦争後、高度経済成長にともない日本社会に自動車が浸透していくなかで、建築の世界ではどのような試みが展開されたのか、たくさんの実例をあげながら丹念に考察したものである。バスターミナルのほか、高速道路やスカイライン、それからガソリンスタンドなどロードサイドの建築にも目を向ける。
ただし本書が対象とする時代は、第一次オイルショックの起きた1973年頃まで。ロードサイドの建築、とりわけショッピングモールやファミレスなどといった「ロードサイド・ショップ」が、自動車の生んだ都市景観として議論されるようになるのは、著者自身が序章で認めているように1973年以降のことだが、本書ではそれについて多くを論じていない。著者はそれよりもむしろ、オイルショック以前に、建築家たちが自動車社会の到来に合わせて、どのような「明日」を描き、さまざまな条件・制約と格闘しつつも新たなビルディングタイプを生み出していったのか、その足跡をたどることに焦点を絞っている。
言い方を変えるなら、自動車に対する建築家たちの理想が理想たりえたのもせいぜいこの時期まで、ということだろう。1970年前後には交通事故の急増、渋滞の慢性化、排気ガスによる大気汚染など、自動車をめぐってはさまざまな問題が生じていた。さらにオイルショックによってエネルギー問題も浮上する。自動車の特性とは何より《運転する者の意思で、あらゆる場所へ移動することができる》ことであり、建築家たちの多くもそれが十分に発揮される建築や都市を夢見たわけだが、自動車を取り巻く環境は、自動車が普及したためにかえって不自由なものとなっていった。こうした圧倒的な現実を前に、自動車はもはや“バラ色の未来”を演出する存在ではなくなってしまったのだ。
もちろん、建築家たちが描いた「明日」のなかには実現したものもけっこうあるのだが、理想の消失を象徴するかのように取り壊されてしまったものも多い。前述の名鉄バス・ターミナルビルも老朽化から建て替えの計画がささやかれているし、かつて多数の大御所・若手をふくむ有名建築家たちが設計に携わった、東名・名神高速道路の各サービスエリアもその例外ではない。
たとえば、丹下健三の設計による名神高速道路の多賀サービスエリア(滋賀県多賀町)では、上り車線側と下り車線側の両レストハウスが、高速道路の本線に対して60度の角度で掛け渡されたブリッジによって結ばれているほか、駐車場の車列パターンや、建物外形から内側の間仕切り壁にいたるまですべて角度60度、すなわち正三角形を基準とするグリッド上(建築の世界でいうグリッドとは、設計の平面計画において、全体を統合しつつ、部分要素を割り振って配置し、輪郭線を載せていくための碁盤目を指す)で処理されていた。以前紹介したように、あらゆる計画において「軸線」(この場合、高速道路の本線が軸線にあたる)を重視した丹下の面目躍如といえる。
だが、この丹下の作品とても、いまグーグルマップの航空写真などで確認すると、本線上に掛かるブリッジはかろうじて残されているものの、全体的に完成時のデザインとは(『自動車と建築』の45ページに掲載された同サービスエリアの配置図と見比べるかぎり)かなり異なっている。ほかのサービスエリアもまた、建築家たちが、敷地の地形や固有の風景を生かしつつ、各人の個性を発揮し趣向を凝らしたものの、1980年代後半からしだいに改築され、標準的なデザインに統一されていったという。
最近でこそ、たとえば首都高速道路が、世界的にも珍しい大都市の中心部に建設された高速道路網として評価の機運が高まっているものの、自動車に関する建築や建造物は全体として審美的・歴史的に評価を得ているとはいいがたい。それゆえに保存するという考えが根づかない、ということもできそうだ。こうした状況を変えるためにも、建築をふくめクルマ文化全般の見直しが必要なときに来ているのかもしれない。
ところで先日、トヨタ博物館(愛知県長久手町)を訪れた際、ミュージアムショップで、「企画展:1980年代の日本車 若者に愛されたデートカー」という同博物館で5年前に開催された企画展のカタログを買い求めた。80年代に若者たちに人気のあったクルマが、それぞれに見合ったデートのシチュエーションとあわせて解説されていて、なかなか面白かった。
70年代の2度のオイルショックから、日本は先進国のなかでもいち早く立ち直ったとされる。このとき日本経済をリードしたのは、半導体産業であり、そして自動車産業であったとはよくいわれるところだ。日本車が世界を席巻するなかで、若者たちのあいだでは独特のクルマ文化が形成されていった。他方、オイルショック前後には、自動車は貨物輸送の主役の座を鉄道から奪い、宅配便や引っ越し事業などさまざまな新サービスを生んだ。映画「トラック野郎」シリーズのヒットから、トラックに派手な装飾をほどこすことが運転手たちのあいだで流行したのもこのころである。