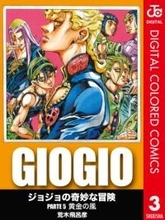今となっては隔世の感があるが、全盛期には、フジテレビのものまね王座決定戦は毎回のように視聴率が30%を超え、毎週ゴールデンタイムでものまね番組「ものまね珍坊」がオンエアされていた。
そのブームの中心にいたのは、コロッケ、清水アキラ、栗田貫一、ビジーフォーの「ものまね四天王」である。
メインストリームではなかったものまね
このブーム以前、ものまねというのは、決してメインストリームの芸ではなかった。もちろんウグイスの声帯模写で有名な江戸家猫八など、伝統芸能に近いところで認められていた人はいたが、他の芸能人を模写するものまね芸は、コバンザメ的な見方をされ、あまり褒められたものではなかったのだ。
郷ひろみのモノマネで有名だった若人アキラなどの一部例外はあったものの、当時ものまね専業でテレビに出ていた人というのはほぼいないに等しく、今のように「ものまね芸人」とくくれば何十人と出てくるような状況ではなかった。
フジテレビの「ものまね王座決定戦」も1973年からの歴史があったが、今で言えば「歌うま芸能人大会」みたいなノリの「本業とは別の余技」の範囲で競うゆるいものであった。それを証拠に第1回優勝者の森昌子から第14回の研ナオコくらいまでは優勝者はずっと歌手である。
ものまねブームが起きた背景は
それが80年代後半、「ものまね王座」の担当プロデューサーが変わり、ものまね専業の芸達者を前面に出すようになってから、いっきに世の中にものまねブームが起きた。
このブームの背景には、大きく二つの転換がある。
ひとつは、ものまね芸を単なる「似ている・似ていない」という次元を超えたひとつのネタ作品として捉えたこと。
それまで似ているか否か、だけが判断基準だったものまね芸の世界に、「面白さ」「斬新さ」が求められるようになった。
ただ普通に歌っていてはいくら似ていても評価されない。いくら素晴らしい芸でも、過去に見た芸は評価されない。これにより出場者の幅が広がり、「本格派」を極めるもの、「笑い」を追求するもの、それぞれが毎回趣向を凝らして完成度の高いネタを披露した。
(一応正統派ものまねは「オールスターものまね王座」、お笑いものまねは「爆笑スターものまね王座」と使い分けはあったが、ものまね四天王を中心に両者に出演する芸能人も多かった)
もうひとつは、余興大会的な雰囲気から真剣勝負に変わったこと。
もちろん1回戦くらいでは、ピンクの電話が着ぐるみで歌うだけみたいなネタもあり、ゆるい雰囲気満載だったのだが、優勝争いともなればかなり真剣勝負感が漂っていた。
「第3回 爆笑!スターものまね」で「どうしてもチャンピオンの称号が欲しい」といつもの下ネタを封印した清水アキラが優勝して男泣きしたり、「ものまね王座チャンピオン大会」で出場者5組中、唯一優勝経験がなかった栗田貫一がチャンピオンになって涙したり、この頃のものまね王座は優勝者が涙するのが恒例になっていた。
このように笑いを題材にしつつも、真剣勝負という舞台装置を作ることで観客を惹きつける流れは、今のMー1グランプリなどにつながっている。
ブームの中心にいた「ものまね四天王」
「四天王」と称された4組は、80年代初頭「お笑いスター誕生」で世に登場したコロッケ(当時は音源にあわせての形態模写のみだった)、かつて若手お笑いグループ、ザ・ハンダースにいた清水アキラ、コミックバンドとして70年代後半から活躍していたビジーフォー、素人ものまねからプロになった栗田貫一と、それぞれ決して芸能界的に新鮮な顔ぶれではなかった。
しかし、コロッケは過剰さ、清水アキラは下ネタ、ビジーフォーは洋楽、クリカンは正統派と、それぞれ違う方向性で高いレベルの芸があり、ものまねブームにそれがはまった。
このブームの波及効果はすさまじく、コロッケが美川憲一を蘇らせたような「ものまねが本人を救う現象」が起きたり、最盛期の「ご本人登場」でビジー・フォーの後にアース・ウィンド・アンド・ファイアーのフィリップ・ベイリーが出てきたりした。
また、ものまね芸人がコンスタントにテレビに出られる土壌ができたことで、岩本恭生や布施辰徳など四天王に続く層もどんどんと世にでるようになった。
ものまねブームの終焉
しかし、ブームというのはもろいもの。
ものまねブームの立役者であったプロデューサーの、暴力も辞さず出演者に怒号を浴びせる厳しい演出に、出演者が反発。
92年には四天王の一人コロッケが降板、その後岩本恭生なども日本テレビのものまね番組に移籍する等の事態に発展し、ブームは徐々に下り坂となっていった。
当時の状況は異常だったとしても、このブームによってものまねがテレビで見せる芸として定着したことは間違いない。
怒号飛び交う中、真剣に新ネタを考え続けた先達の絶え間ない努力があったからこそ、その後のホリ、コージー富田、原口あきまさ、神奈月、福田彩乃といったものまねをベースにしたタレントたちにつながっていったといえる。
いつの世も真剣勝負は必ず時代を変えるのである。