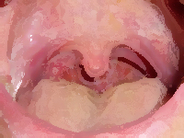日本では4月12日から渋谷のシアター・イメージフォーラムで公開されると、公開2日間の興行収入記録を打ち立てた。
映画は『アクト・オブ・キリング』(以下『アクト』)。1965年のインドネシアの動乱の際に、共産主義者や中国人ともくされた人が100万人規模で虐殺された史実をテーマにした作品だ。
このようなお堅い題目の映画が注目を集めているのは、映画評論家の町山智浩さんや映画時評で人気のラッパー、Rhymesterの宇多丸さんなど映画ファンに絶大なる影響を与える人たちが絶賛しているからだけではない。とにかく面白いのだ。テーマから想像されるお堅さはなく、文字通り笑える面白さがあるのだ。
なんと虐殺を行った張本人に、劇中で本人役を演じさせ再現させているという前代未聞のことを行っている。
監督のジョシュア・オッペンハイマー氏は2001年にインドネシアで別の撮影をしている最中に9.30事件と呼ばれるこの史実以降の実情を知り、それをテーマに映画を取ることを決意した。しかし加害者側がいまだにインドネシアの権力の中心に近いところにいるため、被害者は誰も口を開きたがらない。そこで発想を転換して加害者に話を聞いてみたところ、彼らは一様に武勇伝を語るように、当時の様子を身振り手振りを交えながら再現したという。
主人公はアンワル。現在は、9.30事件の"英雄"として北スマトラの都市で権力者として悠々自適の生活を送っている彼は好々爺然とした風体とは裏腹に、1000人規模の"共産主義者"や中国人たちを殺めた過去を持つ。
「当初は特定の主人公のいる映画にするつもりはなく、アンワルの前にも40人の加害者を取材していました。彼も他の人同様、当時の殺戮の様子を現場で嬉々として語っていました」
インタビューに応じてくれたオッペンハイマー監督は語ってくれた。
大のハリウッド映画ファンのアンワルは、その様子の映像化を提案すると、悪びれず色々な演出を考えるというはしゃぎようだった。地元で恐れられているギャングが殺人というオドロオドロしい内容を再現しようとしているにも関わらず、どこかマヌケでユーモラスな印象さえ与える。
「しかし他の人たちと違って、彼は心の底の苦痛を隠そうとしませんでした」
そこで監督は賭けに出た。
「再現を撮影した映像をすぐにアンワルに見せたのです。他のどの加害者にも見せたことはありませんでした」
というのも、それはかなりの危険を伴う行為だったからだ。自分が人を殺している映像を見させられ不快に思い、制作の意図を悟られ警察に通報されたら一巻の終わりだ。
「フィルムを見せる際、プロダクションマネージャーを空港に待機させ、無事を知らせるテキストメッセージが届かなかったらチケットを買って、すぐに全員が国外に逃げ出せるよう手配していました」
それでも客観的に自分の姿を見せることによって、アンワルが彼の心の苦痛の本当の意味に気づくことに賭けたのだ。
映像を確認するアンワルの顔に居心地の悪さが滲むと緊張感がぐっと高まる。彼からどんな言葉が発せられるか固唾を飲んで見守っていると出てきたのは意外な言葉だった。
「オレ、ピクニックに行くような(場違いな)服装しているな」
長年に渡り虐殺が正当化されてきたため、非道いことをしているという感覚が麻痺してしまっていたのだ。
「しかし彼が感じた居心地の悪さには、罪悪感も潜んでいたと思います」
そう感じたオッペンハイマー監督は、以後撮影してはフィルムを見せるという作業を細かく繰り返していく。
「アンワルにとっては自画像を描いては一歩引いて全体像を見直し、そしてまた描き進めるというような作業だったと思います」
そのような作業を5年間かけて丁寧に繰り返すことによって彼に変化が訪れてくる。そして他に類を見ないこの映画は、監督の意図をも超えたパワフルな結末に向かって展開していくのだ。
(後編につづく)
(鶴賀太郎)