一木裕佳(いちき・ゆか)さん
株式会社バンダイナムコウィル取締役。多摩大学学長秘書を経て株式会社パソナで阪神・淡路大震災後の復興プロジェクトを担当。その後、株式会社ナムコ(現・株式会社バンダイナムコエンターテインメント)に入社。産官学連携事業や教育事業を立ち上げ、2011年に小学生向けの教科書を開発。
一木さんが育ったのは、九州の典型的な男尊女卑の考え方を持つ厳格な家庭。
高校一年生の頃、姉たちに「福岡から出たい」と相談すると「親に内緒で推薦を取るしかない」と教えてもらい、東京の短大へ進学。卒業後は東京で専攻科へ進学し、父親に半ば勘当されながらも東京で得意な英語を活かして働いた。自立していたつもりだったが、「25歳までに親の認める人と結婚できなかったら戻ってきなさい」と言われていたという。
「独身のまま25歳になってしまい、約束どおり父の会社を手伝うことになりました。アメリカのバージニア州に生産拠点を設立することになり、英語の得意な私が駆り出されたのです」
海外で新鮮かつ刺激的な体験や生活。
「パソナの派遣スタッフとして、多摩大学初代学長で一般財団法人日本総合研究所初代会長である野田一夫さんの秘書を務めることに。数か月後に社員となり、野田先生から厳しくご指導をいただきながら、特に起業家精神のすばらしさを知りました。
ところが、野田さんが宮城大学の初代学長に就任。一木さんは東京へ残ったが、阪神・淡路大震災後にパソナが手掛けることになったデパートの復興プロジェクトに誘われる。迷っていた一木さんに、上司である野田さんはこう助言した。
「今後、女性は自分で生きていく時代になる。秘書は天職かもしれないけれど、これからは現場で実務を学んだほうがいい。
人生が大きく変わっていく高揚感が湧き上がり、復興プロジェクトへの参画を決めた。神戸に引っ越し、連日睡眠時間を惜しんで働いた。全く未知の領域、業態、環境、全てが手探りの中で必要な知識を必死で勉強しながら、さまざまな実務を学び、何も知らないところから切り開いていく経験を重ねる。
ゲームクリエイターと最高の教科書を作る震災復興プロジェクトが一段落した後、大学に入り直し大学院に進もうと考えていた。ところが、同じく野田さん主催の勉強会のメンバーであったナムコの創業者に「手伝ってほしい仕事がある」と誘われる。
ナムコに入社し、映画事業に係る新規事業の立ち上げなどに携わることに。
「さまざまなプロジェクトを進めるにつれ、ゲームクリエイターの才能は世の中を変える力があるほど凄いものだと実感していました。そのゲームクリエイターがデジタルではなく紙の教科書を作ったら、最高に素晴らしいものができる、そう確信したのです。また、『ゲーム脳』という批判的な言葉が話題になっていた時代に、医学的根拠がない世論に対してモノを作って反論したかった」
2011年、教科書を出版する学校図書と共同開発。そこまでの道のりも容易ではなかった。
「最初は会社の経営層からも、さすがに文部科学省の検定教科書なんて無理だろうと言われました。出版社に話を持っていっても、ことごとく門前払い。でも、何度もしつこく通ったんです。ついには社長が折れて『一木さんと心中だ。すごく当たるか、業界から大バッシングを受けるか、どちらか。でも、一木さんを信じるよ』とおっしゃってくださった。最終的には算数と国語を含めて全28冊を制作することになりました」
かくして、ゲームのメソッドを取り入れた子どもが夢中になれる「休み時間でも開きたくなる」教科書ができあがった。それは狙い通り異例のヒットとなり、有名私立校をはじめ、全国2500の小学校に採用された。
夢だった事業は、父の意志を受け継ぐもの多くのプロジェクトを立ち上げてきた一木さんだが、バンダイとナムコが合併して最初に希望した業務は、バンダイナムコウィルに携わること。障がい者雇用促進を目的としたバンダイナムコグループの特例子会社だ。
「実は、25歳から2年間手伝っていた家業は、聴覚障がい者の方々を雇用する会社でした。父がその事業を始めたきっかけは、父が経営するレストランで知り合った障がい者のお客様。『自分はほんの一部分的な身体障がいだから、いろいろな仕事ができるはずなのに、田舎には働く場所がない。家族に迷惑をかけて生きていくことが悔しい』と話されたそうです。その言葉を聞いた父は、翌朝一番の飛行機に乗って労働省に押しかけ『障がい者の人たちが働ける会社を作りたいから教えてくれ』と詰め寄り、祖父から引き継いだ事業とまったく異なる精密機器の製造会社を設立しました。
私は父の娘だというだけで、そこで働く人たちから何度も感謝の言葉をいただきました。亡くなった父の意志を引き継いで、バンダイナムコグループでひとりでも多くの障がい者の方々の雇用を創出していきたい。そう思っています」
一木さんが着任するまでは、バンダイナムコウィルとのタッチポイントが、クリーニングやメール便くらいしかなかったのだそう。
「着任してみると、実に多彩な素晴らしい能力や技術力のある障がい者スタッフがいる事に驚きました。10年希望していた私が知らないんだから、みんなも知らないだろうと思い、資料を作ってグループ会社を回り、説明会を開いたり、会社見学に来てもらったりして、グループ内PRに駆け回ったんです。また、外注している業務を障がい者スタッフに委託してもらったり、社員の残業時間の削減に繋がるような業務移管もお願いして、開拓しました」
その結果、ゲームのデバッグといった開発サポートや開発端末機の管理業務などの仕事がどんどん増えた。障がい者スタッフも大好きなゲーム。その開発の一翼を担ってるんだという自信や誇りにつながっている。
「スペシャリストでもなくゼネラリストでもない」とこれまでのキャリアを振り返る一木さんだが、すべてに通ずるのは真摯な「取り組みの姿勢」。目の前にある仕事を全力で徹底的にやり切ることで、さまざまなスキルの蓄積とともに成功が伴ってきた。これからは、長年夢見てきた職場で、ひとりでも多くの障がい者雇用を創出し、バンダイナムコらしい特例子会社としての成長を推進していく。
Q.お気に入りの化粧品は?DIENEUEの100%ピュアのモロッコ産アルガンオイル。
Q. 現在読んでいる本、愛読書は?現在読んでいるのは『悲しき熱帯』(クロード・レヴィ=ストロース)、愛読書は、『風の王国』(五木寛之著)、『九月姫とウグイス』(サマセット・モーム著)。
Q. お気に入りのファッションアイテムは?ツイリースカーフをバッグに入れておき、急な食事の予定などが入った時にはアクセントに。CLASSICS the Small Luxuryで刺しゅうを入れたハンカチもバッグに忍ばせて。
Q. 欠かせないスマホアプリは?NewsPicks
Q. 1か月休みがあったら何をしたいですか?地元でチャリティ活動に奮闘している83歳の母と、船で旅行がしたい。
撮影/柳原久子 取材・文/栃尾江美




















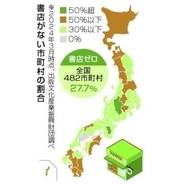


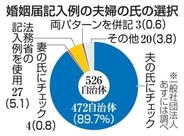



![ファンケル (FANCL) (新) 大人のカロリミット 30回分 [機能性表示食品] ご案内手紙つき サプリ (ダイエット/脂肪消費/糖/脂肪) 吸収を抑える](https://m.media-amazon.com/images/I/51+coHCYZ5L._SL500_.jpg)
![大塚製薬 ネイチャーメイド スーパーフィッシュオイル(EPA/DHA) 90粒 [機能性表示食品(成分評価)] 90日分](https://m.media-amazon.com/images/I/51vjOiqZ2dL._SL500_.jpg)




![[東証プライム上場]爪の中まで浸透・殺菌する 薬用 ジェル 北の快適工房 クリアストロングショット アルファ 爪 ケア 単品1本](https://m.media-amazon.com/images/I/41bjMPMqQXL._SL500_.jpg)



![[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N](https://m.media-amazon.com/images/I/412qbG7GTHL._SL500_.jpg)
