「駅弁」食べ歩き20年・5000個の放送作家・ライター望月が、自分の足で現地へ足を運びながら名作・新作合わせて、「いま味わうべき駅弁」をご紹介します。
平成9(1997)年まで使われた「峠の釜めし」の販売台車(おぎのや資料館にて)
現在、全国で駅弁の立ち売りを行っている駅は極めて少なくなりました。

189系電車・臨時特急「木曽あずさ」、中央本線・上野原駅(2018年撮影)
「駅弁屋さんの厨房ですよ!」第48弾・荻野屋編(第4回/全6回)
昭和41(1966)年から平成9(1997)年まで、30年あまりにわたって東京と信州を結んできた特急「あさま」号。北陸新幹線の開業で廃止になる際は、横川駅で「峠の釜めし」が販売される風景がメディアに繰り返し取り上げられたものです。「あさま」号として活躍した車両は、その後も役割を変えながら活躍が続き、長野~直江津間の「妙高」号や中央本線の臨時列車として、2010年代後半まで、東京近郊にも顔を出すことがありました。

株式会社荻野屋 髙見澤志和 代表取締役社長
昭和33(1958)年2月の発売以来、60年以上にわたって高い人気を誇る「峠の釜めし」。最近は、いままでにはあまり考えられなかったような“変わった”釜めしが登場しています。今回は釜めしの立ち売りの思い出から、いまも“変化を続ける”釜めしについて荻野屋の髙見澤志和(たかみざわ・ゆきかず)代表取締役社長にお話しいただきました。
平成9(1997)年まで使われた「峠の釜めし」の販売台車(おぎのや資料館にて)
●目迎目送(もくげい・もくそう)、声出しが徹底された売り子さん
―「峠の釜めし」は立ち売りが有名でしたが、売り子さんは何人くらいいたんですか?
髙見澤:常時20人くらいいました。本社社屋近くに横川駅の1番線ホームと直結した売り子さんの待機室がありました。売り子さんは4代目・みねじの時代からの教えで「声を出す」ことが徹底されていました。そして、目迎目送(頭を下げて列車を迎え、頭を下げて見送る)ですね。
―「峠の釜めし」は、売店でも布をかけているのが私はとても印象的で、他にやっている業者さんをまず見ませんよね?
髙見澤:これは「峠の釜めし」が、お客様が望まれた“温かい家庭的なお弁当を提供する”というコンセプトで生まれた商品ですので、保温性を高めるという観点から熱が逃げにくいように布をかけています。いまは(販売を委託しているお店もありますので)全部の売場でできるものではありません。一方で衛生面もあるので、温度管理にはとても気を遣います。いまは世界的にもご飯が炊き上がったら急速に温度を下げるのが一般的ですから。

北陸新幹線開業25周年記念「峠の釜めし」(2022年販売)
●この60年あまりで、変わった点は?
―昭和33(1958)年の発売時と変わっている点は何ですか?
髙見澤:発売した当初は内容表示がない時代でしたので、そのときの旬の食材を使っていました。残っている写真を見ると、いろいろなバージョンがあります。でも、文芸春秋に取り上げられてからは、食材の安定的な確保が難しくなり、いまの形に落ち着きました。また、草創期は錦糸玉子を使っていましたが、横浜高島屋の駅弁大会出品を機に(衛生上の観点から)うずらの玉子に、絹さやがグリンピース、チェリーがあんずに変わっています。
―期間限定モノも多いですが、掛け紙はどのようにデザインしていますか?
髙見澤:釜めしの掛け紙のベースは昔と変わっていません。昔は印刷会社にデザインを発注して、そのなかから選んでいましたが、いまは期間限定ものを中心に、ほぼ自社でデザインして作っています。最近は、期間限定の「掛け紙」を目的にお求めになる方も多いですね。釜のカラーも10種類以上あります。

駅弁味の陣2023で初陣賞を受賞した「月見の釜めし」
●増える釜めしのバリエーション!
―最近は釜めしの“姉妹品”が増えているように感じていますが?
髙見澤:いまは「峠の親子めし(鮭とすじこ)」、「峠の牛めし」、そして、冬季限定の「峠のかきめし」の3つを出しています。他にも季節に合わせて鶏、うなぎ、松茸などの釜めしを出しています。とくに松茸は、かつて販売していた「峠の松茸めし」を釜めしにしたものです。松茸は100%長野県産のものを使っていますので、本当にその年の価格に左右されます。私たちも価格設定は悩みますね。
―姉妹品を増やしている理由は?
髙見澤:「峠の釜めし」はもともと、四季の旬の食材を使って作られた駅弁です。10年ほど前に、春夏秋冬の季節限定の釜めしを販売していましたが、コロナ禍で販売を中止しました。季節限定の釜めしの代わりにさまざまな姉妹品を開発し販売を行っています。それまで弊社には「釜めしは1種類だけ」という暗黙の了解がありました。私はそういう(根拠のないルール)が大嫌いなんです。

峠の親子めし
コロナ禍以降、バリエーションが増えた荻野屋の釜めし。

峠の親子めし
【おしながき】
・味付けご飯
・塩鮭ほぐし身
・醤油漬けすじこ
・小葱
・刻み海苔
・香の物

峠の親子めし
掛け紙とふたを外すと、青いカラーの釜にいっぱい敷き詰められた鮭のほぐし身が現れました。コチラの鮭は荻野屋で丁寧に焼き上げたものだそう。そして真ん中には「すじこ」! この手の“親子”では、いくらが定番ですが、贅沢にたっぷりのすじこを使っているところに荻野屋の矜持を感じることができます。峠の釜めしと同様、別添の香の物も付いていて、アクセントを付けながらいただいていくと、どんどん箸が進みます。

横川駅止まりの信越本線・普通列車を待ち受ける軽井沢駅行のJRバス
かつて荻野屋の売り子さんが頭を下げていた横川駅のプラットホーム。いまは高崎からの普通列車が、概ね1時間に1本やってきます。列車が到着すると車止めの先で待ち受けるつばめマークが描かれたJRバスに乗り継ぐ方もいます。朝夕に見られる高校生は、碓氷峠を列車が走っていた時代にはまだ生まれていなかったのだなと思うと、25年あまりの歳月の重みを感じます。
-
 ※画像はイメージです
※画像はイメージです -
 189系電車・臨時特急「木曽あずさ」、中央本線・上野原駅(2018年撮影)
189系電車・臨時特急「木曽あずさ」、中央本線・上野原駅(2018年撮影) -
 株式会社荻野屋 髙見澤志和 代表取締役社長
株式会社荻野屋 髙見澤志和 代表取締役社長 -
 平成9(1997)年まで使われた「峠の釜めし」の販売台車(おぎのや資料館にて)
平成9(1997)年まで使われた「峠の釜めし」の販売台車(おぎのや資料館にて) -
 北陸新幹線開業25周年記念「峠の釜めし」(2022年販売)
北陸新幹線開業25周年記念「峠の釜めし」(2022年販売) -
 駅弁味の陣2023で初陣賞を受賞した「月見の釜めし」
駅弁味の陣2023で初陣賞を受賞した「月見の釜めし」 -
 峠の親子めし
峠の親子めし -
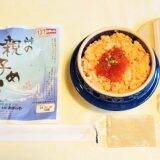 峠の親子めし
峠の親子めし -
 峠の親子めし
峠の親子めし -
 横川駅止まりの信越本線・普通列車を待ち受ける軽井沢駅行のJRバス
横川駅止まりの信越本線・普通列車を待ち受ける軽井沢駅行のJRバス
連載情報

ライター望月の駅弁膝栗毛
「駅弁」食べ歩き15年の放送作家が「1日1駅弁」ひたすら紹介!
著者:望月崇史
昭和50(1975)年、静岡県生まれ。
駅弁ブログ・ライター望月の駅弁いい気分 https://ameblo.jp/ekiben-e-kibun/








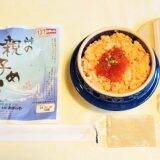































![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


