知的障害のある作家のアート作品やそれをもとにした製品などを企画、プロデュースする会社、ヘラルボニー。創業者の二人(双子の兄弟)の兄が、重度の知的障害を伴う自閉症だったことに始まる会社だ。
「私、キャリアの迷子だったんです」。その意味とは?
撮影/高木亜麗忍岡さんのキャリアを見ると、 目もくらみそうにまばゆく輝いている。
その意味を知るために、歩んできた道をたどっていこう。「アメリカで駐在員の子どもとして過ごして、帰国して公立小に転入したら、それまでの華やかな世界からはがらっと変わって、クラスにはいろんな子がいました。遠足に行っても1000円のおみやげが買えない。
しかし、東大のロースクールに通っていたが、「仕組みや制度作りをしてみたい」と路線変更した(といっても、司法試験には合格している)。法律作りの仕事は面白かったが、米国に留学してスタートアップに転職したいと思い始める。
楽しく社会課題を解決する、唯一無二のビジネスモデル
最初の出会いとなった、へラルボニーの名刺入れ。撮影/高木亜麗そんな彼女が「もう、ここしかない。どうしてもここで働きたい」と思い定めたのがヘラルボニーだった。出会いは、「名刺入れがほしい」とネットで探していて、「かわいい」と思ったのが同社の製品だった。あれこれ調べて、「こんな会社があるなんて」という驚きが、入りたい、という思いに変わっていった。
「障害のある人たちのことを、かわいそうとか救わなきゃ、とかじゃなくて、彼らの才能を引き出して、ポジティブな面に光を当て明るく華やかに売り込んでビジネスの世界で勝負しようとしている。楽しく社会課題を解決しようとしているところにひかれたんです。
当時、同社は「経理のマネージャー」を募集していた。
右脳の世界のことが起こる。刺さる人にはすごく刺さる
ヘラルボニーでの日々は驚きの連続だという。まず、「実は私の家族も障害があって……」と打ち明けてくる人の多さだった。「こんなに悩んでいる人たちが多かったんだ、とびっくりしました。そういう方たちは、本当に一生懸命応援してくれる」。
そして、「スタートアップなんですが、普通のスタートアップと違うことが次々に起こる」ことにも。たとえば、ベンチャーキャピタルの人々に創業者がピッチをした時に、「初めてピッチを聞いて震えました」と言われたこと。JALのキャビンアテンダントの強い後押しでコラボレーションが始まり、ビジネスクラスのアメニティポーチやファーストクラスのコーヒーカップに作家の図柄が採用され取り組みが広がっていった結果、「JALに転職してよかったと思えた仕事です」と担当者に言われたこと、リクシルの商材のデザインに採用された時、営業チームから「こんな商品を販売したかった」と言われたこと……。
「スタートアップでもMBAで勉強するようなロジカルなアプローチが確立されている部分があり、先行事例をモデルに定石があって指標を正しく追うことで成長を競う……、という左脳の世界があるんですが、そうではない右脳の世界のことが起こる」。人の熱とか感情とか勢いに突き動かされたようなこと。これがアートの力かもしれない。
その代わり、というか、響かない人にはまったく響かない。「『良いことしているんですね。がんばってください』で終わり。でも百人に一人、刺さる人にはものすごい刺さるんです。そういう人が、なぜか定期的に現れる」。 再現性のないモデルだ。マニュアルがなく、「学習」できない予測不能なことばかり。「AIにはできないと思うんです。そこがある意味爽快というか、これが人間の生のエネルギーだぞ、って思う」。
なぜヘラルボニーのアートが人をそんなふうに動かすのか
撮影/高木亜麗「作家たちは、別に評価されたくてやっているわけじゃない。自分たちがやりたいから、思うままにやっているだけです。よくヘラルボニーの原画を見て『エネルギーをもらえる』って言われるのは、だからかもしれないです。あるアーティストの方は『この絵は芸大で学んだ人には描けない。技術などを教えられないからこそできる表現』っておっしゃっていました」。今の世の中、同調圧力が強く、人は知らないうちに規範に縛られている。画一性や社会規範から一切外れたところに存在する作家たちのアートは、今という時代だからこそより人々から求められているのかもしれない。「閉塞感への鮮やかなアンチテーゼなんです」。
その唯一無二なモデルで、ヘラルボニーはビジネスの世界で勝負しようとしている。先行事例がないから、未知の世界への航海だ。「でも世の中を大きく変えた、歴史に残るような企業って最初はこうだったんじゃないかと思うんです。たとえばディズニー。ネズミ?アニメ?何それ、っていう。それが今では世界的な企業になりましたよね」。
誰もやったことがないから、どうなるのかわからない。でもだからこそ、そこには未知の可能性があふれている。
ヘラルボニーが描くのは、エルメスやルイ・ヴィトンといった世界的なブランドに肩を並べる存在に育つこと。そしてどんなに会社が大きくなっても、創業者の出身地であり、本社を置く岩手県盛岡市から離れるつもりはない。当事者として、地方から始めて世界へ。 今回、ルイ・ヴィトンを傘下に持つ世界最大の複合企業 LVMHが設立した世界各国の革新的なスタートアップを評価する「LVMH Innovation Award 2024」でファイナリスト企業18社に選出された。ヘラルボニーの予測できない未来はどう広がっていくのだろう。
取材・執筆/渥美 雲


















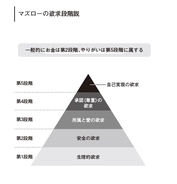






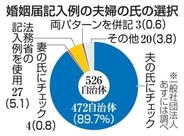

![ファンケル (FANCL) (新) 大人のカロリミット 30回分 [機能性表示食品] ご案内手紙つき サプリ (ダイエット/脂肪消費/糖/脂肪) 吸収を抑える](https://m.media-amazon.com/images/I/51+coHCYZ5L._SL500_.jpg)
![大塚製薬 ネイチャーメイド スーパーフィッシュオイル(EPA/DHA) 90粒 [機能性表示食品(成分評価)] 90日分](https://m.media-amazon.com/images/I/51vjOiqZ2dL._SL500_.jpg)



![レノアハピネス 夢ふわタッチ ホワイトティー 詰替 1,620mL[大容量]【おまけ×3付き】](https://m.media-amazon.com/images/I/513vMqlWpEL._SL500_.jpg)
![[東証プライム上場]爪の中まで浸透・殺菌する 薬用 ジェル 北の快適工房 クリアストロングショット アルファ 爪 ケア 単品1本](https://m.media-amazon.com/images/I/41bjMPMqQXL._SL500_.jpg)



![[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N](https://m.media-amazon.com/images/I/412qbG7GTHL._SL500_.jpg)
