Text by 山元翔一
Text by 小室敬幸
坂本龍一が発表した数々の音楽作品を紐解く連載「追悼・坂本龍一:わたしたちが聴いた音楽とその時代」(記事一覧はこちら)。
第13回の書き手は、『commmons: schola vol.18 ピアノへの旅』にも参加した音楽ライターの小室敬幸。
坂本龍一を「教授」たらしめたクラシック~現代音楽家としての足跡と楽曲群、そして1982年に高橋悠治に書き下ろされた“Just for Me(ぼく自身のために)”を読み解き、たどる。
批判的なビラを配ったという有名なエピソード等もあって、坂本龍一と現代音楽の関係を語る際に武満徹(1930年–1996年)の名があがりがちだ(*1)。
だが東京藝術大学の作曲科在籍中に書かれた作品が収められている『Year Book 1971-1979』(2015年)のDisc 1を聴いてみれば、当時強く意識されていた作曲家は三善晃(1933年–2013年)であることは明らか。実際に坂本本人も、この頃は三善に憧れていたことを何度も公言している(*2)。

坂本龍一(さかもと りゅういち) / Photo by zakkubalan ©2022 Kab Inc.
1952年東京生まれ。1978年に『千のナイフ』でソロデビュー。同年、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成。散開後も多方面で活躍。2014年7月、中咽頭がんの罹患を発表したが、2015年、山田洋次監督作品『母と暮せば』とアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作品『レヴェナント:蘇えりし者』の音楽制作で復帰を果した。2017年春には8年ぶりとなるソロアルバム『async』を発表。2023年3月28日、逝去。
三善晃という存在が、当時の藝大作曲科の学生にとってどのようなものであったのかが伝わってくるエピソードを、坂本の3年後に入学した西村朗(1953年–2023年)が書き残している。1970年から1974年3月にかけて藝大の音楽学部長を務めた作曲家の池内友次郎(1906年–1991年)は、作曲科に入学したばかりの新入生へ訓示として、毎年このような話をしていたという。
入学おめでとう。しかし、作曲家になりたいという君たちの夢は今が頂点です。作曲家はもういりません。三善(晃)君でおしまいです。君たちに役割があるとすれば、それは作曲もどきをする人間になることではありません。ちゃんと勉強して、古典となった音楽作品の素晴らしさを正しく理解して未来に伝えることだけです。だから音楽理論の勉強にひたすら打ち込みなさい。作曲はごく特別な、神に選ばれたような人だけに許されてきた仕事です。- 西村朗『曲がった家を作るわけ』(春秋社、2013年)
恐ろしいことに、第二次世界大戦後に藝大の教授に就任した池内自身が、まさにこの言葉を実践・体現していた。
大学1年の課題として1970年に坂本が作曲した“ヴァイオリン・ソナタ”(※)からは、三善が1960年前後に強く影響を受けていたフランスの作曲家アンリ・デュティユー(特にフルートとピアノのためのソナチネ、ピアノ・ソナタ)から学んだサウンドが聴き取れる。
大学2年時の1971年に書かれた2つの弦楽四重奏曲(先に書かれたほうは「エチュードⅠ,Ⅱ」と題されている)は、フランス音楽の強い影響下にあった三善が、そこから外れてバルトークやシェーンベルクから新たな要素を取り込んでいた時期——三善の室内楽でいえば“弦楽四重奏曲第1~2番”あたり——を想起させるのだ(*3)。
これらの作品は、第三者からみれば習作に過ぎないと軽視してしまいそうだが、“弦楽四重奏曲 エチュードⅠ,Ⅱ”(※)は2015年に、あとの2曲は2022年に坂本自身の希望で成田達輝ら、日本最高峰の若手演奏家らによって録音し直されているのが興味深い(“弦楽四重奏曲”は、テレビ番組『題名のない音楽会』でも複数回にわたり放送された)。
『Year Book 1971-1979』に掲載されたインタビューで「YMOで売れてしまうまでは自分ではロックやポップス系の仕事は、あくまでアルバイトという意識で、本職は現代音楽だと思っていた」(*4)と語っていることから、アカデミズムに追随していたこの時期の音楽も坂本本人にとって大事だったことがうかがえる。

『Year Book 1971-1979』アートワーク(詳細を見る)
アルバイトをはじめるきっかけとなったのは1972年、大学3年時の結婚という実生活上の事情が大きかったようだが、同時に現代音楽のエリート路線の象徴である三善とは異なる道を模索しはじめたのもこの頃だった。
民族音楽学者の小泉文夫(1927年–1983年)の授業を通じて(*5)、それまでのクラシック音楽および現代音楽的な芸術観——簡単にいえば、西洋芸術の文脈で個人の天才が生み出したものに価値があるという固定観念——がやわらいでいき、コンピュータによる音楽の可能性を考えていくのもこの時期だった(*6)。
それが6年後の1978年になると、ソロデビューアルバム『千のナイフ』やYellow Magic Orchestra の1stアルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』へ結実するのは言うまでもない。
だが前述の坂本の発言からもわかるようにYMOで成功を収めるまで——つまり少なくとも1978年までは——、坂本龍一の自意識は現代音楽の作曲家だった(*7)。
1974年4月に藝大の大学院(音楽研究科作曲専門課程)に進んでいた坂本は、修士2年だった1975年、ピアニストの高橋アキが初演する新作を若い作曲家向けに公募された企画のために“分散・境界・砂”を作曲する。
当時流行していた「プロポーショナル・ノーテーション」(不確定的な記譜法のひとつ)を用いているのは、三善のピアノ曲“シェーヌ”(1973年)を思い起こさせるが、鳴り響く音は三善と大きく異なっている。
現代音楽的でこそあるが特定の作曲家は強く意識されていないようで、坂本いわく「そのとき思っていることをどんどん音符にして、自分の中から自然にあふれるものを音にしていった感じ」(*8)でこの作品は生まれた。その結果、部分的にこそクセナキスの強い影響下にあった頃の高橋悠治(高橋アキの兄)を想起させる箇所もあるが、作品の核から聴こえてくるのは民族音楽風の旋法だ。
そもそも「分散・境界・砂」という曲名はミシェル・フーコーの名著『言葉と物』(原著1966年、邦訳は1974年に新潮社より)に由来しているようだ(※)。おそらくフーコーの著書を通じて、近代的な人間主体の考え方や価値観が永続的なものではないということを坂本は悟ったのだろう。
ピアニストが演奏のみならずナレーターの役割も務める“分散・境界・砂”の最後を締めくくる言葉は「作者とは誰」である。こうして三善晃に象徴される、西洋的な天才作曲家像は坂本のロールモデルではなくなっていったのだ。
大学院修士を留年して、3年時に作曲した管弦楽曲“反復と旋”(1976年)は一種のポストミニマル音楽で、ネイティブアメリカンの旋律——つまり西洋の白人文化とは異なる——要素が取り入れられているという。日本の現代音楽の文脈でとらえれば、部分的にではあるが近藤譲(1947年–)が取り組んでいた「線の音楽」(※)に接近しているのは興味深い。
だが坂本は、この路線をクラシック音楽で用いられる伝統的な楽器ではなく、電子音で歩みを進める。それが『Year Book 1971-1979』のDisc 3に収録された1978年作の“ナスカの記憶”(※)だ。
現代音楽の作曲家が個展を行なう枠のコンサートで初演された音楽(事前に収録されたシンセサイザーの録音と、即興演奏のかけあわせ)ではあるが、「アルバイト」で培ったクラシック音楽・現代音楽以外の音楽要素も取り入れたという意味で、『千のナイフ』『イエロー・マジック・オーケストラ』前夜の坂本龍一にとって集大成といえる作品だ。
『イエロー・マジック・オーケストラ』が細野の目論見どおりに海外で評価・商業的に成功。
YMOとして成功を収めていた1981年、学生時代から影響を受けていた高橋悠治のために1曲のピアノ曲が書き下ろされた。それが“Just for Me(ぼく自身のために)”だ。
もはや現代音楽的ではなく、三善晃以前に坂本が惹かれていたドビュッシー的な和声への回帰。そして冒頭と結尾に置かれたアジア的な旋律(朝鮮のメロディーだという)……と、この曲の特徴を抜き出していくと、“千のナイフ”や“東風”のアザーサイドとして生まれた、共通する要素をもった作品であることが視えてくる。
言い換えれば“ぼく自身のために”は、坂本が現代音楽と決別しながらも、あらためてクラシック音楽と手を取り直した重要作なのだ(*9)。
1990年代末に『BTTB』(1998年)でもう一度、坂本はクラシカルなピアノソロに原点回帰するが、このときには葛藤があまりなく、ストレスフリーな「癒やしの音楽」として受容されたのは当然だったように思う。“ぼく自身のために”や、クラシック音楽の演奏家たちによってカバーされた“東風”を聴いてもらえれば、それがよくわかるはずだ。

















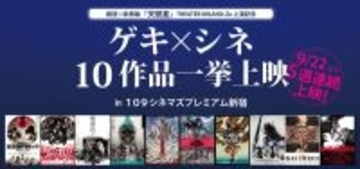












![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








