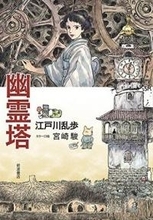エンディングなんか必要ない。
レースゲームを見るといつも「タイムなんか気にしないで、コースの隅々まで見て回れるモードがあったらいいのになー」と思っていた。レースで優勝するよりも、コースをはずれてどこまで走っていけるか試してみたり、道路脇のカンバンを裏から見たらどうなっているのか確かめてみたりするのが好きだった。
「テストドライブ アンリミテッド 2(TDU2)」(プレイステーション3/Xbox 360/PC)の内容を一言で表すなら、「そういうゲーム」である。
他のレースゲームとの違いは、何と言ってもその自由度の高さ。公式サイトを見ると、ジャンルは「カーライフシミュレーター」とある。本作は「レースに勝つゲーム」ではなく、あくまで「カーライフを楽しむゲーム」なのだ。
もっと具体的に言うと、まずマップがむちゃくちゃ広い。本作のマップは実在する「島」をまるごと再現していて、総面積で言えば東京23区(約2200平方キロメートル)とほぼ同じくらいの広さがある。
第二に、決められたコースというものがない。遠くに見える高い山も、誰かの家の裏庭も、目に見えるところはだいたい走れる。
第三に、決まった目的というものがない。なんでもできるし、何もしなくてもいい。レースでお金を稼いでもいいし、だだっ広いマップの中をひたすら走っているだけでも楽しい。僕はもっぱら、好きな音楽をかけながら島の外周に沿ってゆるゆるとドライブするのが好きだ。
前作はハワイのオアフ島が舞台で、今作ではさらに、世界遺産としても有名なスペインのイビサ島が新しく追加された。
どちらの島も、実在する道路や観光名所を忠実に再現してあって、ドライバー視点に切り替えて走ると、本当にホノルルのビル街やイビサの旧市街をドライブしているような気分になれる。ダイヤモンド・ヘッドやワイキキ・ビーチなど、テレビや雑誌でよく見る観光名所を巡るのもいいが、山の中に突然現れる吊り橋とか、道なき道をひたすら進んでようやく辿り着ける絶景スポットだとか、自分以外誰も知らないような秘密の場所を見つけたりするのも楽しい。全部の道路を走覇するには膨大な時間が必要で、「今日は島の北側まで走ってみようかな」とか、「このハイウェイはどこに通じてるのかな」とかやってるだけで時間はどんどん過ぎていく。
僕の大好きな「目的のないゲーム」のひとつに、「夜のゲーム大学」でおなじみの飯田和敏さんが作った「アクアノートの休日」がある。潜水艇を操り、真っ青な海中をひたすら探索するだけのゲームで、そこには倒すべき敵も、目指すべきゴールもない。
このゲームで遊んでいると、ふと「アクアノートの休日」とイメージが重なる瞬間がある。そういえば、真っ青な海底で見たこともない海洋生物に出会った時のうれしさと、山道を走っていてふと古びた吊り橋を見つけた時のドキドキ感はよく似ているような気がする。「TDU2」は、現代の「アクアノートの休日」なのだ。
正直なところ、純粋にレースを楽しみたい人にとっては、本作はやや物足りないかもしれない。そもそも実在の島が舞台なので、どうしてもレースは公道が中心となり、全体的に狭くて走りにくいコースが多くなってしまっている。
教習所でライセンスを取らないとレースに参加できなくなってしまったのも「のんびりドライブ派」にとっては残念な点。総じて「ドライブ派」のプレイヤーにとってはレース部分が足かせにしかなっていないのが辛い。
とは言え、それでもがんばってレースをクリアしようと思えるのは、ドライブ部分の要素が前作以上に充実しているからだ。単純に島がひとつ追加されたのも大きいが、「写真撮影」や「まだ走っていない道路の走覇」「クルマや家のコレクション」「島のあちこちに散らばったスクラップ探し」など、ドライブ中の楽しみは前作に比べてぐっと増えた。また前作にはなかった「時間」「天気」の概念も新たに加わり、同じ道路でも昼と夜、晴れと雨とではまったく違った表情を見せる。前作ユーザーなら、タンタラスの丘からホノルルの夜景を拝めるようになっただけでも感動モノだろう。
レースに参加したくなければいっそ参加しなければいい。レースなんて気が向いた時にでもちょっと遊べばいい程度のものなんだ、ということに気付くと、本作のカーライフは俄然心地よいものになる。
近ごろのゲームは、プレイヤーが迷わないようにいちいちゲーム側で「次はこうしろ」「その次はああしろ」と指示してくれるものが多い。指示どおりに動いていればゲームが進んでいくのは楽だけど、たまに「ゲームで遊んでいる」のか「ゲームに遊ばされている」のかわからなくなる。
たまには僕らを縛り付けている「目的」ってやつを、一旦忘れてみてはどうだろう。コースをはずれて、ゆっくり周りを見渡してみたらどうだろう。
ジェットコースターのようなゲームもいいけど、ゆっくりだからこそ見える景色だってあるんだよ。(池谷勇人)