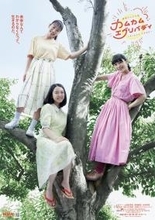「ゴールデンカムイ」3話は主要キャラクターの顔見せをしつつ、アイヌ文化の根幹を紹介する回。
アイヌの知恵と信仰は、今後の物語に大きく影響するだけあって、かなり丁寧に描かれている。アクションシーンとあわせて振り返ってみたい。

ヒグマと兵士
兵士に追われた杉元が、ヒグマの巣に飛び込むシーン。
アシリパ(リは小文字)いわく「アイヌの言い伝えにこういうのがある「ヒグマは巣穴に入ってきた人間を決して殺さない」」。
杉元は1話でヒグマに散々な目に合わされたのに、彼女の言うことを命がけで信じたというのがこの場面のキモだろう。
調子に乗った兵士がヒグマと戦う場面は、原作でも屈指の残虐シーン。
うまく放送規制にひっかからず、かつ隠しすぎないさじ加減で描いてくれた。北海道の自然の厳しさを表現するには、ここは絶対欠かせない部分だ。
ヒグマと戦った兵士は、内臓もあらわにゴミのように木の上に打ち上げられた。
銃を向けた兵士は、顔の皮を一撃で剥がされた。
ヒグマ、怖い。
しかし顔の皮が剥がれて死にかけているのに、ヒグマに銃弾を撃ち込み続ける第七師団の兵士の狂気たるや。
後半出てくる、第七師団率いる鶴見中尉が上官の指を食いちぎるシーンとあわせて「第七師団やべえ」を印象づけてくれた。
この作品は、一兵卒まで含めて、変人しかいません。
強くて元気なアイヌ

実際の北海道は、今もアイヌ文化を守ろう、という動きが続いており、小中学校で特別授業として習うこともある。アイヌをモチーフにしたレリーフや展示は、北海道だといろんな町にある。何より北海道の都市の名前は大半がアイヌ語。アイヌ文化はそんなにマイナーなものではない。
なのに、アイヌを題材としたマンガ・アニメは少ない。
野田サトル「デリケートな題材だから、だれもが尻込みしていたのもあると思います。やはり迫害や差別など、暗いイメージがついてまわりますし」「取材でお会いしたアイヌの方からも言われたんですよ、「可哀想なアイヌなんてもう描かなくていい。強いアイヌを描いてくれ」と」(『ゴールデンカムイ』野田サトルインタビュー ウケないわけない! おもしろさ全部のせの超自信作!(このマンガがすごい!WEB)より)
15世紀以降のアイヌと大和人の歴史は、血で血を洗う争い続き。明治以降、蝦夷地は「北海道」となり、開拓がはじまる。アイヌの文化はいやしいものと扱われ、土地も生活も圧迫され、差別されてしまう。
この事実自体は、今も伝えるべきものだろう。
フィクションとしての「ゴールデンカムイ」を見てみよう。
アシリパのアイヌコタン(小さな集落)は、みんなが仲良く協力して日々の生活を送っている。子供たちは伝統的な遊びをしながら、笑顔に溢れている。
あたたかいチセ(家)の中で、口に入れ墨をした祖母のフチの頬を引っ張るアシリパ。フチは杉元にアイヌ語で「この女の子を嫁にもらってくれ」と言い、アシリパ赤面。
厳しい自然の中だから苦労はある。けれども、アイヌの伝統的な知恵で狩猟と農耕を行い、信仰を守って暮らす様子は、幸せに満ち溢れている。
なにより、アイヌの飯はうまそうだ。
今回細かく、でも美化せずにアイヌ文化が描かれた。これからの「ゆかいなアイヌの生活」のシーンにも、かなり期待ができそうだ。
前回控えめだったアシリパの変顔は、今回はだいぶ解禁。
「女らしくあるべし」という風習に縛られず山林をかけるアシリパは、新しい時代の強いアイヌだ。変顔で杉元を威圧する彼女は、「女」であることをキャラクター達からも作者からも強要されていない。
(たまごまご)