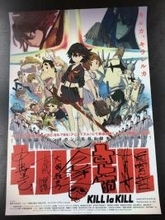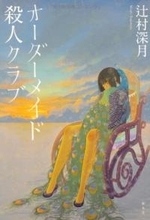夏ですね! 暑いですね!
暑い夏はロリコンのあり方について考えるのにもってこいですね!
……今回は「夏の文庫五冊を選んでね☆」と言われたので、「じゃあロリコンを描いた小説で」と言ったら「いいよ」と言われたのですが、いいんでしょうか。
まあいいか。
ベタなところから変化球まで、様々な「ロリコン小説」の文庫を集めてみました。
と言っても「ロリコンが喜ぶ文庫」ではありません。内山亜紀とか千之ナイフとか入れてません。
ロリコン的な少女描写や、ロリコンの苦悩と十字架を描いた作品群です。
夏の海ではしゃぐ若者達を見ながら読むといい気分になれると思います。
『眠れる美女』(川端康成)
文豪川端康成は少女を非常に丁寧に美しく描く作家です。「伊豆の踊子」とか超かわいいイメージありますよね。読んでいる人の中の「ベストオブかわいい女の子」を想像させます。
彼の少女への強烈な愛情を歪んだ仕方で描いたのがこの「眠れる美女」という作品。伊豆の踊子がホワイト川端康成なら、こちらはブラック川端康成です。
歳をとって性欲を起こさなくなった爺さんたちが訪れる、口伝えで信頼出来る人にしか知らされない秘密の宿。
そこに行くと、死んだように眠る全裸の少女達と添い寝ができるのですよ。
ここで興奮してしまう人はたぶんこの宿にはいけないのです。理由を聞いてはいけない、ただ受け入れることができて、女の子に悪いいたずらをしない人のみが添い寝できるのです。
どんなに起こそうとしても絶対起きないというこの謎の宿。当然しゃべりませんし、反応もしません。人形や死体と添い寝しているような奇妙な錯覚を受けます。
少女達の美しい身体描写はまさに川端流。読んでいてまるでそれは景色のように描かれます。しゃべらないし動かないので身体表現だけで少女達を描き分ける様は圧巻。
しかし後半、一人の少女が死にます。いや、死んだかどうかも定かではありません。
熟れ過ぎて腐敗してしまったような少女愛と老衰への恐怖が混在する、奇妙な作品です。
『鍵のかかる部屋』(三島由紀夫)
三島由紀夫といえばどちらかというと美しい男性肉体美を強調する作家ですが、この作品では珍しく少女への倒錯的感情を描いています。
若手エリート完了の一雄という男は性癖的には非常にノーマルなんですが、ある日9歳の少女房子と出会って人生ががらっとかわってしまいます。
9歳の子を膝に抱いた一雄は「こいつは端的な肉だ」「肉の温度と重みを正確にはかった」と目覚めてしまいます。エロティックな感情というよりも、9歳の房子を美術品のように最初感じるのです。
面白いのは彼の中で房子があまりにも美しかったために、人間の女性に対する情欲ではなくて「少女」という物体として捉えていること。だから何度も「引き裂きたい」という表現が出てきます。
美しいものを破壊したいというのはなんとも三島由紀夫らしい表現ですが、愛でるわけではなく破壊したいという願望は一雄を攻めさいなみます。
途中一雄は「誓約の酒場」の夢を見ますが、ソドムとゴモラのような退廃感に満ちています。自分はいだいてはいけない感情を抱いている、そこにどうしようもない満足感を得ているんです。
うーんなんだそれ、と分からない方も多いと思いますが、後半房子に初潮が訪れ、一雄が房子にキスをした時唇が湿っているのを感じて一気に現実に引き戻されるのを読むと彼が何を少女に求めていたかわかります。
でもタイトルの通り、ここは鍵のかかる部屋。もう戻れません。
『澁澤龍彦初期小説集』(澁澤龍彦)
様々な作品が収録されている短編集ですが、是非読んでいただきたいのが「人形塚」という短編。
主人公は子どもが大嫌いな小学校教諭。学校で生徒を教えるシーンのまあ酷さたるや。愛情もへったくれもありません。
しかしある日、人形塚と呼ばれる供養塔のような場所に、生徒の体を見つけます。
普通であれば「死体だ!」とパニックになるところですが、彼はこれを見て「すばらしい!ほんとうの人形だ……」といって連れて帰っちゃうんです。
人形だから欠損があって壊れて捨てるだろう、という思い込みがある彼なんですが、最初の人形(?)は歯列矯正器がついていました。二つ目の人形(?)は金属の義足をつけています。いずれも生徒……の人形(?)です。
もう徹底してそれが本当の死体なのか人形なのか分からないんです。
その二体を家に持ち帰り、見つかってはいけないからとシートを敷いてバラバラにするシーンは、見てはいけないものを見ているかのような、だけど興奮する彼の気持ちがぐいぐい伝わってくるような極めて珍妙な描写になっています。
一体これはなんだったのかは読んでみてください。ネクロフィリアや人形愛に通じるロリコン的感情の末路の一つが描かれています。
『グランド・フィナーレ』(阿部和重)
いきなり余談ですが、この作品第132回芥川賞受賞作品です。そのころロリコン作品に対しては結構敏感に論じられていた時期だったため、NHKで受賞作品を告知した際にいかにロリコンっぽさを出さないか相当苦労していたそうな。まあ、文学は文学だとはいえ、言いづらいわよね、うん。
妻と最愛の娘を失った男が主人公なんですが、こいつがとんでもないくせもの。
元々は教育映画監督だったのですが、この自分の立場は子どもと接する事が多い。それを利用し、少女達の裸を撮る趣味に高じてしまいます。
遊び感覚で一人に手を出していますが、それが目的ではなくて「映像に収めたい」というあたりがなんともロリコン二次元コンプレックスっぽくてなんとも業が深い。そりゃバレたら娘も何もかも失いますよ。
まあ笑い話であれば「ZIPでくれ」とオチをつけることもできますが、彼のこの悲劇めいた喪失感の隙間に、フォローに入るかのような女性が登場。一瞬彼も救われたような気持ちになります。
ところが! 彼女は少女側のトラウマの現実をものすごい勢いで主人公にたたきつけ、自分の悲劇に酔うんじゃねえよバカヤロウとばかりにぶん投げていきます。
第二部ではこれで目覚めた主人公が、二人の少女を死の淵から救おうと全力を費やすのですが、一番興味深いのはやはりつい趣味感覚で手を伸ばしてしまったロリコンの世界、そして絶望と贖罪の流れでしょうか。
背負った十字架は大きいのです。
『ステーシーズ―少女再殺全談』(大槻ケンヂ)
筋肉少女帯のボーカル、大槻ケンヂによる小説。
少女美をひとつのテーマとして様々な作品で描いていますが、中でもこの「ステーシー」シリーズは、今まで見たこともない言葉の使い方で、失われゆく少女の姿を描いた白眉な作品です。
15歳から17歳までの少女達は謎の理由で世界中で変死を遂げ、ゾンビのような歩きまわる屍ステーシーになって人を襲います。
これはそんな死んだ彼女たちを「再殺」するために少女の姿を見つめる物語。
まだ生きている少女達は、悲嘆に暮れません。死ぬ寸前には「ニアデスハピネス」と呼ばれる多幸感に満ちた状態になるから。そこで自分を再殺してくれる人を選ぶのです。
再殺された死体を見ながら「こんなふうにぐちゃぐちゃにしてね」という少女の姿はあまりにも愛しく、切なさに満ちています。恋人、妹。
痛みも知能もないステーシー。再殺されていないステーシーは再殺部隊によって165分割以上にバラバラにされていきます。
後半、モモという知能を持ったステーシーが登場し、事態は一変します。狂った世界は微調整をはじめ、ステーシーはペットのようになり、増え始めた畸形少女はハムエと呼ばれ、そして人類は「ロスト」と自虐的に名乗り始め、共存をはじめます。
少女達がどんなに人形化しようとも、最後の最後にはステーシーを、少女を愛する姿が刻まれているのが特徴的な本作品。
少女愛そのものの感情とは少し違いますが、男性が持つ少女への畏怖と憧憬はロリコン的な怪作です。
「ロリコンは罪」という文学作品は他にも「少女病」「ロリータ」等色々ありますが、そこから少女美に向かうのか、愛情に向かうのか、破滅に向かうのか色々読み比べていくと興味深いです。
夏祭りではしゃぐ若者達を見ながら読むといい気分になれると思います。
(たまごまご)