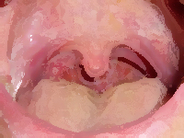医者の息子として生まれ、福島県内有数の進学校から東大へ進み、博士課程に在籍する。
その開沼の最新刊『漂白される社会』 では、ホームレスギャルの移動キャバクラ、売春島、脱法ドラッグ、裏カジノなどと、王道とは程遠い「周縁」の世界ばかりが掘り下げられている。
一般企業に就職 することを「民間に行く」と言って憚らないカルチャーの東大街道を歩みながら、勝ち組と呼ばれる人が一生触れることもないようなテーマばかりを、なぜ開沼は追い求めるのだろうか。
「高校時代は勉強ができれば文系なら法学部、理系なら医学部を目指すべきという価値観の中で過ごしました。医者になりたいわけでもないのになんで医学部を目指さなきゃいけないんだろうと悶々としていました」
そのなか出会ったのが、社会学者・宮台真司だった。
「オーム真理教やブルセラ・援助交際など、社会の周縁部のフィールドワークをしっかりされていた宮台さんは『もういい大学に入って、いい会社に入れば幸せになれる時代じゃない』と言い切ってくれました。
その思いを胸に学部時代から実話誌のライターの仕事を求め、売春からヤクザに関するものまで「何でも取材した」という。ひ弱なエリートと対極にあるタフなその実体験こそが、無精髭に包まれた肝の据わった今日の開沼の面構えを培ってきた。
『漂白される社会』は、そうしたエリートとハードボイルドのハイブリッドである開沼の真骨頂だ。
先に挙げたものの他、夜逃げ後処理屋、生活保護受給マニュアル、援デリ、右翼/左翼、偽装結婚、ブラジル人留学生、中国エステママなど、お行儀のいい人なら目を背けたくなるような12のテーマが章分けされてルポタージュ形式で語られる。
それぞれのルポは文句なしに面白い。正解のないテーマに対し紋切り型の結論を嫌い、著者に可能な限りの深淵を捨て身に希求しているのが伝わってくる。
これらの多くを善良な市民は「あってはならぬもの」と考えている。しかしそれらから目を背け「なかったこと」にすることによって「すっきりする」人々の態度に開沼は疑問を投げかける。
「たとえば、最近問題になった橋下大阪市長の従軍慰安婦に関する発言ですが、確かに政治家の発言としては不適切だしその後の対応も上手くないと思います。しかし炎上させて、叩いてすっきりして終わらせる人がどれだけ社会のことを考えているのか疑問です。皆が聖人君子というわけではないですから、叩いた後のすっきりできない残余にどれだけしっかりと目を向けるかが大切ななのではないかと思います」
こうした問題意識に支えられ、徹底したフィールドワークに基づく各章の物語は、実話誌仕込みのエンターテインメント性に富んでいる。同時に各章を序章と終章とで挟み込むことによって学術論文的のような仕上がりにもなっている。
「大学などアカデミズムの世界もチャレンジしなくなってきています。先人たちが築いてきたパターンをマイナーチェンジするだけの人が多い。枠組み自体を作り変えることが重要だと思うので、敢えてアカデミズムとジャーナリズムの双方で通用するものにチャレンジしたかったんです」
アウトローを描くときも社会の弱者を描くときも開沼の筆致はあくまでクールだ。善悪の予断を挟み込まないのはアカデミズム的訓練の賜物でもあろうが、それだけではない。
高校時代、NHKの解説員であるOBが母校を訪れ「フランス革命は、当時の熱狂の中、冷めた目の傍観者が文章に残したからこそ歴史に記録されたのだ」と言う話をしたのを聴いた。
書き留められなければ歴史に残ることのことのない事象の記録人として、開沼は書き続ける。『漂白される社会』で扱われている「周縁」的テーマは、単発的にマスコミで取り上げられることはあっても、決して歴史に残るような内容ではない。アカデミズム的方法論を用いてそれらを歴史に記録しようとする試みが本書の隠れたテーマだ。
ハイブリッド開沼は、アカデミズムかジャーナリズムかというフィールドのカテゴリーには一切拘泥しないという。
「腰を据えて取材をさせてくれる環境があればそこに身をおきます」
歴史の記録人は、ただひたすらにペンを走らせ続ける。
(鶴賀太郎)