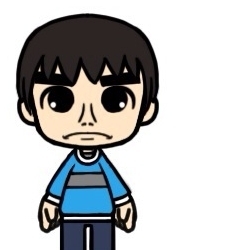そもそも初代「シムシティ」が発売されたのは1989年。プレイヤーが「市長」となり、「シム」と呼ばれる市民が住む街を作るシミュレーションゲームだ。
何もない荒野に発電所を建て、道路を引き、住宅地を作る。街の配置によっては公害や渋滞が起こる。所持金を増やそうと税率を上げれば人口が減る。突然地震が発生して街が壊滅状態になる…。
あちらを立てればこちらが立たず。ほとほと困りつつ、やりくりして都市を育てるのがシムシティの醍醐味。困難を乗り切れば、それだけ街も発展してくれるのだ。
『Simcity Buildit』は、この「困難」が激減した。
予算や税率はなくなった。
建物は自由に移動できる。道路の建設は無料だ。「やっぱりこっちに古いアパートを集めて旧市街っぽくしよう」など、思いつきでレイアウトを変えたっていい。
また、これまで住宅はシムが建てていたが、『Simcity Buildit』ではプレイヤーが住宅を建てるようになった。住宅の建設には「資材」が必要になる。
資材は工場や店舗で生産できる。工場で生産できるのは鉄や木材などの原料。店舗では原料同士を組み合わせて資材を作る(木材+鉄=ハンマーなど)。そのうち建築現場からの指示が「テーブルとドーナツ2つとスニーカーをくれ」みたいになってくる。
着工後、どんな住宅が建つかは地価で決まる。地価はインフラや治安などの住環境で決まる。電力が足りなければ廃墟になるし、工場が近ければ地価が下がる。住環境が大切なのは、旧作と一緒だ。

この大胆なシステム変更は、「スマホ」に最適化した新しいシムシティを生み出した。
これまでのシムシティは、モニタの前に座り、常に街の様子を見ながら調整をする必要があった。対して、スマホゲームの場合、1回のプレイ時間はとても短い。
電車待ちなどの隙間時間にプレイするスマホのスタイルは、じっくり腰をすえるシムシティと相性が悪い。だから、短い時間で気軽に遊べるようにする必要があった。
システム変更のもうひとつの理由は、「フリーミアム」モデル。基本プレイを無料とし、ゲームを有利にするアイテムを有料とする仕組みだ。
『Simcity Buildit』も基本プレイを無料にし、「シムキャッシュ」という有料アイテムを設けた。シムキャッシュを買えば、所持金を増やしたり、資材の生産を早めることができる。
じっと資材の生産を待てるなら、シムキャッシュ無しでもプレイに支障は無い。どうしても行き詰まった時や早くビルを建てたい時に、お金で解決できる手段として使うといいだろう。
3Dで描かれた街には時間の流れがある。ふと自分の都市を観ると、ビル群に朝日が登っている。夕日が沈み、夜景が輝く。ズームアップすれば歩行者も車もいる。海に近づけば波の音がする。二本指でグリグリ回して、好きなだけ眺められる。
筆者の街は20万人を突破した。もっと人口が増えると、ピサの斜塔やオペラハウスなど、世界の名所が建てられるようになる。海辺に自由の女神を建てたくて、今日もニョキニョキとビルを伸ばしている。
(井上マサキ)