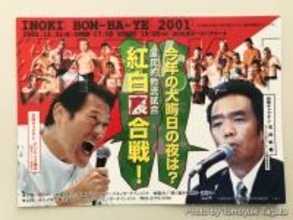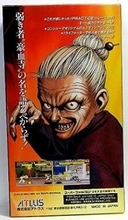たしかに、映像化された途端こける作品は少なくない。でも今回のドラマ化に際しては二宮和也やビートたけしといった手練がキャストで揃っていただけに、あまり心配はしていなかった。……にしても、良い。脚本も小気味よく、みんなが幸せになれたドラマ版ではなかっただろうか?
ボキャブラ以前に起きたお笑い小ブーム
談志と談春の師弟物語が主軸の同作だが、弟弟子・志らくとのライバル物語にも思うところがあった。
実は私が彼らを初めて見たのは、落語ではなくコントであった。かれこれ、20数年前。カジュアルな衣装に身を包む若手らに混じり、妙に若さのないネタをする2人組がいた。コンビ名は「立川ボーイズ」(元は朝寝坊のらくを加えた3人組)。
1991~1992年頃、陣容が揃った当時の若手芸人らによってお笑いの小ブームが起こっている。
『タモリのボキャブラ天国』(フジテレビ系)に若手芸人が起用され出したのが1996年ごろなので、それより一代前の世代に当たるだろう。メジャーどころで言えば、ホンジャマカやバカルディ(現・さまぁ~ず)、爆笑問題やデンジャラス辺りが名を連ねていた当時の若手勢力図。
この頃の若手もアイドル的な扱われ方をされていたが、ボキャブラブームよりはもっと芸人然としていた印象がある。
当時も、やはり吉本興業の力は強大。
後の大物も、高田文夫には最敬礼
そんな中、放送作家の高田文夫が見どころのある関東芸人を招集し、結成させたのが「関東高田組」である。
今考えると、スゴい面子だ。浅草キッド、大川興業(大川豊、江頭2:50など)、春風亭昇太、立川志らく、立川談春、松村邦洋。これらのレギュラーメンバーに加え、前述のホンジャマカやバカルディ、梅垣義明、吹越満、電撃ネットワークといった異常に個性の強い若手らが出入りする。
東京の笑いを愛する高田が自分の趣味嗜好で集めた有望株を可愛がり、レギュラー番組(フジテレビ『たまにはキンゴロー』)やライブイベントで、知名度向上と育成を目指す。
特に縛りはなく、何となく集まった当時の関東若手トップグループといった程度のものだろうか。とは言え、パルコが高田組を起用してお中元用ポスターを製作しているので、やはりそれなりに結束はしていた。
もちろん、上下関係は異常にピシっとしている。『赤めだか』では高田を前に談春が緊張する一場面が描かれているが、ビートたけしの相棒(ビートきよしとは違う面で)として、また立川談志の腹心として、高田は関東演芸界のトップに位置する重要人物である。若手が硬直するのは当然だ。
高田組の出世レース 意外な芸人がトップに
当時は今と比べてネタ番組も多く、若手の漫才やコントを目にする機会に恵まれていた。
20数年後の今、冷静な気持ちで回顧すると、浅草キッドが最も“本命視”されていたのは動かしようのない事実である。
今でこそ妙に達観した空気感をまとっているが、初期の2人の漫才は危険球のオンパレード。芸能界の裏情報とプロレストピックを散りばめた漫才は、テレビ放映されるやピー音が被さるのが常であった。彼らのキレ味は心地良く、過激な笑いを欲する客の琴線に触れまくり。キッドは、高田組の番頭的役割を担っていたと思う。
一方、立川談春と“キレ者”立川志らく(「フランスにシラクという切れ者がいるからあやかるように」と、談志から命名された)による立川ボーイズはどうだったか?
『赤めだか』を読むと、「俺達立川ボーイズで売れ損なった」という志らくの台詞がある。彼らはやはり噺家であり、他のコント師と比べると妙なまどろっこしさがあった。少なくとも筆者(当時はたかだか中学生だが)には、そう感じられた。「チャップリンは神様です」と公言する志らくだが、その嗜好は落語に落とし込まれてこそ活きた、という気がする。
そんな中、高田組のマスコット的存在であった松村が、あれよという間に一般層へ浸透してしまう。きっかけは『進め! 電波少年』(日本テレビ系)でのレギュラー抜擢。「渋谷のチーマーを更生させる」「牛のゲップを吸いきりたい!」という異常であり非情な企画にチャレンジし続け、飛躍的に知名度をアップさせていった。
自分でネタが作れないので「もしもビートたけしが売れてなかったら」というピン芸を浅草キッドに作ってもらい、高田組主催のライブがあれば演者側よりも高田のサブとして進行役を務めることも多かった松村。なるほど、よく考えると初めから別格だったのかもしれない。
「ああいうのって、楽屋受けの面白さなのにさ、まさかこれほど世間に認知されるとは俺も思わなかったよ(笑)」(高田文夫による発言 ムック「続 キンゴロー」にて)
何だかんだで、今ではほとんどの芸人が一目置かれる存在になっている。若手時代の出世レースで後方を走っていた者が大成したり、順調だった者が思いもよらぬ立ち位置で活躍していたり、人生いろいろだ。そして、現在へ至るまでには言葉にならぬほどの苦境を乗り越えてきているはずである。
それにしても芸風といい客席からの視線といい、やはりこの時とボキャブラブームでは若手芸人の有り様がかなり違って感じられる。個人的には、「ボキャブラ以降」という言葉があっても違和感はない。転換期だったのだろうか。それとも、思い入れの違いか? 私は、この時代の若手芸人の出世レースを見ているのが大好きだった。
(寺西ジャジューカ)