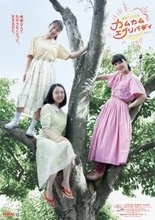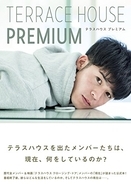前回のラスト、弟子の与太郎に聞かせる形で八代目・有楽亭八雲の語りが始まった。時代は一気に戦前へと遡り、昭和10年代まで戻る。ゆえあって七代目・有楽亭八雲の内弟子へと預けられた「坊」こと前座名・菊比古(のちの八代目八雲)と「信さん」こと前座名・初太郎(のちの有楽亭助六)は同日同刻に師匠宅の門をくぐり、弟子入りする。修業を開始した2人が数年後、初高座を踏むまでが第2話の流れである。
落語の世界では入門順が絶対
ここで大事なのは八雲宅の門前で菊比古と出くわした初太郎が、先んじて中に入って先に弟子入りした既成事実を作ろうとすることだ。落語の世界では年齢と無関係に一日一刻でも早く弟子入りしたほうが「兄さん」であり、その順列は出世の如何に関わらず一生続くからである。
この決まりはもちろん現在の落語界でも守られている。ただし、何をもって「入門」と見なすかは団体によって違うはずである。たとえば落語協会では、師匠に弟子入りをお願いして許可された日ではなく、協会に届けを提出した時点で落語家の見習いとして認められたものとされる。若手真打として人気のある春風亭一之輔は、師匠・一朝が機転を利かせてくれたおかげで得をしている。一朝は一之輔に、入門を認めたその足で協会事務所に伴い、履歴書を出させたのだ。
一之輔 (前略)うちの協会は履歴書を提出した時点で登録されるんです。だから履歴書を出した瞬間、パシーンと香盤(注:序列)が決まる。
前座は入場料の内に入らない存在
菊比古と初太郎は入門してから前座として初高座を勤めるまで数年が経っているが、それだけの時間がかかる例は実際には少ないはずで、皆いくつも噺を憶えていない、本当の卵のような状態で寄席に出ることになる。だからこそ「前座は入場料の内に入らない」などといわれて、名前を書いた「めくり」なども準備してもらえないのである。誰もお客がいない状態で高座を勤め、中には「客が入ったから降りろ」などと噺の途中で引きずり降ろされた経験をした者もあるという。
それだけに、初高座がめろめろになるのはむしろ当然である。アニメでは、菊比古は「子ほめ」を掛けて惨敗、初太郎は「時そば」で客を沸かせたが、むしろウケるほうが異例の事態といえる。どんなに酷い高座であっても楽屋の先輩は「良かったよ」「うまくなるよ」と迎えるのがしきたりだ。後輩を思いやる態度が、代々受け継がれているのである。
「野ざらし」を演じたのは立川こはる
今回話中で演じられたのは「野ざらし」「子ほめ」「時そば」の三席だった。
「野ざらし」は釣りに行った男が女の骨を発見して供養してやることから始まる奇譚で、昭和の落語家ではなんといっても三代目春風亭柳好(故人)のそれが有名である。故・立川談志も「落語で一席選ぶとしたら柳好の「野ざらし」」と断言しているくらいで、謡い調子で軽やかに演じられる「野ざらし」は一曲の歌のようだった。これは音源が残っているので機会があればぜひ聴いてもらいたい。また、その謡い調子は故・三代目古今亭志ん朝にも引き継がれた。
この「野ざらし」を演じたのは子供時代の初太郎だった。声を当てたのは立川こはるである。あの「日本でいちばんチケットがとりにくい落語家」立川談春の現在では唯一の弟子で、落語立川流唯一の女性二ツ目でもある(前座には女性落語家がいる)。「野ざらし」といえば釣りに行く男が歌うサイサイ節が大事なのだが、それもきちんと(しかも子供の初太郎が歌うなりに)こなしていたのはお見事であった。日本で唯一の演芸専門誌「東京かわら版」によれば、こはるの出演する1月下旬の落語会は以下の通り。気になった人はぜひ行って応援してあげよう。
1/27(水)19:00〜「あかぎ寄席」神楽坂・赤城神社参集殿 入場料1500円
1/28(木)19:00〜「こはるの冬休み 立川こはる落語会」桜木町・横浜にぎわい座 入場料1500円
「子ほめ」「時そば」はアニメオリジナル
「子ほめ」は無知な男が聞きかじった褒め文句を使ってただ酒にありつこうとする噺。寄席では比較的多くかかるため、足を運んでいれば2回に1度くらいは聴けるのではないか。典型的な前座噺なのである。オチの「1つには見えねえ、どうみてもタダだ(もしくは半分)」というのは、昔は数えで年齢を言っていたため、赤ん坊は生まれた瞬間にゼロ歳ではなく1歳になったことからきている。現在ではピンとこない人もいるかもしれない。この「子ほめ」と次の「時そば」は、原作には出てこないアニメのオリジナル場面だ。
「時そば」は流しのそば屋をごまかして勘定を1文安くしてやろうとする男と、それを真似して失敗する間抜けの噺である。
たしかにそばの仕草が大事で同じ麺類でもうどんとそばでは食べ方が違うというのが落語的なリアリティであり、それが上手いと寄席では中手といって噺の半ばで拍手が起きたりする(ちなみにこの噺、関西では「時うどん」になる)。ただし、五代目柳家小さん(故人)は、中手を貰うことがいいと思わないように戒めていたという。
小里ん あと、「そばを食べるところがやたら目立つようじゃ、噺自体がダメだ。鸚鵡返しで失敗していく噺だから、そばを食う件だけが印象に残るような演り方をしちゃいけない。そばを食ってて中手が来るようだったら、それ以上、そばを巧く食うな」と師匠から言われています(柳家小里ん&石井徹也『五代目小さん芸語録』中央公論新社)。
勘定を「一つ、二つ」と数えて行く中で最初の男はそば屋に刻限を聴き「九つで」と言わせて「十、十一」と続ける。それで一文浮くのだ。オチではその部分が「へえ、四つで」と言われるために、戻って「五つ、六つ」と余計に払わないといけなくなる。この時刻の数え方はもちろん江戸時代のもので「九つ」は深夜0時ごろのこと。次の男が真似をしたときの刻限は「四つ」で午後10時ごろ(昼夜とも約2時間ごとに「九つ→八つ→七つ→六つ→五つ→四つ→」となる)。
さて、1/22に放送される第3回では時計の針が少し進み、戦時下の話になる。時局は風雲急を告げる。また、菊比古と初太郎の運命はいかに。
(おまけ)
私も新米落語プロデューサーというか、下足番として会を企画しています。よかったらこちらにも足をお運びください。
杉江松恋プロデュース落語会
※会場はすべて新宿五丁目CAF? LIVE WIRE
1/26(火)午後2時半〜5時半「立川さんちの喫茶★ゼンザ 立川流前座勉強会」出演者:立川志ら鈴、立川志ら門、立川らく葉、立川うおるたー、立川らくまん(予定)
1/26(火)午後6時半(開演午後7時)「立川志のぽん落語会 志のぽん言語遊戯集」出演者:立川志のぽん

2/19(金)午後6時半(開演午後7時)「立川談慶独演会 談慶の意見だ」出演者:立川談慶、ゲスト:畠山健二(作家)
2/22(日)午前0時半(開演午前1時)「立川談四楼独演会 オールナイトで談四楼」出演者:立川談四楼、立川只四楼
2/24(火)午後2時半「立川さんちの喫茶★ゼンザ 立川流前座勉強会」出演者:立川志ら鈴、立川志ら門、立川らく葉、立川うおるたー、立川らくまん(予定)
2/24(火)午後6時半(開演午後7時)「台所鬼〆独演会 お腹一杯独演会」出演者:台所鬼〆
(杉江松恋)