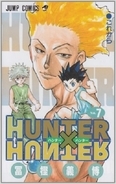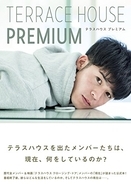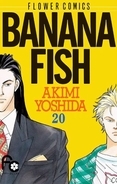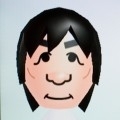では、なぜ困るのか。 これは本当に手前勝手な理由で申し訳ないのだが、理由は単純で、レビューしづらいタイプの作品なのだ。この数年、マンガ大賞の速報を書いているが、当然ながらそこには何らかの作品レビューを盛り込んでいる。しかし、本作は過去の受賞作のなかでも、もっとも作品を構成する柱が多い。
例えば昨年の速報では、「【速報】決定! マンガ大賞2015は、東村アキコ"涙"の自伝『かくかくしかじか』」というように「"涙"の自伝」とし、あらすじのさわりを書いた。一昨年の「ついにあのジンクスが破られた。速報!マンガ大賞2014は森薫『乙嫁語り』〜現場から詳細レポ」も難しかったが、「中央アジアを舞台に、描き出される暮らしにあるもの──。
どちらの作品でも触れたのは、映すひとつの柱でもあるように思う。だが今年の大賞『ゴールデンカムイ』のレビューはとても難しい。例えば、僕の2次選考時の推薦コメントはこうだ。
「舞台である開拓使時代の北海道について考証を重ね、アイヌという異文化の暮らしをていねいに描く手法は、2年前の大賞受賞作『乙嫁語り』(森薫)をも想起させるし、史実を大胆に膨らませながら、ときにコミカルなテイストを織り交ぜるセンスは過去のノミネート作である『ドリフターズ』(平野耕太)にも通じる引力とおかしみがある」
一部ディテールの面白さについて触れてはいるが、本質的な面白さについては、ほとんど伝えられていない。『乙嫁語り』と『ドリフターズ』を読んでいる人相手ならまだしも、両作を読んでいない人にはちんぷんかんぷんだろう。
だが、『ゴールデンカムイ』を「×××マンガ」と一義的にカテゴライズしようとするのも違和感が残る。パッと思いつくだけでも、「歴史」「民族」「狩猟」「グルメ」「サスペンス」「アクション」「バトル」に「ギャグ」「やおい」などなど、カテゴリーになりそうな要素はいくら挙げてもキリがない。
しかも何かひとつのラベルを貼りつけた瞬間、そのジャンル分け自体がウソになる。多彩な要素こそが、『ゴールデンカムイ』という作品の魅力につながっている。レビューを書くのに困りながらも、一読者としてはそう思うのだ。
では、作り手サイドにとって、『ゴールデンカムイ』の柱はなんだろうか。
(松浦達也)
<マンガ大賞2016最終結果>
大賞
『ゴールデンカムイ』(野田サトル)
91ポイント
2位
『ダンジョン飯』(九井諒子)
78ポイント
3位
『BLUE GIANT』(石塚真一)
68ポイント
4位
『僕だけがいない街』(三部けい)
55ポイント
5位
『百万畳ラビリンス』(たかみち)
49ポイント
6位
『波よ聞いてくれ』(沙村広明)
43ポイント
7位
『恋は雨上がりのように』(眉月じゅん)
42ポイント
8位
『町田くんの世界』(安藤ゆき)
38ポイント
9位
『東京タラレバ娘』(東村アキコ)
29ポイント
10位
『岡崎に捧ぐ』(山本さほ)
28ポイント
11位
『とんかつDJアゲ太郎』(イーピャオ/小山ゆうじろう)
25ポイント