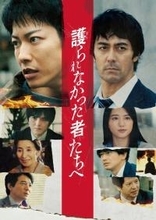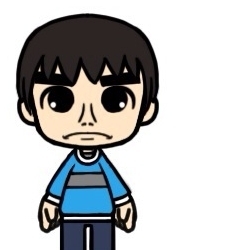2014年のダウンタウン──。
50歳を過ぎて仕事を失っていた松本人志と浜田雅功は、かつてのマネージャーに会いに吉本興業の事務所を訪れた。

笹山敬輔『昭和芸人 七人の最期』(文春文庫)のプロローグはこうして始まる。何事かと思うが、これは1994年に放送された『ダウンタウンのごっつええ感じ』のコント「2014」。当時30歳のダウンタウンが、20年後の落ちぶれた自分たちを演じたものだ。
著者は「お笑い芸人は、他の芸能に比べて、晩年を穏やかに生きることが難しい」と語る。歌手や俳優は、多少人気が落ちても歌唱力や演技力の評価は保たれている。対して、芸人は人気が落ちれば即座に「面白くなくなった」という評価が下る。笑い声が起きなくなる。逃げ道がない。
『昭和芸人 七人の最期』は、戦前から戦後にかけて劇場やテレビ黎明期に活躍した「昭和芸人」たちの晩年を描く。華やかな絶頂期からの最期までの落差は、やはり穏やかではない。
榎本健一「喜劇人は同情されたらおしまい」
芸人として絶頂期を過ごし、芸人のまま下降線をたどっていく彼ら。焦りやプライドに翻弄されながらも、笑いへの執着を捨てることができない。しかし、執着すれば笑いが取れるわけでもないのが辛い。
昭和の喜劇王・エノケンこと榎本健一は58歳で脱疽によって右足を失った。「喜劇人は同情されたらおしまい」が口癖のエノケンは、それでも義足をつけて舞台に立ち続け、全盛期のとんぼ(宙返り)を諦めなかった。長男を結核で亡くしたときも、最期を看取ったその足で稽古場へ向かい、用意された代役を断って舞台に上がる。しかし、エノケンの身に起こった不幸を知った観客たちは、全く笑わなかった。
「笑いだけを追求した姿を賞賛する人々も、晩年のエノケンは目を背けたくなるようだったと書く。彼が全てを犠牲にして笑いを求めれば求めるほど、笑いは遠のいていった」(P.40)
古川ロッパは結核であることを隠し続け、周囲からの悪口を逐一日記に書きつけて復讐を誓った。
石田一松は初の「タレント議員」まで上り詰めたが、落選後は寄席で自虐ネタを歌い続けた。
柳家金語楼は全盛期に作った五人の「妻」のため、70歳を過ぎてもキャバレーの仕事を入れた。
本書には戦前から戦後へ、舞台からテレビへと時代が大きく変わっていく様子も描かれている。環境が変われば、笑いの作り方もガラリと変わるだろう。
七人の昭和芸人たちは最後まで芸人であろうとした。そして、芸人であろうとすればするほど笑いから遠ざかった。なんと皮肉なことだろうと思う。
有吉弘行「ギャグは拍手をもらうようになったら終わり」
本書は昭和芸人たちの伝記にとどまらない。現在活躍している芸人やテレビ番組も絡めた「お笑いの歴史」としても興味深い一冊になっている。
例えば、エノケンが自身の舞台をスピーディーに演出した史実から「日本のお笑いで革新が起きるとき、それはいつも『スピード』の革新として語られることは興味深い」(P.22)と語り、約50年後の登場するツービートの漫才に触れ、M-1グランプリへと話をつなげていく。
昭和の物語のあちこちに平成の芸人が顔を出していて、モノマネ、歌ネタ、漫才、吉本興業などの「はじめて」を知ることができる。遠い昭和の出来事でも、現在のお笑いにつながっているとわかると俄然興味が湧いてくる。
『笑っていいとも!』『水曜日のダウンタウン』などの番組名や、タモリ、ビートたけし、松本人志、爆笑問題などの言葉も随所に盛り込まれている。なかでも印象的なのは、トニー谷の章で引用されている有吉弘行の言葉だ。
楽器代わりにソロバンを鳴らし、「〜ザンス」というしゃべりは「おそ松くん」のイヤミのモデルにもなったトニー谷。長男の誘拐事件をきっかけに人気を落とすが、日本テレビ『アベック歌合戦』の司会でカムバックを果たす。番組は約8年続き、最終回では再び全盛期のソロバン・マンボを披露した。この時、トニー谷は52歳だった。
「舞台上を踊りはしゃぐ彼に向かって、客席からは『トニーのおじさん、頑張って!』という声援がかかった。この記事を読んで、私は有吉弘行が言った言葉である『ギャグは拍手をもらうようになったら終わり』を思い出した」(P.206)
有吉弘行のこの言葉は、エノケンの口癖だった「喜劇人は同情されたらおしまい」を連想させる。同じことを言っているようだが、エノケンが自身の言葉に身を縛られてしまったのに対し、有吉弘行のそれはあくまで状況を俯瞰したものだ。昭和の喜劇王と平成の毒舌王をこうして比べられるのも、本書ならではだろう。
『昭和芸人 七人の最期』は巻末に伊東四朗のインタビューも収録しており、250Pほどの文庫でありながらボリューム感がある。お笑いファンの基礎教養としてもオススメできる一冊だ。
読み終わると、どうしてもこれからのことを考えてしまう。いかりや長介、松本竜介など「土曜8時」を争ったメンバーには既に故人がいる。
(井上マサキ)