脚本:渡辺千穂 演出:新田真三
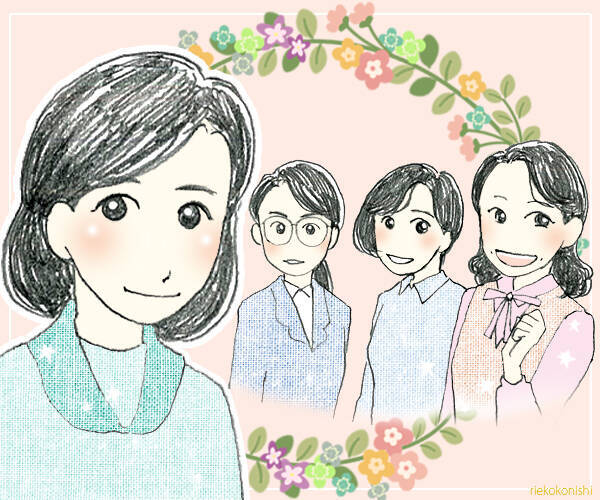
103話はこんな話
さくら(井頭愛海)を追ってすみれと紀夫(永山絢斗)がヨーソローへやって来て、家族で揉めたことによって、二郎(林遣都)はようやく五月(久保田紗友)の状況を知る。
どうして自分のことしか考えられないの
すみれが↑さくらを叱ったとき、たくさんの視聴者が「おまえもなー」と突っ込んだであろう。
「守るべきものはなんなのか、いつでもひとは自分に問いかけながら生きているのです」(語り・はな/菅野美穂)と語りは至ってご教訓めいた口調だが、さくら(井頭愛海)の場合は思春期のご乱心でしかないので、観ていてイラッとくるひとも多いのも仕方ない。
その点、五月は「大切なひとのためなら自分を犠牲にできる子」とすず(江波杏子)は評価している感じ。家を出てヨーソローにいたときは、若干ツッパっている子に見えたが、さくらの家に居候したら、「この家におったらありがとういう言葉しか出てけえへんなあ」とまでかなり殊勝である。
一方、すみれは、赤ちゃんがいるから自分ひとりのことじゃないと、赤ちゃんを大事にする視点で意見を述べる。それもごもっとも。
実際、すみれはさくらを大事にするあまり、紀夫(永山絢斗)がいない間、栄輔(松下優也)に頼り、それが結局、結婚まで考えてくれた栄輔との関係をすっきりさせないものとなっている。
さくらとすみれの問題に長く時間を取り過ぎているという意見もSNS で見かけるが、このドラマは、早い時期から主人公を母として描いている。それを展開早すぎ!と思って観ていたが、いま思えば、母と子の話を主に描くためだったのだろう。
戦争ですべてを失い、夫の生死もわからなくなったとき、すみれはさくらを守るために、自分ができることを最大限に利用して働きはじめた。さくらという娘への想いが、世の中の母と子供に広がってキアリスは人気店になった。ところが仕事が順調になって、一番大切なさくらと分かり合えなくなってしまった、さてどうする、というのはこのドラマの重要なところ。
すみれの想いや生きてきた道筋がさくらに伝わるといいのだが。そういうことを、明確に自覚し、言語化して他者を説得できるような人は現実にはなかなかいない。
誰もが悪気はないけれど世の中をうまく渡っていけていない。
こんなふうにもどかしい様を日々描き続け、完璧な正解を提示しないのが「べっぴんさん」だ。
ドラマや映画ではよく、悪い人がひとりもいないことが売りになる。その反対で、「全員悪人。」なんていうコピーの映画「アウトレイジ」があるけれど、「べっぴんさん」は悪人もいないが、よくできた人もいない(五月とその赤ちゃんのために、腹巻きを編み、さらに編み方も教えてくれる喜代(宮田圭子)さんは、困ったところがひとっつもないけれど)、それこそが世の中の真実に近いのではないか。つまり、このドラマはキャラを類型化せず、登場人物が、その都度、出会う人、出来事によって、影響されて変化していき、いい人にも困った人にもなって、どこに帰着するかわからないように描いている。まさに「ケセラセラ」だ。
お母さんだけやないお父さんも来た
五月が二郎の子供を身ごもっているらしいと知り、家に(叔母の家だが)に帰って布団を被ってこもっていたが、突如 がば!と起き上がると、ジャズのノリノリの曲がかかり、彼女のイケイケ気分を表すように曲が盛り上がって、ヨーソローへ。
探しにすみれたちが飛んできたときの紀夫の上記↑の台詞に笑った。説明台詞の少ない、そもそも台詞自体が少ない「べっぴんさん」がせいいっぱいの説明台詞に挑んで笑いをとってみました、という印象だった。
二郎とスカウトの大切な話に、すみれ一家が家族の問題を持ち込んでかき回す場面は、演出によってはど修羅のドタバタにも描けるはずだが、あくまで淡々としている。
完璧な人をつくらない、起こった出来事を茶化さないという点において、このドラマは新ジャンルを開拓しているのではないか。
願わくば、君枝と良子と健太郎(古川雄輝)にもう少し活躍の場をつくってほしい。
(木俣冬)































