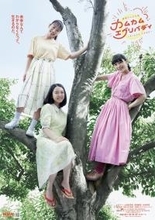なお、今回のドラマの脚本は、これまでたけし主演で『昭和四十六年、大久保清の犯罪』や『イエスの方舟――イエスと呼ばれた男と19人の女たち』など、多くの実録ドラマを手がけてきた池端俊策である。いずれの作品も問題作にして傑作だけに、「破獄」にもおおいに期待が高まる。
とはいえ、吉村昭の『破獄』がドラマ化されるのはこれが初めてではない。いまから32年前、1985年にもNHKでやはり単発ドラマとして放送されている。このときの主人公は脱獄囚で、いまは亡き緒形拳が演じた。

NHK版「破獄」は現在、NHKアーカイブスに所蔵され、埼玉県川口市の同施設のほか、全国のNHKの各放送局に置かれた番組公開ライブラリーで視聴可能だ。この記事では、今回あらためてドラマ化されるにあたり、このNHK版について原作との違いなどから振り返ってみたい。
人間性を奪う獄中生活に抗って
NHK版で何より印象に残るのは、監獄における囚人の過酷な扱いだ。冒頭からして、青森刑務所に収監された佐久間が、裸になって刑務官から体を隅から隅まで調べられる場面で始まる。このとき、津川雅彦演じる看守・鈴江圭三郎に、肛門に指を入れられた佐久間は、放屁して抵抗を示す。
二度目の脱獄後にいたっては、佐久間は手錠を後ろ手でかけられるばかりか、足錠までされたうえ全身を鎖で縛られる。
ドラマのつくり手は、佐久間の計4度にわたる脱獄を、監獄での非人間的な扱いに対する反抗として描いている。それは山内久による脚本(『山内久 人とシナリオ』所収)に、フランスの哲学者ミシェル・フーコーの『監獄の誕生』より《“一望監視施設”は一種の動物飼育場である》との一文が引用されていることからもあきらかだ(もっとも、この引用文は放送時にはカットされている)。
原作小説でも佐久間はやはりドラマと同様に、ひどい仕打ちを受ける。しかし、西洋史学者の木村尚三郎が《この本の本当の主役は脱獄犯の佐久間ではなく、刑務所長や看守ではないでしょうか》といみじくも指摘したとおり(丸谷才一・木村尚三郎・山崎正和「鼎談書評 天才ジャーナリストの時代」、「文藝春秋」1984年6月号)、原作では、ある意味で囚人たちよりも厳しい看守ら刑務官の境遇も克明に描かれている。何しろ舞台は戦中から終戦直後の食糧不足の時代だ。看守は自分らの食べるものがないにもかかわらず、囚人に対しては規定がある以上、十分に食べさせなければならなかった。
脱獄囚のセリフは「……」だらけ
結局、看守もまた、囚人と同様、あるいはそれ以上に囚われの身にあったともいえる。そこへ来て、佐久間が何度も脱獄を繰り返すのだからたまらない。原作において彼は、規則厳守を強く命じる看守に対し、《そんな非人情なあつかいをしていいんですか。痛い目にあいますよ。あんたの当直日に逃げられると困るんじゃないんですか》と脅しともとれる言葉さえ吐くこともあった(吉村昭『破獄』新潮文庫版)。
ドラマにも同様のセリフは出てくる。《おまえの当直の日にずらかられたら困るだろう》《俺に脱獄されたらお前の出世は止まりだぞ》というのがそれだ(前掲、『山内久 人とシナリオ』)。だが、原作の佐久間のセリフとくらべるとニュアンスが微妙に違う。原作のセリフは「ですます」調でどこか理知的な感じがするのに対し、ドラマではそういう印象が薄い。そもそもドラマのなかで佐久間は言葉らしい言葉をほとんど口にしない。脚本を見ても、セリフが「……」となっている箇所がやらと多い。
ようするに、佐久間とはどんな人物なのか、セリフではなく表情や動作で表現せざるをえないわけで、そうとうの演技力を要する難しい役ともいえる。もちろん名優として鳴らした緒形のこと、劇中、佐久間の過去について明示されないまでも、彼がたびたび見せる何とも言えない表情などから、背負いこんだものの重さは十分すぎるほど伝わってくる。
ドラマは、佐久間と前出の看守・鈴江の長年にわたる関係を軸に展開していく。じつはこれもドラマ独自のものだ。原作では、佐久間が刑務所を移るたびに、相手となる看守ら刑務官も変わる(そもそも鈴江は、原作では看守ではなく、佐久間が最後に入る府中刑務所の所長として登場する)。それがNHK版のドラマでは、佐久間の相手役として鈴江という看守を立て、時代を越えた1対1の対決と交流を描いた。

新旧「破獄」の見どころは?
……と、つい小難しい言葉を使って説明してしまったが、そんなことを抜きにしてもNHK版「破獄」はいまでも十分に楽しめるドラマである。何より、佐久間が驚異的な身体能力をもって脱獄するさまを、緒形拳がたっぷり再現しているのは見ものだ。ひるがえって今回のテレビ東京版「破獄」で佐久間を演じる山田孝之は、悪役に定評のある、この世代では稀有な俳優だけに期待できる。年齢的にも33歳と、いまがいちばん体の動く盛りだろう。
年齢ということでいえば、かつてのNHK版では、佐久間と鈴江の年齢はほぼ同世代と思われた(ちなみに放送当時の緒形拳と津川雅彦の実年齢はそれぞれ48歳、45歳)。それが今回のテレビ東京版では、看守役のたけしは実年齢が70歳で、山田とは親子ほどの差がある。NHK版と同じく囚人と看守の対決を描くにしても、その関係はおのずとNHK版とは違ってくるはずだ。
吉村昭が『破獄』で書かなかったこと
ドラマの原作となる小説『破獄』は、岩波書店の雑誌「思想」で連載されたのち1983年に単行本が刊行された。同作は、吉村昭が元警察関係の要職にあった人物から聞いた脱獄囚の話がもとになっている。その執筆動機を、吉村は後年、次のように明かした。
《私は、かれを主人公に小説に書いてみようか、と思うこともあったが、積極的に筆をとる気持ちにはなれなかった。脱獄につぐ脱獄というかれの動きは余りにも劇的で、書いてみても興味本位の物語にしかならぬ、と思えたからである。
そのうちに、(中略)ともかく調査に入ってみようと考え、S[実在の脱獄常習犯のこと――引用者注]が破獄をかさねた時代背景、当時の刑務所の実情、所員の生活の実態を知ることにつとめた。
その結果、Sとかれを監視する看守たちとの奇妙な関係を知ることができ、それを描けば、戦中戦後の異様な時代の姿を浮き彫りにすることができるという確信をいだき、筆をとったのである》(『吉村昭自選作品集 第十二巻』)
吉村は実際の事件や人物を題材に小説を書くにあたり、事実を徹底的に追究した。『破獄』の場合は、単行本を出したあとも、モデルとなったSの死について新事実があきらかになると、あらためて詳細を調べ、文庫化(1986年)に際してラストの数行を改変したほどだった(ちなみにNHK版「破獄」の放送は、原作の文庫化の前だったので、改変されたラストは反映されていない)。
しかし、それだけ事実を調べつくしながらも、吉村は一方で「事実を主にしても、私は小説を書いている」とも語っていた(NHK「あの人に会いたい File No.161 吉村昭」)。取材して得たもののなかには、小説にするうえで切り捨てざるをえないものもあるというのだ。
じつは佐久間のモデルとなったSは、小説やドラマで描かれた4回目の脱獄以後も、とくに懲りたり改心したりすることもなく脱獄を繰り返したという。前出の鼎談書評の丸谷才一の言葉を借りれば、男は《夜になると「では、ちょいと行ってこようか」と、外へ出てブラブラ遊んできて、また戻ってくる。(笑)そこへくると、吉村さんは、とてもこんなのは書けない、四回で切り上げようということになったらしいんです》(「文藝春秋」1984年6月号)。
原作を忠実にドラマ化していないからこその傑作?
事実そのままでは、やはり小説にはならないということだろう。おそらくは、ドラマと原作の関係についてもこれと似たことがいえるのではないか。
仮に名作を忠実に映像化できたとしても、それが原作と同じく名作となる保証はないはずだ。ましてや「破獄」のように長編で、作中の人間関係も複雑な小説を単発ドラマにする場合、省かざるをえない部分が出てくるのは当然だ。
たとえば、松本清張の小説『砂の器』は、橋本忍脚本・野村芳太郎監督によって映画化されるにあたり人物設定などが大幅に改変されているが、高い評価を受けた。そのせいか、その後の『砂の器』のドラマ化では、原作小説より、むしろ映画版が下敷きにされていたりする。
今回のドラマもまた、佐久間と看守の関係については、原作よりもむしろかつてのNHK版を踏襲し、1対1の物語として描かれるようだ(ただし、たけし演じる看守は、NHK版に出てきた鈴江ではなく、原作に登場する浦田進というべつの人物に設定されている)。
しかし、周辺の人物の設定を見るかぎり、監獄の外の世界もかなり細かく描かれるらしい。そこが今回のドラマのひとつの特色といえるかもしれない。
思えば、脚本の池端俊策はここ10年ほど、ビートたけし主演の「あの戦争は何だったのか――日米開戦と東条英機」(2008年、TBS系)あたりを手始めに、足尾銅山鉱毒事件を題材とした「足尾から来た女」(2014年)、戦時体制に抵抗した財界人を描いた「鬼と呼ばれた男~松永安左ェ門」(2015年)、第二次大戦中の日本人夫婦による諜報活動をとりあげた「百合子さんの絵本」(2016年)、あるいは「夏目漱石の妻」(同年、以上いずれもNHK)と、日本の近現代史に鋭く迫ったドラマをあいついで手がけている。
今回のドラマでも、たとえばオリジナルの人物として、たけし演じる浦田の娘・美代子(吉田洋)が登場、母と兄妹を関東大震災で亡くした設定となっている。ひょっとするとこれは、吉村昭に『関東大震災』という作品があるのを意識してのものだろうか。このほかにも、登場する各人物の設定には、農家の娘の身売り、蟹工船での重労働など史実が反映されている。これらがいかに物語にリンクしていくのか、おおいに気になるところだ。
何より、かつて緒形拳と津川雅彦が演じた名作が、ビートたけしと山田孝之という組み合わせにより、どんなふうに新たな作品として提示されるのか、非常に楽しみである。
(近藤正高)