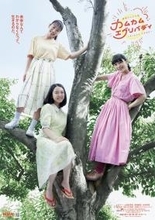画面中が、やたらめったら動く。
テーマ性とか、色々小難しいことを考えるのを放棄しちゃうほど、愉快だ。

『思い出のマーニー』などの米林宏昌監督が、ジブリ制作部門解散後にスタジオポノックで制作。
2017年の空気で、宮崎駿と鈴木敏夫から離れて、『ラピュタ』や『千と千尋』を別の人が作ったらこうなります、というファンタジー映画だ。
明解なエンタテイメント
序盤から爆発したり飛んだりと、ド派手にアクション。
『ラピュタ』の追っかけっこみたいだ。
メアリが乗るほうきは全然まっすぐ飛んでくれない。スポーンと雲の上まで出る暴れウマ。
『魔女の宅急便』ラストのデッキブラシの、超加速版だ。
魔法大学の珍妙な構造。常にあっちこっちぐねぐね動いている。
色とりどりの魔法が渦巻く極楽感があるかと思いきや、即死しそうな機械の並ぶディストピア感もある。
『千と千尋』の油屋や、『コクリコ坂』のカルチェラタンの混沌を見ているかのよう。
後半で、あるものが群れなすシーン。
ファンタジーの世界に行って帰ってきた時に、メアリが一回り成長する様子は、『アリエッティ』『マーニー』になかった、シンプルな安心感がある。
驚いた時に「えーっ!?」という表現をするのは、なんだかジブリっぽくなく、ノリが軽い。
「ジブリっぽい楽しいシーン」を「ジブリっぽい重さ抜き」で、ジブリアニメーターたちの職人技をフル活用して見せてくれる娯楽作品になっている。
米林宏昌と女の子
主人公メアリは、かなりがさつで、ウソをつき、言うことを聞かず、失敗ばかり。へらへら調子に乗ることも。
でも根は真面目。声が朗らかで明るい。泣くときはわんわん泣く。目がパッチリと大きい。
思春期前の子供感が、とてもキュート。
序盤着ていたのは、パーカー、ミニスカート。ニーソックス。
普段はもさもさの髪。途中からふたつ縛り。そしてポニーテール。
その他にも、記号的なかわいらしさ・愛され要素がバリバリと盛り込まれている。
これは近年の宮崎駿作品では、ほとんどなかった。
鈴木敏夫は、『マーニー』の時に宮崎駿が「麻呂(米林)は、美少女ばかり描いている。しかも、金髪の……」と苦言を呈していたのを語っている(「思い出のマーニー」公式)。
美少女描写は、米林宏昌の武器だ。
鈴木敏夫いわく、「宮さんを脅かす絵」と言うほどだ。
今回はそこに加えて、元気な少年ピーターが登場。『アリエッティ』でやたら艶めかしかった少年・翔を演じていた神木隆之介が声を当てており、こちらもかわいい仕草だらけ。
2人の関係は、赤毛のアンとギルバートのようで、みずみずしいガールミーツボーイ。
米林作品は、女の子がはじめて誰かに出会う描写に、ワクワク感があるのも特徴だ。
ジブリでありジブリでない米林宏昌
スタッフの8割はジブリ出身者。映像や音響の技術部分はほぼジブリと言って差し支えない。
米林監督は、恩師とも言える宮崎駿の元に『メアリ』制作を伝えに言った時「だったら今すぐ帰れ!長編をやるなら、覚悟を持ってやれ!」と言われた。
製作中には「うれしい!」とも言ったそうだ。(CINEMAランキング通信)
かと思えば、完成した新作に対して「俺は観ない」といってそっぽを向いたり、それでいて「よく頑張った」とねぎらったり(シネマトゥデイ)。
宮崎駿がツンデレすぎて、本音が読めない。
なお、高畑勲は昨今哲学的で複雑な作品を放り込んでいる作品が多くなっている中で、分かりやすくて良かった」と、鈴木敏夫は「若い」「ジブリの呪縛から解き放たれると、こういう作品を作るのか」と述べている(animate Times)。
良い悪いというよりは、ジブリなのにジブリではない異物さを感じたのだろう。
『メアリ』におけるジブリと米林宏昌の距離感は、後継者問題の渦中にいた庵野秀明の発言がわかりやすい。
「僕が西村君に言ったのは宮崎さんの画の系譜を残してほしいということ。
米林宏昌は、伝統と革新に挟まれている最中の作家だ。
最後のシーンは、ジブリという魔法に対しての、米林監督の表明なのだろう。
今回の映画は、メアリが手にした魔法同様に、「ジブリ」という派手で楽しい付け刃。
米林宏昌は「スタジオジブリ、宮崎駿、このふたつの魔法の言葉」「これを乗り超えていかないといけない」と初日舞台挨拶で語っている。
(たまごまご)