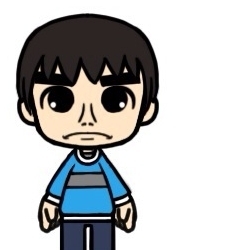「5日間、この国の価値観からぼくを引き離してくれ。同調圧力と自意識過剰が及ばない所までぼくを連れてってくれ」(P.40)
『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』は、若林がキューバで過ごした5日間を記録した書き下ろしエッセイだ。

20代のお前、残念だったな!
そもそもなぜキューバだったのか。「アメリカとの国交が回復して、今のようなキューバを見られるのもあと数年だから」というのは建前の理由。きっかけは若林が1年前から雇っている家庭教師だった。時事問題に疎い若林は、東大の大学院生にニュースを解説してもらっていた。
家庭教師の講義のなかで「格差社会」「超富裕層」について聞いた若林は、「新自由主義」という言葉を知る。勝ち組。負け組。
「僕は家に帰って自分の著書『完全版 社会人大学人見知り学部 卒業見込』を取り出し、『おい、お前の悩みは全部人が作ったシステムの中でのことだったぞ。残念だったな!』と言葉をかけた後、ひとつの儀式としてゴミ箱に捨てた」(P.33)
では、他のシステムで生きている人間はいったいどんな顔をして暮らしているのか? この目で見ないと気が済まない。そこで選ばれたのが社会主義国のキューバだった。トロントを経由して15時間半のフライト。深夜のホセ・マルティ空港に降り立った若林。空港の女性職員のミニスカートで寝ぼけ眼を覚まし、トラブルが起きても腕力で勝てそうな高齢のドライバーを探す。クラシックカーのタクシーに運ばれること30分。ホテルに着いて電気を付けたまま寝てしまう。
キューバでは誰も若林を見ない
東京での自意識過剰さとは異なり、キューバの若林は本当にキューバを楽しんでいる。
「ぼくは笑っていた。『笑み』というレベルではなくて、口を押さえてほとんど爆笑していた。これはどんな笑いなんだろう。誰かの顔色をうかがった感情じゃない。お金につながる気持ちじゃない。自分の脳細胞がこの景色を自由に、正直に、感じている」(P.60)
キューバ人なのにガイドが人見知りだったこと。
以前の若林は自分自身を延々と眺め、自意識過剰をくすぶらせていた。東京のしがらみを忘れるために箱根に温泉旅行に行ったのに、ネガティブな感情に突然襲われたこともあった。
「最初は『露天から見える竹林が綺麗だな』と大変気持ちが良かった。しかし、しばらくすると『そういえば、あれはいつまでにやんなきゃいけないんだっけ?』とか『こんなことしていいのか?』と展開し『この先どうなっていくんだろう?』とネガティブの底に向かって思考はまっすぐに降下していた。おいおい、嘘だろ」(『完全版 社会人大学人見知り学部 卒業見込』より「ネガティブモンスター」)
キューバを旅する若林は、ただひたすら目の前の物を楽しみ、味わい、喜び、観察する。自分自身をほとんど掘り下げず、ネガティブの底に落ちることはない。東京から物理的に遠く離れたことも、とても効果的だったようだ。街中の視線について記しているのをたびたび目にする。
「すれ違う人は誰もぼくを見ないし、失笑もしない。帽子もマスクもしないで歩くと、コメカミを通り過ぎていく風がとても気持ちいい」(P.65)
「ぼくがモヒートを飲んでいる姿など、日本人に見られたら確実に笑われるだろう。だがここはキューバ。見渡す限り日本人はいない」(P.95)
キューバでは誰も若林を見ない。だから安心して、自分自身を見ずに済むのかもしれない。
実は、若林がキューバを選んだのは前述の理由だけでは無い。真実は最終章で明かされ、陽気なキューバ人が集まるマレコン通りの描写と、若林の回想が交互に現れる。この理由に向き合うために、若林は15時間半かけてキューバまで来た。ほぼ日本の真裏まで来ないと消化できなかった。ここは読んでいて本当に泣いてしまった。
帯文にもあるように『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』は単なる「キューバはよかった」で終わらない。かつての自意識過剰をぬぐい、喜びも悲しみも解放する若林と5日間を過ごしてほしい。
(井上マサキ)