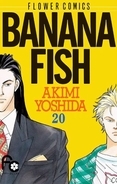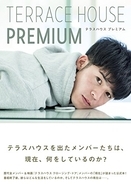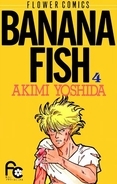ペナントレースを14.5ゲーム差でぶっちぎりの独走優勝を果たした広島が、日本一を決める戦いに出られないというのだから、ファンの落胆ぶりは想像に難くない。連覇だったからまだ良かった(?)ものの、25年ぶりの優勝だった昨年、日本シリーズに出られなかったとしたら、どうなっていたことか……。
プロ野球ファンのCSに関する「モヤモヤ」を代弁したのが、お笑いタレントの陣内智則だ。陣内は、自分は阪神ファンだと前置きした上で、「広島カープファンの気持ちを考えればこの変なモヤモヤは何やろ」とツイート。さらに「ルールとはいえ、この1年間の選手やファンの頑張りが短期間で失われる今のCSルールをもっとファンが納得いくシステムに変えてほしいな」と注文をつけた(10月24日)。
元巨人監督の堀内恒夫氏は、自らのブログに「より良いクライマックスシリーズのために」と題した記事をアップ。「シリーズの存在自体を問われる中で続けていくとするならば、より良いものとなるように今シーズンが考える機会となってほしい。色々試してもいいんじゃないかな」と記している(10月25日)。報道によると、「2位に10ゲーム以上差をつけて優勝した場合、最終S(ステージ)でさらに1勝のアドバンテージを加える」という案も議論されていたらしい(朝日新聞 10月25日)。
CSは全チームにとって願ったり叶ったり
ロジカルかつ異色の分析で人気を博す元千葉ロッテマリーンズで野球解説者の里崎智也氏は、著書『捕手異論』(KANZEN)の中で「CSは必要」という持論を展開している。里崎氏が何より重要な要素として挙げているのが、CS導入の理由でもある「『消化試合』の減少がもたらす経済効果の大きさ」だ。

そもそもCSは、リーグ優勝・日本シリーズ進出決定後の消化試合を出来る限り減らすことを目的に2007年から導入されたもの(パ・リーグは2004年からトーナメント方式のプレーオフ制度が実施されていた)。今年、広島がセ・リーグ優勝を決めたのは9月18日であり、CSがなければ、この日以降の試合がすべて消化試合になっていた可能性がある。
プロ野球はあくまで“興行”であるという観点に立つ里崎氏は、ファンの楽しみ、メディア側の関心の持続に加え、「経費だけがかさんでいた『消化試合ありき』の頃とは違って、仮にBクラスであっても観客動員にある程度の見通しが立つのだから、各球団にとってもまさに願ったり叶ったりな状況」であると語っている。CS進出に望みがなくなったチームでも、相手がCS進出を賭けて戦っているチームなら観客動員が見込めるというわけだ。
また、「消化試合」には別の弊害があると里崎氏は主張する。それは、チームの勝利よりも個人記録を優先することで起こる“泥仕合”だ。たとえば、1988年はロッテオリオンズの高沢秀昭と阪急ブレーブスの松永浩美が首位打者を争っていたが、ロッテは高沢をスタメンから外し、打率2位の松永をダブルヘッダー2試合において10打席連続敬遠を行った(11打席連続四球)。この年は1厘差で高沢が首位打者を獲得している。このような“泥仕合”をなくすためにもCSは有意義だというのだ。
CSはほとんど欠点の見当たらないシステム
現在レギュラーシーズン優勝チームは全試合でホーム開催ができ、1勝のアドバンテージが与えられている。この現状についても里崎氏は「圧倒的に有利な制度」と説く。実際、レギュラーシーズンで優勝をしたのに日本シリーズ進出を逃したのは、2007年と2014年の巨人、2010年のソフトバンク、そして今年の広島と4例に過ぎない。なお、07年にはまだ1勝のアドバンテージが付与されていなかった。
里崎氏は「(CSは)8割以上の確率で『優勝チームが勝ちぬけできる』ようにできている、ほとんど欠点の見当たらないシステム」と説く。
「そんな奇跡を起こすチームが何年かに一度出現するというのもCSという制度のもつ醍醐味であり、プロ野球の新たな“付加価値”ではないだろうか」と里崎氏。今年のDeNAは、下克上という“奇跡”に向かってひた走っているチームなのだ。
なお、『捕手異論』には、「野球界に氾濫する『曖昧さ』への違和感」「『リードの善し悪しは結果論』の真意」「『盗塁阻止』はバッテリーの連帯責任」「練習量で『熱心さ』をはかる悪しき風潮」など、これまで球界の常識とされてきたセオリーに対する刺激的な“異論”が並んでいる。プロ野球ファンなら一読の価値ありだ。
(大山くまお)