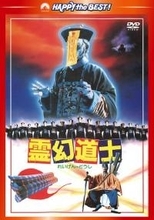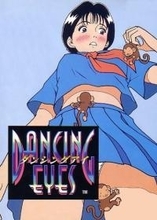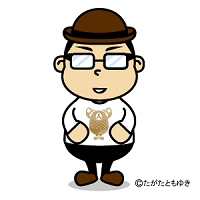19カ国語を操り、生物学、民俗学、天文学、考古学などなど、様々な分野にも確かな足跡を残した“知の巨人”である。
また、異常な癇癪持ちだったり、多汗症ゆえに全裸でいることを愛するなど、奇行やエキセントリックなエピソードにも事欠かない、語れる要素の多い変人でもあった。
この魅力的な偉人は91年の没後50周年前後にもちょっとしたブームとなっているが、筆者としてはその流れに少年ジャンプが乗ったことが忘れられない。
『てんぎゃん』の前の作品も超異色作『恐竜大紀行』
90年50号から始まった『てんぎゃん-南方熊楠伝-』。熊楠の生涯を描いた実録漫画だ。「てんぎゃん」とは天狗のこと。その天狗が登場するなど、ファンタジックな色付けもされている。
作者の岸 大武郎先生は、前作『恐竜大紀行』に続き、またも異色作でのチャレンジとなる。
88年に連載された『恐竜大紀行』は、多感な時期のジャンプ読者に絶大なインパクトを残した作品。筆者と同じアラフォー世代なら、ご記憶の方は多いのではないか?
タイトル通りに恐竜の話なのだが、これがリアルに恐竜しか登場しないのだ。
人間がタイムマシンで恐竜時代にとか、『ジュラシックパーク』のように現代に恐竜を復活させたとかではない。恐竜がいた時代の日常をリアルに切り取った物語であり、漫画ならではのディフォルメ要素もなく、絵柄もあくまでリアル。
オムニバス形式のため、決まった主人公はおらず、共通のナビゲーターとなるキャラもいない。弱肉強食の世界がひたすらシビアに描かれていた作品である。
異例中の異例……あの鳥山明が絶賛!
アンケート至上主義のジャンプにはそぐわず、全1巻での打ち切りとなったが、その評価は非常に高い。
05年に完全版として復刊された際には、あの鳥山明先生が絶賛のコメントを寄せている。
普段、自身の漫画さえ再確認することのない鳥山先生が何気なくジャンプを見ていた際に、目を引いたのがこの作品だという。
丁寧な絵、ドラマチックで確かなストーリー、恐竜の生態についての知識と、いたく感心した鳥山先生は、バックナンバーを読み返し、次号を心待ちにするほどだったと語る。
「漫画に夢中だった小学生の時以来、毎週欠かさず漫画をめくったのは、この頃だけかも知れません」
そもそも、他の作品にコメントを寄せること自体が珍しい鳥山先生がこれほどまでに絶賛するのは異例中の異例。漫画家冥利に尽きる大勲章である。
編集部も力を入れた偉人を題材に! 学習漫画『てんぎゃん』
『てんぎゃん』連載開始号の巻末(なつかしの「ハロージャンプガイ」!)では、担当編集者の椛島良介氏が「読みごたえのある作品にしようと先生も担当も張り切っています」と、この作品にかける想いを熱く語っている。
注目するのは「担当も」の点。なんでも、この椛島氏が熱烈な熊楠ファンで、資料集めから始めた肝煎り企画となるという。
だからか、内容も史実に忠実な作品となったのだが、実は前述の『恐竜大紀行』も同じく椛島氏。目の付けどころが中々ユニークというか、なんとも通好みな編集者だ。
ちなみに、『ジョジョの奇妙な冒険』の初代編集者でもある。主人公が外国人、しかもホラー要素強めというジャンプ向きではない題材をプッシュし、人気作に押し上げた功績は大きい。(この時点でのジョジョは第3部を連載中)
椛島氏の持論は「ジャンプは王道だけでなく、異質な作品を育てる土壌もある」。
どう転がるのか楽しみだったのだが……。
12週で無念の「第1部完」
『てんぎゃん』は、南方熊楠の幼少期から青年期のアメリカ時代にかけてを描いた実録漫画だ。そう、青年期までを……。
意欲的で面白いテーマではあったが、毎号の盛り上がりには欠ける展開。人気アンケートを集めるのは至難の技である。
結局、こちらもジャンプでの生存競争には勝てず、後半は巻末が定位置のまま12週で終了。新連載時の表紙にあった後年の姿に到達する前の打ち切りとなった。
最終回掲載号では「第2部ロンドン編を構想中」と作者コメントを寄せているが、現時点でも幻のままなのが切ない。
この少し後に、水木しげる先生も熊楠をモチーフにした『猫楠(ねこぐす)』を発表。人語を解する飼い猫「猫楠」からの目線で熊楠の半生を描いているが、この作品を書くきっかけは熊楠の人となりが面白かったからだという。
描きがいのある人物だったのは間違いないが、ジャンプではそのさわりのみで終わってしまった印象。
「異質な作品を育てる」前に終わってしまったため、せっかくの岸先生の才能を生かせなかったのは残念でならない。
筆者的にも、熊楠が胃の内容物を自在に操れる特殊能力持ち(絶対にいらない能力)で、食べ物を戻して飲み込んでを繰り返して楽しみ、ケンカの際にはゲロをぶち巻けることから、「反芻(はんすう)」というアダ名だったことぐらいしか記憶に残っていないのである。