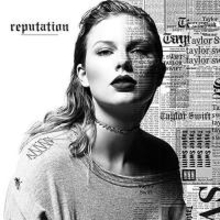座間市で起きた9人遺体事件において、被害者と加害者がTwitterを使って接点を持ったことから、ネットに対する規制を求める声が出ています。タレントの坂上忍氏も、11月6日放送の『バイキング』(フジテレビ系)でSNSになんらかの規制を加えるべきだという趣旨の意見を述べたとのことです。
「出会い系サイト規制法」でも児童被害は減っていない
ですが、ネットへ規制は意味があるのでしょうか? それで本当に卑劣な犯罪を防ぐことができるのでしょうか? 私は一時的な効果はあっても、それだけでは根本的な解決にはつながらないと考えています。
その代表例が、「出会い系サイト規制法」の事例でしょう。インターネットと児童が絡んだ諸犯罪では、2005年に1051人の児童が出会い系サイト経由で被害に遭いましたが、10年後の2015年にはコミュニティサイト経由1652人、出会い系サイト経由93人、合計1745人となりました。
つまり、規制法の制定と警察の努力によって出会い系サイトというチャネルを潰すことには成功したのかもしれないですが、犯罪を抑えられることができていないばかりか、被害者数は増加傾向にあります。
結局のところ、政治や行政は、被害者や加害者を覆う根本的な問題に対してほとんど何もしてきませんでした。臭い物に蓋をしただけの対策で終わりにして、その中身に対しては無策だったのです。このように、ネットに何らかの規制をかけても、根本的な対策を怠れば別の形で問題が発生するという意識はもっと認知されるべきでしょう。
生涯に渡る加害者防止教育が必要です
それでは、今回の座間市のようなケースにおいては、大まかにどのような対策が必要なのでしょうか? まず、やるべき対策を大きく3つに分けて考えてみましょう。
(1)被害者の「死にたい」という想いをいかに小さくするか
(2)加害者の「殺したい」という欲求をいかに小さくするか
(3)プラットフォーマーにいかに秩序維持に責任を持たせるか
この中で、事件を起こさないという意味で最も対策が必要なのは(2)でしょう。ところが残念ながら、加害者になることを防止するための施策というのは行われていない等しいのが現状です。確かに「悪いことはやめましょう」のように表面的に教わることはありますが、それでは加害を抑制することは不可能に近いと思います。
しっかりと人間の闇や認知の歪みにまで踏み込み、それを哲学し、自らを律する術を、社会全体に頒布しなければなりません。一朝一夕にはいかないことですが、幼児教育から始まり死ぬまでの間、全ての人が「善意の芽」を大きくし、「悪意の芽」を小さくできるような生涯学習の文化が必要です。私たち一人ひとりにできることとしては、近しい人とこのような重たいテーマについても話せるような関係を築くことが重要だと思います。
また、加害者更生プログラムへのアクセスをしやすくするべきでしょう。加害者自身が自分の加害性に気が付いたら、気軽にプログラムに参加できるような仕組みが必要ですし、そのようなものがあるということを全国民に知らせる必要があると思います。
自殺は私たち日本に住む全員の問題だ
加害防止と並んで重要なのが、被害者を作らないことです。日本が自殺大国で、若者の死因の一位が自殺であることはわざわざ触れることの無い常識となってしまっていますが、まずは、なぜこの国がそんなに人々を死に追いやる構造になっているのか、知る必要があるでしょう。その最大の要因は、とにかく自己肯定感を破壊するような教育と人間関係にあると私は思っています。
そして、死にたいと思ってしまっている人たちのことも、もっと詳しく知らなければなりません。ネット規制を唱える人たちは、その点があまりに鈍感だと言わざるを得ません。彼ら彼女らを本当に救うことができるのは、ネットの規制でしょうか? 彼ら彼女らがそのようなものを欲しているのでしょうか? もちろんそんなものではないはずです。
「死にたい」という心の叫びは、「本当ならばもっと希望を持って行きたい」ということの裏返しだと思っています。希望に溢れる社会にするためにはどうするか。自殺志願者の問題は「自殺志願者の側」にあるのではなく、「私や貴方のいるこの社会の側」の問題です。変わらなければならないのは、彼ら彼女らではなく、私たちです。
対策がゆるゆる後手後手な日本のネット
最後に、プラットフォーマーの問題についても触れたいと思います。
また、フリマアプリのメルカリでも、現金が出品されたことが問題となりました。しばらくはいたちごっこが続きましたが、今では対策も一巡して落ち着いているようです。さらに、ヤフーオークションでは、転売で不当な利益を得る行為が多発していることから、11月8日より転売目的で入手したチケットの出品を禁止しました。このように、プラットフォーマーは秩序を維持するために、対策をしっかりと行わなければなければなりません。
ところが、Twitterはやらなければならない対策を実施しているでしょうか? 事件が起こってから規約を見直し、「自殺や自傷行為」を凍結の対象としましたが、遅過ぎると言わざるを得ません。たとえば、リベンジポルノが禁止されたのは、2017年の10月になってからですし、様々なプラットフォーマーの中でも、対応がかなり遅い傾向にあります。
規約を設けたとしても、実際にしっかりと運用されていないことも多々あります。ヘイトスピーチや盗撮等に関しても放置していることが多く、ヘイトや犯罪の温床になっていることを指摘されても、なかなか改善が進みません。
冒頭で「規制では根本的な解決にはならない」と述べましたが、このように動きの鈍い業者を促すためには、何らかの規制は必要でしょう。たとえば、ドイツではヘイトスピーチを24時間以内に削除しないSNSには最大60億円の罰金を課す法律が制定されましたが、日本でもそのようにプラットフォーマーとしての秩序維持を怠った企業に対して罰金を課すことも検討する必要があると思います。
(勝部元気)