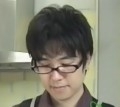まずは、『Toy-Con01 VARIETY KIT』を一通り作って遊んでみたので、レビューしたい。
「つくる」は世界一イケてる組み立て説明書
Nintendo Laboを購入すると、まず驚かされるのは箱の大きさだ。ゲームソフトというよりは、ゲーム本体が入っているのではないかと思うほど。
中には、カラフルに色分けされた何枚ものダンボールが入っている。Nintendo Laboではこれらのダンボールを自分で組み立てて、遊ぶことになる。どんなものなのか詳しく見てみたい人は、公式ページで公開されているので、そちらを参照して欲しい。

組み立てには、糊もハサミもカッターも必要ない。ダンボールには切れ目が入っているため、シートから簡単に外せるようになっている。ただ、細かいパーツをくり抜くことも多いため、つまようじを用意しておくといいだろう。
ソフトでは「つくる」「あそぶ」「わかる」の3つのメニューがある。
まずはチュートリアルとして、Joy-Conケースを作成することになる。

「つくる」は簡単に言うと、プラモデルにおける組み立て説明書だ。ただし、普通の説明書ではない。タッチパネルを存分に使った、世界一イケてる組み立て説明書だ。
シートのうち、どれを切り離せばいいのかはカラーでわかりやすく表示される。

この工程ではこれ以上のダンボールが必要なくなった場合は、箱にしまっておこうという指示もでる。

組み立て工程では、画面を回転させたり

拡大縮小も可能だ。ちなみに、画面左下のカメラアイコンをタッチすると視点がリセットされる。

どこを折るのか、事前に折り目をどうつけるのかも、丁寧に説明してくれる。

重要なところは、きちんとできたかどうかの確認がある。

時にははげまされながら、画面の指示に従っていくと、無理なく完成させられるだろう。
丁寧に作られているなと思うのは、たとえば同じパーツを複数作成するときに、「同じ作業を3回やってね」みたいな繰り返しの指示ではなく、毎回丁寧に組み立て指示を行う点だ。
同じ作業をするとしても、画面に出てくる台詞が毎回異なるようになっている。子供が作業をするときに、つい忘れてしまうということがないようにする工夫だろう。
VARAETY KITでは「リモコンカー」「つり」「おうち」「バイク」「ピアノ」の5つを作ることができる。
「ここがこうなるのか!」という体験
Nintendo Laboはダンボール工作の部分だけでも、相当に楽しい。
プラモデルでも、飾るよりも作っている最中が好きだという人がいるように、何かを作るというのはそれだけで楽しい行為だ。
さらに、工作をしていると、「ここがこうなるのか!」という驚きが出てくる。
たとえば、「つり」では、伸縮式のつりざおを作成する。
このとき、さお部分で、つめを出したまま合体させるのだが、これが「かえし」となって外れないようになっていたり

外れそうな部品には、きちんとストッパー(これもダンボールで作る)を差し込んだり)

不思議なパーツだなと思っていたら

実はバネだったり

ダンボールだけでここまでできるのか! という感動がある。
できあがったもので「あそぶ」
工作が終わったら、「あそぶ」番だ。
■リモコンカー
「リモコンカー」は、左右に装着させたJoy-Conを振動させ、前進したり、回転したりできる。

本体をコントローラーに見せかけ(ダンボールでアンテナも装着する)、左右のJoy-Conの振動の度合いをコントロールすることで、リモコンカーを自在に動かそう。
■つり
「つり」はSwitch本体を海に見立てて、魚を釣るゲームだ。

面白いのは、本体を固定する台とつりざおとが糸で結ばれていること。実際にさおを引いたりしたときの手応えがリアルだ。
リールを回して海底へ針を送り込み、魚がかかったらさおを上へ引き上げるとヒット。そこからはリールを回して糸を回収しつつ、魚の抵抗で糸が切れそうになったら緩めて切れないようにし、駆け引きを繰り返しながら釣り上げる。
あまり釣りをやったことがないので、どこまでリアルかは判断が難しいのだが、十分に魚との戦いを楽しめた。
ただ、ちょっと戸惑ったのが、右手でリールを回転させるとき、糸を繰り出すのが反時計回り、糸を巻き取るのが時計回りだったことだ。おそらくは実際のつりざおもこういう方向だとは思うのだが、さおを引っ張りながら手前にリールを回すという感覚だと巻き取る方向が反時計回りだと思い込んでいたので、しばらくの間は操作で混乱してしまった。
釣った魚は水槽で見ることができる。
なお、後述のピアノと組み合わせることで、オリジナルの魚も作成可能だ。
■おうち
おうちは、Switch本体を家にセットし、中にいる不思議な生き物と遊ぶ。

家の側面と、底には穴が開いていて、そこにスイッチを差し込んだりすると、画面の中にも変化が現れる。
おうちを揺らしたり、傾けても画面の中に変化が起きる。そうやって、生き物と戯れていくのだ。

おうちでは、普通に「つくる」だけで作成が完了するわけではない。「つくる」の中に、オプションとしてケーブルブロックを作成するところが独立してあるのに注意しよう。
■バイク
バイクは文字通りバイクのハンドル部分を作成し、Switch画面に現れるコースを実際に運転できる。

単にJoy-Conのボタンを押すのではなく、きちんとエンジンのボタンなどもダンボールで作成。
ゲーム的には、ウイリーをしたり、マリオカートみたいなドリフトをしたりと、リアルではないところも組み込まれている。マリオカートのハンドルコントローラでも運転している実感は多少あったが、こちらはそれ以上だ。
バイクもオプションとして、ミニバイクやIRスキャナを作成できる。

ミニバイクやIRスキャナを使えば、簡単にオリジナルコースやスタジアムが作成できる。
■ピアノ
ピアノは、1オクターブの鍵盤だけに見えるが、かなり多機能だ。

最初はトイピアノとして演奏できるのだが、これだけでも相当楽しめる。つまみを挿入して音色を変えたり音を揺らしたりすることができるからだ。
だが、いろいろと遊べるのは「録音スタジオ」を使ってからだろう。

録音スタジオでは、横のレバーでオクターブを上げ下げしたり、演奏を録音したり、自分で音色を作ったり、さまざまな機能を活用できる。
さらには、リズムカードという、いわゆるパンチ穴を開けるようなカードで、リズムを後ろに流したり、作成した曲を指揮棒でスピードを変えて演奏させたりと、単に演奏する以上のことができる。
さらに、波形カードで音色を変えることもできる。
「わかる」で仕組みを学ぶ
さんざん遊んだら、「わかる」を確認したい。
それぞれのゲームの説明書と思いきや、どういう仕組みでJoy-Conを利用し、この動作を実現しているかを、チャット形式の軽妙なトークで教えてくれるコンテンツだ。

IRカメラで反射シールをどういう風に認識しているかなども、きちんと見せてくれる。
これが、実に面白い。ここのギミックはこういう風に実現しているなどが理解できると、より楽しくなってくる。かなりのボリュームがあるが、ちょくちょく読んでいくといいだろう。
Toy-Conガレージで学んだ知識を活かす
「わかる」で仕組みを学んだら、是非とも挑戦したいのが「Toy-Conガレージ」だ。

「わかる」メニューの下にあるマンホールのアイコンをタッチすると、自分でJoy-Conの挙動などを作成できる。

左が入力、右が出力、これらを線でつなぐと、入力の動作をすれば出力として反映されるという仕組みだ。画面にタッチするとJoy-Conが振動したり、特定の音を鳴らすことができる。
これで、自分でもさまざまな遊びを「発明」できるのだ。すでにネット上では、リズムゲームを作ったり、複雑な曲を演奏したりしている動画が複数上がっている。
最初のうちは、公式ページにある「Toy-Conガレージであそびの発明」の動画を見て、同じようなものを作るところから始めるといいかもしれない。
ダンボールは購入できる
材質がダンボールだけに遊んでいるうちに弱ってくる部分が出てくるかもしれない。また、工作時に失敗してしまい、重要なパーツが欠けてしまったということになってしまうかもしれない。
そんなときには、オンラインショップでシートを購入できる。
また、個人的に頭を悩ませたのが収納方法だ。
つめを使ってがっちり固定したり、かえしで外れないようにするため、遊び終わった後に分解してしまうということができない。
というわけで、収納に困っていて、MyNintendoストアで購入したときの箱を使っても、高さが足りずにはみでてしまった。

公式ページのQ&A内の「完成した時の大きさは?」の項目には、各部品の大きさや、ピアノの空洞に部品を入れたり、つりをコンパクトにまとめる方法が載っているので、参考になるだろう。
このページによれば、VARAETY KITの部品は「43.5cm×34cm×30cm」の箱に全て収納可能だ。収納用にこういった箱を購入するのも手かもしれない。
VARAETY KITは当初想像していたよりもはるかにボリュームがあった。
どれも共通するのは「手応え」を重視しているということ。実際にダンボールをくり抜き、折り、組み立てていくというところはもちろん、わざわざ動作するところに、ダンボールのベロがあたるようにして音が鳴るようにしたりと、とにかく何かをしたときに反応する、ということを徹底している。それが心地よさにつながるし、ついついのめりこんでしまう要因だろう。
正直なところ、まだまだ遊び足りないし、ダンボールをデコったりなど、試せていない部分も多い。もうしばらく遊んだ後に、何か新たな発見があったら『Toy-Con02 ROBOT KIT』のレビューと一緒に報告する予定だ。
(杉村 啓)(Amazon)