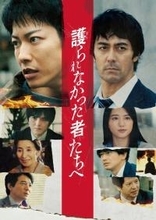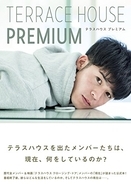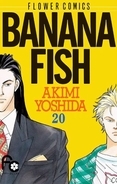かこさとしの作品といえば、「だるまちゃん」「からすのパンやさん」シリーズといったオリジナルのキャラクターが活躍する絵本のほか、川の流れを源流から海に出るまでたどった『かわ』をはじめとする科学絵本など、子供のころ愛読した人も多いだろう。私も、小学生のときに読んだ科学絵本『宇宙』や、年中行事や記念日、偉人の誕生日などをとりあげた『こどものカレンダー』、古今東西の科学者たちの小伝集である『科学者の目』など、彼の著作から少なからぬ影響を受けている。
それでもかこは生涯に600冊以上もの作品を残しており、未読の作品も多い。ちょうど彼について調べる機会があり、最近いくつか作品を手に取ったのだが、なかでも初めて読んだ『ならの大仏さま』(福音館書店、1985年/復刻版:ブッキング、2006年)は、ならの大仏がつくられる過程を歴史、宗教、技術などさまざまな観点から描いており、たくさんのことを教えられた。

ちなみにタイトルが『ならの大仏さま』と、奈良がひらがな表記なのは子供向けだからかと思いきや、そうではなかった。冒頭の文章では「奈良」という地名に注釈がつき、次のように説明されている。
《平らな所の意味とか、あるいは楢の木が生えていたためにつけられた地名といわれている「ナラ」に、諾楽・寧楽・平城・奈羅・那羅・乃楽・奈良の字があてられてきましたが、この本では大仏をさす場合には、ならの大仏と記すことにしました》(原文では「なら」に傍点)
ようするに大仏建立当時は「ナラ」の地名にはさまざまな漢字が当てられていたことを踏まえ、大仏に対してはあえて現在の奈良の字は用いなかったということらしい。このあたりからして、あくまで事実に忠実であろうとする作者の意志が感じられる。
科学的な視点から学界の論争にも一石投じる
かこさとしはこの本を5年間かけて、膨大な資料にあたり、専門家にも教示を受け、また関係の地を何度か取材したうえで、やっとまとめたという。
大仏のような複雑な状況と背景のなかでつくられた巨大な建造物に取り組むには、広い科学的な視野、とくに土木建設の技術的視野を持たなければ、判断を誤る恐れがある。そう考えたかこは、従来の研究を参照するだけでなく、場合によっては自分なりに検証したうえ、新たな説やデータを果敢にも提示している。
たとえば、それまでの本や教科書では、大仏づくりには多量の金が使われたように記載されていたが、かこは計算をし直して、実際に使用された金はさほど多くはなかったことを突きとめた。
また、大仏の鋳造にあたって台座は仏身より先につくられたか、それともあとからつくられたのか、学界では長らく論争となっていた。
『ならの大仏さま』の刊行後、東京藝術大学グループが大仏本体調査を進めた結果、現在では、台座はあとでつくられたという説が学界でも有力視されているという(『週刊 新発見!日本の歴史 11号 奈良時代1 聖武天皇と大仏造立』朝日新聞出版)。
大仏建設中に起こったであろう事故を推測
かこさとしという人はもともと、東大工学部で応用化学を学んだのち、昭和電工という総合化学会社の研究所に勤めていた技術者である。ここまであげたような科学的な考え方も、そうした経歴から培われたものであった。
かこの科学的な見方は、大仏に金を塗る作業の描写にもうかがえる。この作業では、水銀に金を混ぜた金アマルガムという粘土状のものを、あらかじめよく磨いた大仏の表面に塗る。そして金を定着させるため、炭火を使い表面を350度以上の高温であぶり、水銀だけを蒸発させた。しかし、このとき使われた水銀は金の5倍以上と、普通の塗金法で用いる量よりはるかに多かったという。このため、猛毒の水銀蒸気が大量に発生し、おそらく作業者にも被害が出たに違いないと、かこは推測する。作業の様子を描いた絵にも、中毒を起こして体が青くなった作業者が仲間にかつがれていく姿が見える。
思えば、昭和電工はちょうどかこが勤務していた時代、工場排水により阿賀野川水銀中毒事件(新潟水俣病)を引き起こしている。そう考えると、くだんの事故についての記述には、かこの技術者としての反省の念が込められているような気がしてならない。
なお、大仏の塗金作業で水銀が多量に使われたのは、少ない金をできるだけ薄く伸ばし、節約するための工夫であった。
「はっきり簡明に書くこと」と単純化・簡易化は違う?
『ならの大仏さま』の文章は、子供にも読みやすいよう平易に書かれているとはいえ、それでもそこで語られる事柄は複雑で、一読しただけでは理解しにくいところもある。しかし、かこはこの本の終わりに、《真実はそうした複雑さのなかに秘められているのです》と書いている。彼はあくまで複雑なものは複雑なまま提示することで、《入り組んだり矛盾したりする人と人、人間と人間の関係のなかで大仏が建ち、長らえてきたということ》を伝えたかったのだ。
かこは本書を書くにあたり「はっきり簡明に書くこと」を心がけたという。とはいえ、それは「東大寺を造ったのは聖武天皇」などといったクイズの正解のような《単純化や簡易化ではなく、あいまいさや誤解を除き、確かなことをはっきりと明らかに記述したい》ということだと、あとがきに書いている。
おそらくかこは、わかりやすさを求めるあまり、物事を過剰に単純化・簡易化してしまうと、かえって本質から遠ざかってしまうと考えていたのではないか。それゆえこの本は複雑なものは複雑なまま提示するし、専門用語も注釈を入れつつ頻繁に出てくる。これは逆にいえば、読者を信頼していたからこそだろう。たとえ子供でも、興味があれば、最初はわからなくても繰り返し読んだり、まわりの大人に聞くなどして理解しようと努力するはずだ。きっと彼はそんな期待を込めてこの本を書いたに違いない。
ならの大仏はこれまで2度焼失し、江戸時代に再建されたあとも、明治政府の神道国教化にともなう仏教排斥運動、さらには太平洋戦争中に空襲が激化したときと、たびたび取り壊しが検討されたことがあったという。それでもなぜ、大仏は現在にいたるまで残されてきたのか? これは、大仏が建てられた理由とともにこの本の重要なテーマだ。本書の最後の場面には、《大仏を造り、焼き、再建し、保存してきたのは、まぎれもなく人間の意志、行動、考えの結果です》と答えのようなものが書かれているが、それが具体的に何なのかを読み取り、そしてそこから何を学ぶかは、私たち読者に託されている。
(近藤正高)