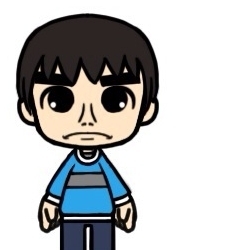ストップ。いま何を見ただろうか。ホームや壁面に設置された「駅名標」を確認したはずだ。この駅名標、鉄道会社ごとに書体やデザインが異なっていることにお気づきだろうか。
駅名標や出口案内、路線図、車両の標記など、駅には「文字」があふれている。その書体やデザインを考察し、愛でる趣味が「もじ鉄」だ。その提唱者、石川祐基の『もじもじもじ鉄 鉄道の書体とデザインほぼぜんぶ』(三才ブックス)がおもしろい。

石川は前作『もじ鉄』で、全国166社ぶんの駅名標を全て写真付きで解説している。例えば、JR東日本の駅名標は、和文が「新ゴB」、英文が「Helvetica Bold」というフォントで書かれているという。「東京」と「Tokyo」では、フォントが異なるのだ。他にも、和テイスト(箱根登山鉄道)、手書き文字(小湊鐵道)、縦書き(富士急行)、Officeでおなじみ「創英角ポップ体」(阿佐海岸鉄道)など、個性豊かな「もじ」の世界を見せてくれた。
『もじもじもじ鉄』では、さらに一歩踏み込み、鉄道会社やデザイナーへのインタビューを中心に構成されている。「どうしてこのデザインなのか」「なぜこの書体なのか」を“中の人”に聞いてみると、思いもよらないこだわりが飛び出しくる。
なぜ京急の文字は「平べったい」のか
最初に登場するのは、品川と三崎口を結ぶ赤い電車・京急電鉄だ。京浜電鉄の駅名標や各種サインは、文字を少し横に引き延ばしているという。
通常、書体は縦横比1:1の「正体(せいたい)」で作られており、書体を平べったくする処理は「平体(へいたい)」と呼ばれる。なぜわざわざ文字を平体にしているのか? サイン計画を担当したデザイナーはこう説明する。
「漢字の形には凹凸があるため正対のまま組むと、大きい、小さい、大きい、小さい、と凹凸が目立ってしまうんです。それを平体にすることで均一なバランスに近づけています」

言われてみれば……というレベルの、ほんのわずかな違いである。だが、細部にまでこだわるのがプロだ。福井県を走るえちぜん鉄道にも、プロの仕事があった。
えちぜん鉄道では、福井・新福井・福井口の3駅に、国内でも珍しい木製のサインを設置している。ヒノキのプレートに打たれた文字は、和文に「たづがね角ゴシック」、欧文に「Vaud」というフォントを使っているが、これとは別に数字にだけ「Akko」というフォントを採用している。
もちろん、これには理由がある。
何気なく目に入る文字には、デザイナーたちのこだわりが隠れている。気づかなかったことばかりだが、「気づかない」ことが正解かもしれない。違和感なくスムーズに読める文字こそ、デザイナーが腐心して生み出した結果なのだから。
駅名からゴミ箱までフォントを統一
文字の読みやすさを追求した事例に加え、『もじもじもじ鉄』には「ブランドイメージ」を追求した事例も取り上げている。駅全体のサインデザインを統一することで、鉄道会社を印象づけることができるからだ。
関西を走る京阪電鉄は、和文を「新ゴ M」、欧文を「Frutiger Bold」に統一している。その徹底ぶりはすさまじく、駅名標や出口案内のみならず、エスカレーターの注意喚起、自動販売機コーナー、ゴミ箱の「燃えるゴミ」などの表記、車両のLED表示に至るまで、文字という文字が全て「新ゴ M」と「Frutiger Bold」だ。ちなみに「Frutiger」は、シャルル・ド・ゴール空港のサイン用書体として生まれたフォント。
また、富山県を走る第三セクター・あいの風とやま鉄道のロゴや駅名標は、日本で唯一「フォーク」というフォントで書かれている。波をモチーフにした社名ロゴは、富山に吹く柔らかな風を表現しており、そこにマッチした書体がスマートな雰囲気をまとう「フォーク」だった。駅名標はブルーとグリーンの2パターンがあり、海側と山側で色分けして設置。海から山へ吹き抜ける「風」を表現している。
『もじもじもじ鉄』にはインタビュー以外にも、昔と今のサインの比較、フォントメーカー別の駅名標図鑑、映えるサイン特集など、鉄道と「もじ」にまつわるコンテンツが詰まっている。元々「撮り鉄」だった著者だけあり、どのページを開いても写真が美しい(駅の掲示物をきれいに撮るのは照明の関係とかあって大変なのに……と、路線図マニアの筆者はうらやましく思ったりもする)
一度「もじ鉄」の世界を知ると、駅の光景が違って見えてくる。壁に、頭上に、足元に、描かれたサインにこめれている「意図」が気になる。読み終えたあと、新たな視界がインストールされていることに気づくだろう。
『もじもじもじ鉄 鉄道の書体とデザインほぼぜんぶ』(三才ブックス)
著者:石川祐基
【インタビューに登場する鉄道会社&デザイン会社】
京急電鉄、都営地下鉄、相模鉄道、つくばエクスプレス、東急電鉄、湘南モノレール、横浜シーサイドライン、えちぜん鉄道、あいの風とやま鉄道、静岡鉄道、四日市あすなろう鉄道、京阪電鉄、JR西日本、阪急電鉄、福岡市営地下鉄
i Design inc. 、黎デザイン総合計画研究所、Superelement、氏デザイン、富士フイルムイメージングシステムズ、八島デザイン事務所、METROPLEX、GOOD MORNING、伊藤達雄、アド近鉄、GKデザイン総研広島
(井上マサキ)