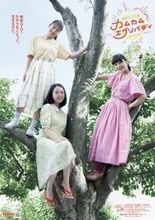2018年、ゴミ収集員としての体験を綴ったエッセイ「このゴミは収集できません」(白夜書房)を出版して大ヒット。もちろん、今でもゴミ収集は続けていて、その日常生活を奥様の滝沢友紀さんがコミック化した「ゴミ清掃員の日常」(講談社)を今年5月にリリースした。


……なんて思っていたら、8月6日には子ども向けにゴミの分別をクイズ形式にした4778316770/">「ゴミ育 日本一楽しいごみ分別の本」(太田出版)を刊行! マシンガンズ滝沢は今をときめく売れっ子ゴミ収集芸人なのだ。

ここでは「ゴミ清掃員の日常」をご紹介したい。これがしみじみ良い本だった。
ギャラ315円……ゴミ収集芸人になったわけ
まず、著者がなぜゴミ収集を始めたのかが語られる。理由はシンプル。お金がなかったのだ。ライブのギャラは315円。芸歴20年、テレビバラエティにも多数出演した芸人のシビアな現実……。必死にツテを探り、たどりついたのがゴミ収集の仕事だったというわけ。
当然ながら、読んでいるとゴミに関する知識がどんどん身についてくる。たとえば、可燃ごみと不燃ごみの分類。
一方、使い捨てカイロやアルミ箔、ハンガー、コップ、電池などは不燃ゴミ。焼却炉の中に不燃ゴミが溜まると、火を止めて手作業で不燃物をかき出す清掃工場もあるらしい。作業を終えて、もう一度火をつけるのにかかる経費が一回につき200万円から350万円。もちろん税金だ。「ビール瓶1本くらいわからねぇだろ?」という気持ちで可燃ゴミに不燃ゴミを混ぜて捨てれば、それだけ税金が無駄になるということだ。
よく話題になるスプレー缶の捨て方だが、著者の地域では「一般家庭では穴をあけないよう呼びかけている」のだという。穴をあけるときにケガをする人が増えているからだ。不燃ゴミの日に別の袋にまとめて、「スプレー缶」と書いておけば回収してくれる(事業系の場合は除く)。
キーワードは「日常」
とはいえ、「ゴミ清掃員の日常」はゴミに関する知識だけが羅列されている本ではない。作家の顔も持つ滝沢氏の観察眼とストーリーテラーぶりも存分に味わえる。
印象的だったのが、ガンに冒されて30代前半でこの世を去った同僚のエピソード。彼は幼い4人の子どもたちに働く姿を見せたいと考えて、抗がん剤治療を選ばなかった。彼の選択が良かったのか悪かったのかは誰にも判断できない。一緒に働きながら彼の横顔を見つめてきた著者は「いつも通りの“日常”を繰り返して人生を終えたいという希望を見た」と綴る。
著者自身も、人生の難局にぶつかってしまう。ハードなゴミ収集の仕事をしながら、お笑い芸人を続けるのは大変なこと。さらに家のこと、子どもたちのこと、お金のこと……。さまざまな難題が積み重なっていく。
どんな結論になるかはぜひ本書を読んでもらうとして、キーワードになるのは「日常」という言葉。なるほど、「ゴミ清掃員の日常」というタイトルにはそういう意味が込められているのか、と得心する。子どもたち、パパは頑張って働いてるよ!(ママも頑張ってる)
人生の機微がじんわり伝わってくるエピソードが多いが、漢字にルビがふってあるのは子どもにもゴミのことを知ってもらいたいと思う著者の気持ちの表れだろう。
余談だが、滝沢さんは東京生まれなのに筆者と同じ中日ドラゴンズファンで、野球観戦もご一緒させていただいたことがある。滝沢さんの野球コラムも素敵なので、ぜひご一読を。
(大山くまお)