流浪と反逆!室町幕府のラスト将軍・足利義昭の苦難と悲劇に満ちた壮絶人生【前編】
■理想と現実の板挟みー信長との対立
将軍としての義昭の理想は次第に、信長の現実的な野心と次第に衝突するようになります。信長は義昭を支える一方で、実際には幕府の権威を利用して自身の支配を広げる戦略を進めていました。
義昭は毛利氏や本願寺などの反信長勢力を結集し、信長の野望を阻止しようとしました。この動きは、義昭が単なる傀儡ではなく、独自の理想を持った指導者であったことを示しています。しかし、信長の軍事的優位と戦略の巧みさの前に、義昭の努力は実を結びませんでした。
1573年、義昭は信長によって京都を追放され、室町幕府は実質的に終焉を迎えます。しかし義昭は諦めず、西国へと活路を見出したのでした。

足利義昭坐像(等持院霊光殿安置) 森末義彰, 谷信一 編『国史肖像集成 将軍篇』(1941 目黒書店)より
■鞆幕府の誕生―備後国への下向
1576年、義昭は備後国の鞆の浦(とものうら)に移り住みます。将軍の座を失った後も理想を追い続けました。
この地を選んだ背景には、足利尊氏が光厳上皇から新田義貞追討の院宣を受けた由緒がある場所であり、さらに10代将軍足利義稙が大内氏の支援を得て京都復帰を果たした「吉兆の地」としての意味がありました。
鞆で義昭は「鞆幕府」を樹立し、毛利氏の支援のもと、全国の武士や旧室町幕府の家臣たちに呼びかけて反信長勢力を結集しました。鞆幕府は義昭を筆頭に、かつての幕臣や織田氏と敵対する諸大名の子弟などが集まる総勢100名以上の勢力を持つに至ります。
■毛利輝元との協力と鞆幕府の活動
鞆幕府の基盤となったのは、毛利輝元を中心とした西国の勢力でした。
義昭は御内書を全国の大名に送ることで、反信長の結集を図ります。特に上杉謙信や武田勝頼に信長包囲網への参加を呼びかけたほか、毛利水軍と本願寺の協力による大阪湾での戦闘(第一次木津川口の戦い)では大きな成果を上げました。
しかし、信長の圧倒的な軍事力や戦略の前に、鞆幕府の活動は次第に限界を迎えます。信長が各地の反対勢力を次々と鎮圧する中、義昭の影響力も弱まり、毛利氏は防衛を優先する姿勢に転じました。
■鞆幕府の意義
鞆幕府は、足利義昭の政治的理想を象徴する最後の試みでした。信長との対決に終始する中で、義昭は文化や伝統の復興にも尽力し、室町幕府の権威を維持しようとしました。義昭の行動は単なる「追われた将軍」としてではなく、武家社会の正統性と文化を守ろうとした「最後の将軍」としての姿を映し出しています。
鞆幕府が成立した背景には、信長の急速な勢力拡大に対する反発がありました。しかし、義昭が鞆に下向した当時、西国の主要大名である毛利氏と信長との関係は緊張状態にありながらも、同盟の形式を保っていました。そのため、義昭が鞆に拠点を構えたことは、毛利氏にとって大きな政治的負担となりました。
信長は毛利氏の領域への影響力を拡大しつつあり、同時に毛利氏の敵対者である浦上宗景を支援して圧力を加えていました。一方、義昭は毛利輝元に対して信長との決戦を求めましたが、輝元は慎重に動く姿勢を崩さず、義昭の求めに直ちに応じることはありませんでした。最終的に毛利氏は義昭の要請に応じる形で反信長勢力として立ち上がりましたが、信長との戦いは厳しいものとなります。
【後編】の記事はこちらから
流浪と反逆!室町幕府のラスト将軍・足利義昭の苦難と悲劇に満ちた壮絶人生【後編】
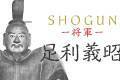
参考
- 桑田忠親『流浪将軍 足利義昭』(1985 講談社)
- 奥野高広『人物叢書 足利義昭』(1996 吉川弘文館)
- 久野雅司 編著『シリーズ・室町幕府の研究 第二巻 足利義昭』(2015 戒光祥出版)
- 久野雅司『中世武士選書40 足利義昭と織田信長 傀儡政権の虚像』(2017 戒光祥出版)
- 黒嶋敏『天下人と二人の将軍:信長と足利義輝・義昭』(2020 平凡社)
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan
































![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



