しかし今回紹介するのは、伝説を築き上げたプレイボーイ歌人 平貞文(たいらのさだふみ)!
■家柄、才能も十分な平中は完璧プリンス。されど、嘘泣き作戦で恥をかく!
平貞文は桓武平氏、それも桓武天皇の玄孫と言う名門中の名門の御曹司として生まれた人物で、美形なだけでなく歌にも優れていました。平さんの次男坊と言う意味で、平中のあだ名でも呼ばれます。
後世、中古三十六歌仙として称えられた平中は、『古今和歌集』などの歌集にも名を連ねる歌の名手にして、従五位上の官位を授かるほどの高スペックな才能を誇った、光源氏も顔負けの完璧なプリンスだったのです。その平中が歌と並んでこよなく愛したのが、美女との逢瀬(おうせ)です。
そんな平中を見て気が気じゃなかったのは彼の奥方。彼女はいつも夫が女性を口説く際に持ち歩く道具に細工をしました。平中は目を付けた女を落とすために嘘泣きをするべく、水を入れる小瓶と口に香りを付ける丁子(香料)を持っていたのですが、奥方は水を墨に、丁子をネズミの糞にすり替えてしまったのです。
無論、それを使ってしまった平中の美貌は墨で真っ黒、ネズミの糞なんて臭くて食べることも出来ないので、その日の逢瀬は大失敗…たいそう恥ずかしい思いをした平中はこれに懲り、嘘泣きと丁子を食べる作戦をピタリとやめてしまったそうです。
■惚れてまうやろ~?愛しの侍従に振り回される平中

次に紹介する平中の伝説は、『今昔物語』や芥川龍之介の『好色』にも取り上げられているエピソードです。ある大臣の家に仕える“侍従”と言う女房に惚れた平中はラブレターを書いて『見たという返事だけでも頂きたい』と伝えたところ、その手紙の“見た”と書いた部分だけが帰ってきたり、夜這いをかけても騙されて逃げられるなど、散々な目に遭います。
あの意地悪女を嫌ってやる手はないものかと思いつめた平中は、侍従がトイレとして使っている箱を召し使いから奪い、その中身を見ます。
平中が口にしてみると、それは丁子を煮詰めた液の中に野老(山芋の仲間)とお香、甘味料を調合した固形物で、侍従はそうなることを予測して平中にお菓子で作ったニセの汚物を掴ませたのでした。
数々の女を陥落させた自分を上回る侍従の機知と魅力に恋い焦がれた平中は、遂に病に倒れて死んでしまう…としてこの説話は終わります。実際の平中こと平貞文は延長元年(923年)に亡くなっていますが、失恋がきっかけで死んだかは不明です。
しかし、このような逸話が生まれるほどに彼が魅力的な文化人にしてプレイボーイであったかを今に伝える、またとない物語であるとも言えます。
平貞文(たいらのさだふみ)
日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan















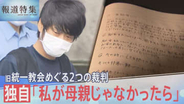











![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)
![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)
![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)




![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)



