オリジナルアニメーション『海賊王女』 第3弾PV
明るくて美しくて綺麗な「白」のファンタジー
――『海賊王女』は中澤監督が原作を務めていますが、どのような形で制作はスタートしたのでしょうか?
中澤一登 まずは僕の方で企画書を何本か用意したんですが、その中で一番大変なものをプロデューサーの黒木さんが選んだところが始まりでした(笑)。
――黒木プロデューサーによると、中澤さんが一番やりたがっていたものだったということですが?
中澤 確かに本命の企画ではありましたが、同時に大変なのは予想がついていて(笑)。でも、黒木さんがやりましょうと言ったことで覚悟を決めました。
――同じく中澤監督が原作を担当した『B:The Beginning』も近現代異世界を舞台とした作品でしたが、そういった世界を描きたい欲求があるのでしょうか?
中澤 とにかく「ファンタジー」がいいとは思っていました。リアルな世界をアニメで描くということにあまり意味を見い出せないというか、「アニメなのにリアルとは?」と考えてしまうんですね。
――たしかに、フルCGで描こうが実在のストーリーだろうが、アニメという手段を用いる段階で虚構を描くことになるとは思います。
中澤 僕が映像を見たり音楽を聴いたりする理由として、やはり「現実逃避」というところはあるんです。だから、それを実現できる世界として描いたのが『-Beginning』であり、『海賊王女』であり。ただ、前者ではダークで「黒」の世界を描きましたが、反対に明るくて美しくて綺麗な「白」の世界を描こうと思ったのが『海賊王女』です。
――そういう選択をされる方はいますね。
中澤 いますよね。そこから、彼と全く反対の能力もあるのではないかと思ったんです。何かを選ぶと、必ず正解のような方に進むような。そこも作品に反映されてはいます。
――中澤監督の頭の中をどのような形で具現化されていきましたか? 今回、中澤監督以外に、高橋哲也監督、藤井サキ監督という監督3人体制をとられていますが、脚本の窪山阿佐子さんも含めてどのような役割分担だったのでしょうか?
中澤 いや、すべて会議で決めていきましたし、どちらかといえば僕が一番おとなしかったくらいです。最初から「少女漫画」を作ろうとは決めていたので、男性としては強い意見を発することができなかったですし。どうも自分は女心がわかってないらしくて(笑)、「ここはおかしくない?」と発言すると女性陣から「そんなところはどうでもよくないですか」みたいに言われるんです。あとは、作中のイベントに「これは必要?」と疑問を呈しても「何言ってるんですか? 絶対必要ですよ」みたいに却下されるとか。雪丸には多少意見も反映されましたが、フェナと紫檀に関して言えば男性陣の意見はゼロだと思っていただいて大丈夫です(笑)。
――そういった中で音楽に梶浦さんを起用された意図についても教えてください。
中澤 現代音楽をいろいろと聴いていく中で、誰よりも音の組み合わせが綺麗だと思ったのがきっかけですね。どの音も粒だっているのに流れていくような曲線を描いていて、しかもその角度が大きいんです。全ての音楽に起承転結がありますから、なにしろ絵が浮かびやすいんですね。例えば、部屋の中で音楽を聴いたとき、僕が頭の中でその音楽が流れる景色を完全に描くことができました。ただ、非常に著名な方ですので、「ダメ元でお願いしていただけないか」というところではあったんですが、(フライングドッグ代表取締役社長 )の佐々木(史朗)さんとは若干交流があったので、「久しぶりですね」みたいな感じで裏から少し攻めてみました(笑)。
――中澤監督が描きたい世界に必要な音楽だったわけですね。
中澤 ダメなら似たような曲を作る人に、と言ってしまったくらいですからね(笑)。
――でも、いませんよね。
中澤 いないんですよね。
――梶浦さんはオファーが来たとき、『海賊王女』にどのような印象を持たれましたか?
梶浦由記 最初にタイトルとプロットをいただいて。もうタイトルだけで「ズキューン!」って感じでしたね。しかも絵はすごく美しかったですし。それに私は、光が当たる海の上を渡っていく冒険物というものをやったことがなくてですね。比較的、ダークな傾向が多いと言いますか。
中澤 日光のイメージがあまりないですよね(笑)。
梶浦 はい(笑)。光の当たらない場所の音楽をより多く作ってきたので。だから、そこでまずすごくワクワクしました。その後にもいろいろと資料をいただき、最後にものすごく熱量のあるメニューと共に打ち合わせをさせていただいたんですが、ずっと楽しかったですね。
――今回は中澤監督が音響監督も兼ねていますので、メニュー出しは中澤監督が直接出されたのでしょうか?
中澤 はい。組み立ては僕ともう一人で行ったんですが、(どのような曲が欲しいかを説明した)メニューについては気持ち悪いと思われるのを覚悟でたくさん書きました(笑)。
梶浦 でも、その方がイメージ湧きますね。
――ではいつもはそれほど書かないんですか?
中澤 書かないですね。
梶浦 そうなんですか?
中澤 お任せしますで終わることが多いです。でも、音響監督を兼任するのが初めてでしたし、敬意としてそうするべきだという考えはありましたね。
梶浦 お仕事するのも初めてという部分も大きかったですよね。
中澤 とにかくもう「告白」ですよ。ラブレター感覚。「こういうことなんです」って思いを書いて、でも最後は「好きにしてください」「全部無視してもらってもかまいません」って。
梶浦 今でもメニューを見るとその熱量が甦ってきます(笑)。
――梶浦さんは先ほど、「イメージが湧きやすい」と仰いましたが、その音楽メニューに対してはどのような印象を受けましたか?
梶浦 音楽メニューをいただくとき、基本的に脚本もいただいていて、それを読んで音楽の意図を汲み取ってから当日の打ち合わせに臨むんです。でも、いろいろと「可能性」ってあるじゃないですか? 悲しい曲にしてもどれくらい悲しさを前面に出していいのか、場面に合わせるにしても綺麗にまとめた方がいいのか盛り上げた方がいいのか、そういった可能性に関してはお話を伺うんですが、非常にストーリーと明確に密接したメニューでしたので、イメージはすごく湧きやすかったです。
音楽から湧きだしたイメージに合わせてあらためて作画を
――梶浦さんは『海賊王女』という作品にはどんな音楽が求められていると感じましたか?
梶浦 「ワクワク」です。「これはワクワクだな」って思いました。
中澤 そうですね。
梶浦 話の進展が速く、どんな未来かはわからないけれどもみんなが積極的にどんどんと未来へ向かって前進していくストーリーなんですよね。積極的ではなかった人もフェナに巻き込まれて。だからやっぱり、音楽でも「次はどこへ行くんだろう」というワクワクがないと、あるいは辿りついた場所でワクワクしてもらわないといけない。だから、「この場所に行きたい」とか「ここで遊びたい」とか「この船に乗って海の上を走ってみたーい」とか、そういったワクワクを届けられる音楽にしたかったですね。
――現実世界には存在しない異世界感を持つ作品でもありますが、その点で意識された点はありますか?
梶浦 旋律を曖昧にするというか、わずかな異世界感を必ず入れておくというところですね。『海賊王女』はいろいろなバックボーンがある作品ですが、向かう場所は誰も知らない場所というか、いつも異世界な雰囲気にしたかったんです。冒険の始まりとなる娼館の島もすごくいろいろなものが混在しています。
中澤 本当にそうですね。
梶浦 どこにもない異世界と言ったらこれでしょ、みたいな。久保田早紀みたいな。
――「異邦人」ですね(笑)。
梶浦 あの曲も「どこでもない」じゃないですか?イスタンブールを感じさせますが少し違いますし。やっぱり私たちが一番ワクワクするのはどこの国でもない異世界、「ここではないどこか」ですよね。そういうものが漂う音楽にしたいとずっと思っていました。だから、違和感がちょっとある旋律を目指しました。海の上で聞こえる音にしても街の音にしても、ここから先の何かを夢見るような音楽にしても、素直なテンションではないというか、「ここだけどうしてマイナーノートに?」「どうしてシャープに?しかもここだけ1音低いのはなぜ?」というように。でも、ちょっとでいいんですよ。違和感を意識させてもいけないので。「よく聴いたら何か違うね」という音楽を狙っています。
中澤 今回、一度に全曲が上がってきたんですけど、聴いていたら鳥肌が立ち過ぎて風邪引きそうでした(笑)。思わず「CDはいつですか?」ってすぐに聴きましたからね。12/8らしいんですが(笑)。でもずーっと聴き続けていると(The Beatlesの)『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』の頃のコンセプトアルバムの雰囲気を感じたんですよ。それぞれが独立した曲ではありつつも全体として作品のように仕上がっていたんですね。
――あるアニメ作品のサウンドトラックという共通点以上にコンセプトを感じるような?
中澤 そうですね。特に核となる「Vice Versa」となる曲を聴いたときはもう「ああああぁ……」ってなりましたね。なんて言うか……。どう言ったらいいんでしょうね。
――魂が抜けてしまうような感じでしょうか?
中澤 あ、そうそう、そうです。聴いていたら「いや、そうなんだよね」という感じになりましたし、同時に「癒し」でもありました。ただ感動したと同時に、この曲がはまる場面を作らなければいけない、と負けたくない気持ちも少し出てきました。聴きながらずっと、「どういう色なんだろう」というようなことを考えながら作業していました。今までそんな感覚で仕事をしたことはなかったですね。多分日本で一番聴いているのは僕だと思います。1年以上にわたって1日6ループくらいを続けていますからね。それも今後15年くらいにわたって。
――宣言、ですね(笑)。
中澤 それから先ほど仰られた隠し味みたいなのが入っているんです。それによって聴いていたら「ここに向かうだろうな」という予想を裏切られて驚かされるんですよ。面白いというか不思議な感覚でしたね。
梶浦 でも、コンセプトアルバムっぽい作り方を少ししちゃったかもしれないという自覚はあります。
中澤 やっぱりそうですか。
梶浦 (『海賊王女』は)非常にドラマチックな作品ということで、作っていたらだんだんサントラ曲なのになぜか4分くらいの長さになることがあって。
中澤 そうなんですよ。サントラっぽくない感覚でした。
梶浦 「作り込んで長くなったらサントラとしては使いにくいのでは?」というところに少し入り込むことがありました。多分、物語の世界観や海賊王女というコンセプト、海の上を旅するイメージによるところだと思うんですが。なにせ船がめちゃめちゃかっこいいし、しかも(第2話の)その登場シーンがめちゃめちゃドラマチックですから。そこに安っぽい音楽を流せないじゃないですか?(笑)。「これは力を入れなければ」と引っ張られた結果、少しだけサントラの域を逸脱し、饒舌になり過ぎたところが無きにしも非ずかもしれません。
中澤 いやいやいやいや。
梶浦 コンセプトアルバムに聴こえたのも、そちらに寄ったからかもしれないです。
――でも、そうなるとどうシーンに当てはめてくれるか楽しみですね。4分をそのまま使うことはないでしょうし。
中澤 ところが。使っているんですよね(笑)。終盤ではフィルムスコアリングまでやっていただきましたし。
梶浦 最後の話数ではフィルムスコアリングをやりたいですね、という話になったんです。だから、あとからシーン合わせで音楽作ったところもありました。
――では、『海賊王女』の魅力の一つとして、梶浦さんの音楽との一体感を見てほしいというところでしょうか?
中澤 いや本当に。そう、本当にそうですよ。だって音に合わせて作っているんですからね。
梶浦 あと、実は不思議なご縁もあったんですよ。作品の中に登場する街の一つが、私が遊びに行ったことのある街で。
中澤 モデルにした街に行ったことがあるらしくて。
梶浦 その街の雰囲気をよく覚えていたので、「わ、あそこだ」ってすぐにわかりました。イダー=オーバーシュタインという鉱石で有名なドイツの観光地なんですが、そこにサマースクールのような形で行ったことがあるんです。元々は鉱山都市で、今も鉱石や宝石では有名な街なんです。子供が行って水晶を掘る体験もできるんですね。山のほとりにある、すごく綺麗な街ですし、楽しかったし、多分、一週間くらい滞在したと思うので覚えていたんです。でもまさか、自分の関わる作品に思い出のある街が出てくると思わなかったですね。
――中澤監督がイダー=オーバーシュタインを登場させた理由というのは?
中澤 ヘッジスの水晶ドクロが作られた街なので。
――オーパーツとして有名でしたが、実は近代に作られた加工品であると判明した。
中澤 そこは職人気質の街なので作品に銘を掘らないということも聞いて、「なんて神秘的な街だ」とも思ったんです。そうしたら梶浦さんに「行ったことがあって」「観光地なんです」と言われて、「えぇっ?」となりました(笑)。ネット上にあまり情報がないのも、神秘的で謎めいた街だからかと思っていたんですが、ただ小さい街らしくて。
梶浦 観光地といってもあくまでドイツ国内での観光地で。それにすごく綺麗な街なんですよ。でも、そんなマイナーな地名がまさか出てくるとは思いませんでしたし、作中で一瞬立ち寄るだけではありますが急に親しみが湧いてきました。
中澤 いや、でも、その街で流れる曲がめちゃくちゃいい曲で。
梶浦 これ以上、光栄なことはないです。作曲家冥利に尽きすぎています。
中澤 こちらこそ絵描き冥利に尽きるという感じです。作りながら、「見ていて楽しいと思えるのは何十年ぶりだろう」と思いました。背景を頼んだ竹田(悠介)さんは、個人的に今の日本で一番上手いだろうという方なんですが、僕の意図を理解してくれて、すごく綺麗に仕上げてくださったので嬉しかったです。話の筋なんかどうでもいいように思えてくるというか(笑)、絵が綺麗だから見ていられる感覚はすごく久しぶりでした。昔のファンタジー映画のように、よくわからない部分もひっくるめて目の前にある映像をただ受け入れられる、というところが懐かしかったです。
梶浦 私はいつも背景を先にいただくんですが、今回も音楽を作り始める前に「あるだけください」と言ったんですね。で、背景画をいただくと作品のキーになると思う絵をカラープリントして、見えるところに貼ってから作曲するんです。それを見れば、「この世界だったらこういう音楽が聴きたいな」とすごく思えるので最後のサウンド感に悩まないんですね。今回は、第1話に登場する紫色の街並みは早くからいただいていたので、それを貼って作っていました。あと、夜景もいっぱい貼っていましたね。だから『海賊王女』は、タイトルだけでワクワクするコンセプト、ストーリー、そしてすごく美しい背景画というところがすごくエネルギーになりましたし、これでもかというほどにインスピレーションをいただきながら音楽を作ったんですね。その音楽が作品にピッタリだと言ってもらえるなんて、これ以上の名誉は作曲家にとってありませんね。
中澤 こちらでも、「(音楽に)これ以上は望めないよね」という話は作りながらしていました。だからこそ色も雰囲気もシーンも音に合わせて作っているんです。
――音楽に合わせて作画を? サントラ曲をもらってから作画に入ったということでしょうか?
中澤 そうです。撮影のフィルターも音に合わせています。でも、それが一番確実ですよ。僕が音楽から受け取ったイメージを絵にしているので。だから声を大にして言いたいですが、全アニメがそうするべきです。
――作画作業に入る前に劇伴を作ってもらうべきだ、と。
中澤 作業前に音楽が上げられる状況を整えた上で発注し、上がってきた音楽を元にあらためて作るというやり方をとるべきだと思いました。アフレコではなくプレスコで行っていますしね。
梶浦 普通、音楽が絵に合わせてカラーやトーンを変えることはままありますが、絵の方で合わせていただけるなんてことはまずないので、本当に光栄です。
――いわば、一度できた作画を作り直すというのは、スケジュール的にも労力的にも大変だったのではないかと思うのですが。
中澤 スケジュールに関しては最初からその想定でしたし、そこに余分な労力がかかったという感覚もありません。一度組み立てたものをばらしてもう一度組み直した方が良くなるのは当然という感覚ですね。むしろ「一度ではできない」ですよ。
――作画と音楽、どちらの作業が先行したとしても、整えるなりすり合わせるなりの工程が必要ということでしょうか?
中澤 正直なところいただいた音楽のイメージに絵が追いついていないという感覚だったんですよ。だから絵をそのレベルまで持ち上げないと失礼ですし、単純に負けたくないという気持ちですよね。「音楽はいいんだけど」と言われるのが本当に辛いので。だから徹底的に絵はブラッシュアップしましたし、逆にフィルムスコアリングのシーンも編集し直しました。
――『海賊王女』の世界観構築に梶浦さんの音楽が大いに寄与しているというところでしょうか。ある意味、クレジットの「原作」に「梶浦由記」の名前があってもいいくらいの。
中澤 ええ、入っていてもいいと思います。
梶浦 いや、とんでもない(笑)。
中澤 音楽のほかに「Special Thanks」と入るとか。でも、そんなことをしたら梶浦さんが一番困惑するでしょうが(笑)。
深みのある奥行きが描き出された美しい絵がそこに
――OP主題歌も梶浦さんが担当されていますが、こちらも中澤監督の希望でしたか?
中澤 はい、「主題歌もお願いしてください」と。もう全部お願いしてください、と(笑)。
――OPに関しては何かオーダーされましたか?
中澤 いや、何も。すべてこちら側が合わせることが正解だと思っていました。でも、それも初めてに近いですね。何しろ、基本的にOPの製作は時間がないので。
――どうしても、放映初回分の作業がほぼほぼ終わるようなタイミングでやっと、OP制作に入れることも多いと聞きます。
中澤 そうなんですよ。だから曲が上がってからじっくり考えてOPを作ることができたのは初めてかもしれないです。「むぅ……」って言いながらやってました(笑)。
――梶浦さんとしては、どのような楽曲をJUNNAさんに歌ってもらうイメージでしたか?
梶浦 最初に出した曲はもう少し暗かったんですよ。JUNNAさんが歌う曲をずっと聴かせていただいていて、マニアックであったり大人っぽかったりという曲が多かったので、「あまりハジけてはいけないのではないか」という思いが私の中にありました。それに『海賊王女』のストーリーも、明るいところもありますがそれだけではないので、ある意味、どの方向性にもOPを持っていけますよね。だから、インナーな曲を提出してみたんですが、そうしたらフライングドッグさん側から少し暗いんじゃないかという意見をいただいたので、それならということで迷わず「ワクワク路線でいきます」と宣言し、作らせてもらったのが今の曲です。勿論、JUNNAさんはお子様な感じではない女性なので、のびのびとしたワクワク感がある曲、というところですね。「『海賊王女』ってどんな作品だろう?」と思ってOPを見た方が、「私も海賊になって船で海を渡ってみたい」と思えないといけないので。
中澤 すごく景色の広い曲だと思いますね。音が「見渡す」という感じというか、境目がないようなイメージを持ちました。なので絵も回り込みをたくさん使っています。サビの部分は「海」というよりも海中のイメージが浮かんだんですが、でも絵的にただの海中だとつまらないのでメキシコのセノーテをモデルにしています。
――フェナが海中で回っているシーンですね。
中澤 本編ではそこには行かないんですが(笑)。あくまでイメージで。
梶浦 でも、この先で行くかもしれないですよね。
中澤 いや、その通りです。2ndシーズンがあれば。
梶浦 2ndシーズンのことは考えていなかったです(笑)。フェナたちの将来を想像しただけで。でも、このお話なら2ndシーズンも作れますよね。
中澤 いくらでも作れますね。しかも、アメリカでは好評をいただいているので可能性はあるかもしれないです。
――完成したばかりのOP映像を先ほど梶浦さんもご覧になりましたが、感想をいただけますか?
梶浦 いや、もう、「幸せだなぁ」と。あんな素晴らしい映像をつけていただけるとは、なんて幸せな曲だろうと思います。
中澤 見ているとき、僕は逃げ出したかったですけど。
梶浦 いや、本当に美しくて度肝を抜かれました。
――ちなみにEDについては、OPと何か関連付けて選ばれるなどはあったのでしょうか?
中澤 そこは全く。OPとEDで大きく差異をつけるつもりはなかったですし、あくまでもOPはOP、EDはEDということで曲を作ってもらい、その候補曲の中から一番いいと思うものを選ばせてもらいました。ただ、最初は3分全てを使って起承転結が作られている曲になっていたので、(TV用に)切り出すと静かな部分だけになってしまいます。なので、(90秒の)尺に合わせて起承転結をつけていただけるとすごく嬉しいですとは伝えました。あとは何よりもアウトロがすごく良かったので、「そこを全部拾ってもらえませんか」と佐々木さんに言いました。映像に関しては、もう一人の監督である高橋に全部任せています。でも、歌詞も含めて、OPもEDも世界観を完全に理解していただいたので、それだけでもう嬉しかったですね。だからそこでもやっぱり「負けたくない」とは思いました。
――最後に、お二人が作りながら感じた、『海賊王女』の魅力を教えていただけますか?
梶浦 ストーリーのワクワク感や前に進む感じは勿論ですが、やっぱり絵が綺麗なんですよね。フェナもですし、特に街はどこに行っても、奥行きのある綺麗な深みがあります。世界が綺麗だと、そこで誰かが一言を発するだけで物語が始まりますし、そういう説得感を持っている絵なんです。「そこに行きたい」「この夜景が見たい」って思わせてくれますね。第1話を見たとき、脚本を読んでいたので何が起こるかは勿論知っているんですが、力のある絵が後ろに付くだけで台詞の聴こえ方が全然変わるということをあらためて気づかされました。それはすごく衝撃でしたね。なので、この美しい世界がどんどんと前に進み、さまざまな物語が巻き起こっていく、その、美しさとめくるめく物語の両方を楽しんでいただきたいです。そこで音楽が上手くサポートできていると嬉しいですね。
中澤 そこは同じ気持ちかもしれないですね。背景がすごく綺麗で空間が抜けているという感覚はあります。取材写真を撮った場所の「奥」がどのように抜けていたかという記憶はすごく残っていて、コンテを僕が一人で全部やっているというのもあり、その記憶だけで書いたんです。それに3Dによるレイアウトといったものは一切使っていません。実にアナログなんです。その場所の空気みたいなものが感じられる絵が描けたら、という思いがあったんです。劇場アニメと違ってTVアニメはフレームが小さいのでどのように描き切るかかなり四苦八苦しましたが、大きなものは大きく、小さなものは小さく、空間やそのスケール感を描くことができたと思っています。だから、見れば旅行に行った気分にさせる自信はあります。
――3DCG全盛の時代にあえてアナログな手法で美しい景色を描いている作品なんですね。
中澤 昔ながらのアニメの作り方に近いと思います。だから正直、昔よくあったアニメという感じになっているので、全然尖がっていないんです。キャラクターも物語も。丸みを帯びた作品になっていると思います。
INTERVIEW & TEXT BY 清水耕司(セブンデイズウォー)
●作品情報
TVアニメ『海賊王女』
MBS 10月2日より毎週土曜26時38分~ ※第1話は26時08分より放送
TOKYO MX 10月4日より毎週月曜24時30分~
BS朝日 10月8日より毎週金曜23時00分~
AT-X 10月3日より毎週日曜23時30分~
※リピート放送 毎週木曜29時30分~、毎週日曜8時30分~
配信情報
FODにて独占配信
【スタッフ】
原作:中澤一登×Production I.G
監督:ToyGerPROJECT
中澤一登
髙橋哲也
藤井サキ
脚本:窪山阿佐子
キャラクター原案:中澤一登
メインキャラクターデザイン:高橋靖子
キャラクターデザイン:西村理恵
コンセプトアート:西田 稔
色彩設計:土井 和
美術:竹田悠介 楠元祐也 田中孝典
撮影監督:荒井栄児
編集:石井 知
音楽:梶浦由記
音楽制作:FlyingDog
音響監督:中澤一登
音響監督補佐:鐘江 徹
音響効果:倉橋裕宗
録音調整:星野賢爾
プロデューサー:黒木 類
制作:Production I.G
オープニングテーマ:「海と真珠」JUNNA
エンディングテーマ:「サイハテ」鈴木みのり
【キャスト】
フェナ・ハウトマン:瀬戸麻沙美
雪丸:鈴木崚汰
紫檀:櫻井孝宏
花梨:悠木 碧
槐:佐藤 元
楓:逢坂良太
椿:大須賀純
真樺:田中進太郎
サルマン:村治 学
オットー:平田広明
グレイス・オマリー:深見梨加
チン・シー:金田 愛
シャーロッテ・ベリー:薮内満里奈
メアリ・リード:七瀬彩夏
ハンナ・スネル:河野 ひより
アルテミシア:茉莉邑薫
アン・ボニー:森谷彩子
アルビダ:日野まり
アベル・ブルーフィールド:森川智之
コーディ:八重畑由希音
フランツ・ハウトマン:中谷一博
©Kazuto Nakazawa / Production I.G
関連リンク
TVアニメ『海賊王女』公式サイト
https://fena-pirate-princess.com/





















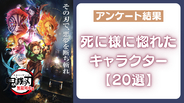






![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)








