浸透し始めたヘルスケアアプリ
60代の約5人に1人がヘルスケアアプリを利用
スマートフォンの普及に伴い、世代を問わずアプリを利用する機会が増加しています。ゲームなどの娯楽だけなく、日常生活に役立つアプリもあり、特にヘルスケアアプリは若者世代から高齢者に至るまで浸透しているようです。
MMD研究所は、18歳~69歳のスマートフォンを所持する男女5,984人を対象に、ダイエットや健康管理などのヘルスケアサービスや、オンライン診療などの医療サービスを利用できるスマートフォンアプリの認知度と利用状況を調査しました。
その結果、「現在利用している」が24.2%、「利用したことはあるが、現在は利用していない」が7.5%に上ることがわかりました。
年代別でみると、「現在利用している」は10代が29.6%、20代が32.1%、30代が26.3%と若い世代の活用が進んでいますが、60代でも19%に達しています。つまり、60代の約5人に1人がヘルスケアアプリを利用していることがわかります。
出典:『ヘルスケアアプリと医療DXに関する調査』(MMD研究所)を基に作成 2022年10月25日更新バイタルサインの測定に関心が高まっている
同調査では、ヘルスケアアプリの存在を知っていて、まだ利用していない人に利用してみたい機能があるか聞いたところ、69.4%があると回答しています。
そのうち、どのような機能を利用してみたいか尋ねた結果、「健康管理(バイタルサイン)」が最も多く47.6%、次に「ダイエット・美容」が30.3%、「メンタル(ストレス)ケア」が24.7%となりました。

ヘルスケアアプリの多くは、1日の歩数などを記録したり、体重や内臓脂肪などの数値の変化をスマートフォン上で確認できるというメリットがあります。
こうしたニーズに応えるアプリが大手メーカーから続々と登場しており、関心が高まっているといえるでしょう。
ヘルスケアアプリだけでは健康管理ができない!?
重要な数値を測定できない
一方、ヘルスケアアプリだけでは健康管理において不十分だという指摘もあります。
その理由として挙げられるのが、要介護の原因となる疾患や病気を測定するのに必要な数値を記録できないからです。
厚生労働省の調査によると、要介護になる原因の第一位が認知症、第2位が脳卒中、第3位が高齢による衰弱となっています。
なかでも脳卒中は動脈硬化から生じるとされ、動脈硬化を進行させる主な要因は、高血圧や糖尿病、脂質異常症などです。そのため、60代以上が健康管理のために必要なのは、血圧や血糖値などのコントロールが重要になります。
ヘルスケアアプリでは歩行数や体重、BMI、体脂肪などを管理することはできますが、血圧や血糖値まで入力して管理できるわけではありません。重要な数値をコントロールするためには、機能が不十分だとされているのです。
国が推進するデータヘルス計画
民間でのヘルスケアアプリが浸透する一方、より高機能でシニア世代の健康管理に最適なのが、マイナンバーポータルなどによる健康管理です。
実はマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、医療機関で受けた健康診断などの情報を、スマートフォン上でいつでも閲覧できる機能があるのです。
こうした取り組みは、国が掲げる「データヘルス計画」の一環とされています。例えば、オンライン診療や電子処方箋などもその取り組みに含まれています。
国はマイナンバーを活用して、個人が健康診断の結果などをPCやスマホで閲覧し、医療機関で適切なデータを掲示できるような仕組みの構築を急いでいます。
ただ、この仕組みはマイナンバーカードの普及率に左右されるため、まだ国民全体に浸透するには時間がかかりそうです。
介護施設で広がる新しいサービス
介護施設で取り入れられるヘルスケアアプリ
介護施設では、アプリ活用を推進している例もあります。
神戸では民間のアプリ開発会社が、食事量やバイタル、排せつなど利用者の情報を記録するアプリにお薬手帳の記録も連携させるなど、介護施設での活用を狙った開発が進められています。
介護現場では血圧などの数値も記録することが多いので、民間の開発したアプリとの連携で重要な健康データを管理できるのです。
また、大手介護事業者はAppleWatchを活用した健康管理を行う有料老人ホームを神奈川県に開業しています。
入居者全員にAppleWatchを配布し、取得する心拍や心電図、血中酸素ウェルネス、運動量などを計測。そのデータを基に専門家が日常生活において改善できるポイントをアドバイスするといった実証実験を勧めています。
ヘルスケアアプリは、まだ要介護認定を受けていない健康的なシニア世代には不十分でも、介護施設ではすでに導入されているアプリやシステムとの連携を図れば、活用の幅が広がります。
官民一体の開発がカギを握る
先のMMD研究所の調査では、オンライン診療やAI問診などに関心がある人も約5割もいることがわかっています。

また、オンライン診療を受けたり、オンライン健康医療相談をしたことはあるか複数回答で聞いたところ、「オンライン診療を受けたことがある」が26.1%、「オンライン健康医療相談をしたことがある」が17.4%となり、合わせて43.5%に上っています。
このように、ヘルスケアアプリを日頃から活用して、医療や介護に役立てたいと考えている人が多いことがわかります。
国はマイナンバーカードを基にしたデータヘルス計画を進めていますが、マイナンバーカードにはまだ抵抗感を抱く人も少なくありません。
まずはヘルスケアアプリなどの民間サービスを医療機関や介護施設で活用し、その有効性を広めていくことが大切ではないでしょうか。
そのためには、国が推進するデータヘルス計画を民間サービスも含めて考えていく必要があるかもしれません。
介護施設や医療機関で進められている実証実験に基づき、データヘルスの価値を高めていければ、より国民が身近に感じることができるのではないでしょうか。


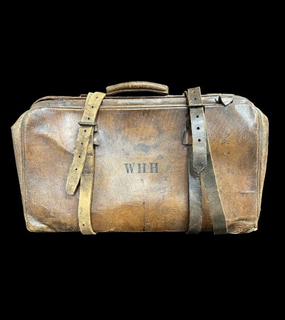





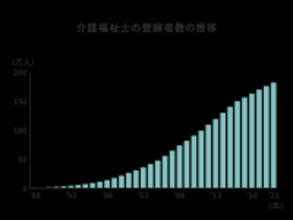



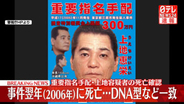

















![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)








