株主になると、投資先の上場会社からさまざまな書類が送られてくる。株主総会の案内や配当金の通知などが一例だ。
「個人株主と上場会社の対話を増やしたい」という想いから誕生
株主パスポートは、自身が投資している複数の銘柄について、株主総会や配当金、株主優待といった情報を一括管理できるアプリ。株主総会で提出された議案に対して、株主が賛成・反対の投票を行う「議決権行使」についても、株主パスポートから各社の議決権行使の専用サイトへ簡単にアクセスできる。
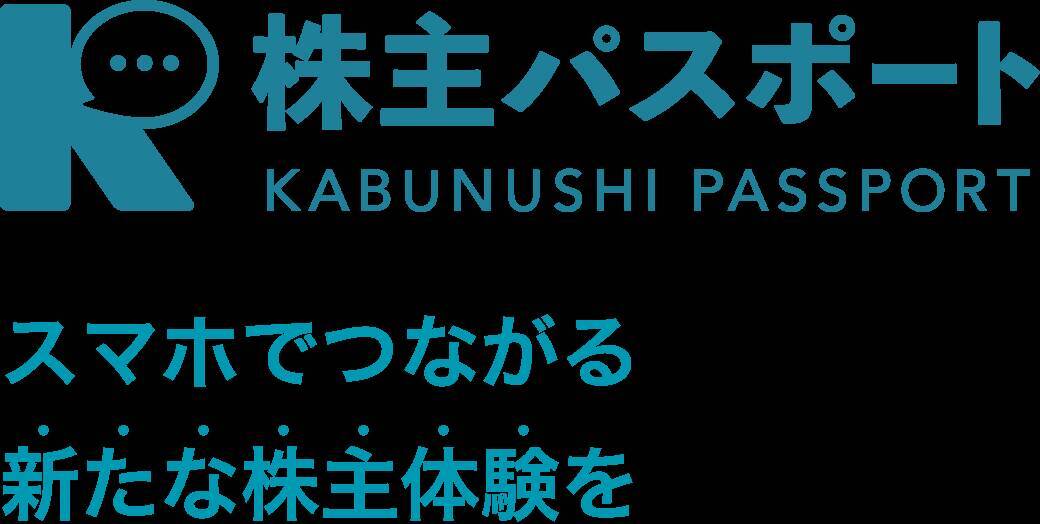
このアプリが誕生した背景には、「個人株主と上場会社の対話を増やしたい」という思いがあったという。大澤氏が詳しく伝える。
「これまで両者の対話は、年1回の株主総会や、紙の通知物によるコミュニケーションなどに限られていました。一方、近年は新しいNISAなどで個人株主の方が増えています。投資先との対話が増えると、株主は経営に参加している実感を持ち、投資を続ける動機へとつながるでしょう。上場会社にとっても、個人の方々とのコミュニケーションを増やし、長期で支えてもらう関係を築くことが大切になっています」

こうした中で、両者の関係をもっと近くし、対話を増やそうとこのアプリが生まれた。
「たとえば、株主総会や配当金のお知らせといった通知物は、それぞれの会社から紙で送られていました。株主の方からすると、一社ごと封筒を開けて書類を確認するのは面倒ですよね。きちんと見ないケースも増えてしまいます。また、紙でのやり取りは環境負荷やコストもかかるでしょう。そこでこれらをデジタル化し、複数の銘柄をまとめて1つのアプリで管理できるようにしました」
ここで説明しておきたいのが、信託銀行の行っている“証券代行業務”について。株式会社に代わって、その会社の株主名簿の管理や、株主向けの通知物の発送、配当金の支払い手続きなどを引き受けている。三井住友信託銀行もこうした業務を行っており、今回はその一部をデジタル化・アプリ化したと言える。
株を売却した理由を尋ねる「売却時アンケート」も実装

株主パスポートでは、ユーザーの氏名や住所、保有している銘柄をアプリに登録すると情報管理が可能になる。登録できる銘柄は、三井住友信託銀行が株主名簿を管理する銘柄のうち、株主パスポート参加企業に限られる。2025年8月1日時点で832社が参加しているという。各社の株主名簿をもとに、アプリ登録者と保有銘柄の情報を照合している。
先述の通り、アプリ内では登録銘柄の情報を見られるほか、議決権行使なども行いやすくなる。
一方、株主パスポートでは「アプリから各社の議決権行使サイトへ直接アクセスできます」と話すのは、このアプリの開発に携わった井田氏。「今まではログインが面倒でやらなかった方も、チャレンジしやすくなるのではないでしょうか」と続ける。

個人株主と上場会社の対話を活発にする機能もある。このアプリでは、上場会社が株主にアンケートを実施できる。開催してほしい株主イベントや、自社に対するイメージ、株主の趣味嗜好など、企業は任意で自由に質問できる。
「さらには『売却時アンケート』という機能も設けています。その名の通り、株を売却した方にその理由を尋ねたり、今後買い戻すとしたらどのような場合かを聞いたりしています。株主ではなくなる方に対して、これまで上場会社はコミュニケーションを取る術が少なかったでしょう。新しい“対話”を生み出す取り組みです」(大澤氏)
通常4割の議決権行使が、このアプリでは9割超

このアプリは、株式投資を行っている人の”声“を聞きながら開発していったという。今まで紙だった通知物をデジタルに変えるアイデアが生まれたのも、そこで聞かれた本音がきっかけだった。「一社ごと封筒で書類が送られてくるため、『開けるのが面倒』というお話や『中身をよく見ていない』といった声が聞かれました」(井田氏)
そうした課題をもとにアプリを設計し、開発中も投資家に使ってもらいながら、機能や画面操作を改善していったという。
一方で、セキュリティの担保も当然重要だ。そこでこのアプリでは、マイナンバーカードを用いた会員登録を可能とし、なりすましの防止につなげているとのこと。セキュリティと使いやすさ、その最適なバランスを模索したという。
アプリを継続的に使用してもらう工夫も取り入れた。というのも、株主総会などは1年のうち特定の時期にしか行われない。そのシーズン以外はアプリに触れない状況が発生すると、仮に上場会社がアプリ伝いで情報を発信しても、見てもらえなくなる。継続的な対話は生まれない。「そこでアプリにポイント機能を設け、企業の施策などに参加するとポイントを得られるようにしました。たまったポイントは物品と交換ができます」(大澤氏)。

企業と個人株主の新しい関係性を築く
アプリは2025年4月15日にローンチし、2カ月弱で18万ダウンロードを突破(6月9日時点)。さらに見逃せないのは、アプリユーザーが議決権行使を積極的に行っている点だ。「通常、個人株主の議決権行使は4割ほどですが、このアプリでは9割を超えています」と大澤氏。アプリから簡単に専用サイトまで行ける点が奏功しているのだろう。
株式投資では、どうしても値上がり益や配当、株主優待などに目が行きがちだ。しかし、議決権行使などを通じて「経営に参加できること」も忘れてはならない。個人株主が積極的に意見を伝えることで、上場会社もその考えを経営に活かせる。また、個人株主が投資先の企業を適切に見守ることで、経営のガバナンスにも好影響をもたらすだろう。
「個人株主と上場会社の強固なネットワークができると、日本市場の健全な発展につながると思います。このアプリが、そうした点に寄与できればうれしいですね」(大澤氏)

個人株主が増える中で、上場会社との対話をいかに生み出していくか。そこでデジタルを活用し、両者の距離を近づけていく。

(取材・文/有井太郎 撮影/森カズシゲ)
※記事の内容は2025年8月現在の情報です



















![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
