2009年の自主制作盤でのデビュー以降、ポストパンク、ローファイ、ムード音楽、エキゾ、モンドなど、様々な養素を織り交ぜた独自の表現をブラッシュアップさせてきた彼だが、近年は先端的なダンスミュージックの要素も大胆に取り入れ、自身が手掛けるVJを交えたライブ活動とあわせて、クラブミュージックシーンでも高い評価を得ることとなった。
今年7月にリリースされた最新アルバム『The Secret Life of VIDEOTAPEMUSIC』は、横山剣(クレイジーケンバンド)、高城晶平(cero)、折坂悠太、ロボ宙、mmm、カベヤシュウト(odd eyes)、キム・ナウン(ex. Parasol/韓国)、Mellow Fellow(フィリピン)、周穆(Murky Ghost/台湾)といった多彩かつ豪華なゲストボーカル陣を招いた初の全編〈歌モノ〉アルバムとなっている。アーティスト名に象徴的なように、匿名的かつコンセプチュアルな美意識に貫かれてきた彼の音楽だが、この新作においてはそれぞれの楽曲が個性豊かなフィジカリティを纏わせることで、ポップスとしての圧倒的強度を獲得することとなった。そのコンセプト性ゆえ、時にヴェイパーウェイブとも関連付けて語られる彼の音楽だが、ここから聴こえてくるのは、自分の耳と足を駆使し、今世界中の様々な場所で生まれつつある音楽と積極的に触れ合おうとするヒューマニティに溢れる姿だ。よりダンスオリエンテッドに、一方でそのサウンドは更に精緻かつダイナミックに……集大成的且つこれからの展開を予見させるそんな作品のリリースツアーを盛況に終えたばかりの彼に、普段から足繁く通っているという経堂の住宅街に佇む喫茶店「ドエル」にて話を訊いた。
―子供の頃はどんなものに興味を持っていたんでしょうか?
VIDEOTAPEMUSIC(以下V):実は子供の頃音楽が一番苦手な分野だったんです。絵画や映像のほうが好きでした。でも、ラジオは好きでよく聴いていましたね。特定の番組をちゃんと聴くとかじゃなくて、どこからともなく混線して聴こえてくる外国語の放送とか……。思えば、ガジェット的なものにロマンを感じたり、未知のものへ興味を抱くという今の自分の音楽に通じる要素もその頃に遡るのかもしれません。
―VHSという媒体に対して特別な興味を持つようになったのは?
V:昔の特撮モノや怪獣モノが好きだったこともあって、そういった作品のVHSを近所のレンタルビデオ屋で借りて観ていたので、はじめは当たり前のものとして生活の中にあった感じですね。メディアとしての魅力を意識するようになったのは2000年代前半、DVDに移行していく中でVHSがどんどんなくなっていく頃。
―色々な音楽へ関心を持つようになったのもその頃?
V:そうですね。武蔵野美術大学に入ったころから興味が広がっていきました。高校時代にも一応バンドをやったりしていたんですが、それはあくまで単純な楽しみのためだけで、大学で周りの友達や授業を通していろんな音楽について知ていくうちに、自分の中にそれまであった映像への興味と融合したものを作ってみようと思ったんです。その頃は、ナム・ジュン・パイクのビデオアート作品やアンディ・ウォーホルの映像作品、宇川直宏さんの仕事にもとても刺激を受けました。レコードじゃなくて、VHSをサンプリングソースにしようと思ったのは、単にVHSの方が自分にとって身近だったからです(笑)。
―その頃よく聴いていた音楽は?
V:ボアダムズやバッファロー・ドーター、コーネリアスなどの日本のオルタナティブな音楽や、海外のいわゆるローファイ、ポスト・パンク系、特にフライング・リザーズには影響を受けました。ずっと音楽教育からドロップアウトしてきた身だったので、「身近な素材でこうやって自由に音楽を作っていいんだ!」という衝撃がありました。VHSからサンプリングするという制作法にはそういう考え方も反映されていると思います。
―VIDEOTAPEMUSICの音楽の重要な要素として、マーティン・デニーやレス・バクスターなどに通じるような、いわゆる「エキゾ」というものがあると思うのですが、そういったものを取り入れようと思ったのは?
V:子供の頃から怪獣映画に出てくる南国の風景とか巨大な昆虫とか、自分の外部にある未知の世界へ興味を持っていたので、そういう感覚が後に聴いたエキゾ的なものと自然に結びついた感じですね。そもそも写真や映像などの記録メディア自体が、自分の環境の外部にあるものを記録して体験する感覚=エキゾ性や「観光」ということを成り立ちとしているということも知って。そのあたりも自分の表現にしっくりきたのかもしれません。
―なるほど。
V:移動と記録メディアの歴史について論じられている、美術史家の伊藤俊治さんによる『ジオラマ論』という本があるんですが、その影響は大きいですね。そこに書かれていることを自分なりに音楽に置き換えることで、エキゾチック・ミュージックの要素を自覚的に取り入れていくようになった感じです。
―近年ではダンスミュージック的な要素も積極的に取り入れていますね。
V:以前は自分の音楽を体を動かしながら聴くものだとは一切思ってなかったんですが、リリースを重ねる中でクラブでのイベントに呼んでもらうことが増えてきて、当初は必要に迫られて取り入れてきた感じなんです(笑)。それまで踊りながら音楽を聴くことの快感もあまりよくわかっていなかったんですが、友だちに連れて行ってもらったりしているうちに徐々にその魅力に惹かれていって。そしてそこで気づいたのが、それまでのあくまでただ見る側としてだけあった「エキゾ」という視点に、新たにダンスミュージック性が加わることで、自分の肉体を通して別の感覚が開けていく、ということだったんです。観光的態度でありながら、一方で身体の参加も伴う感覚……。段々とこれは表現として可能性があるなと思い始めて、積極的にそういった要素を取り入れたのが2015年のアルバム『世界各国の夜』ですね。
―最新作『The Secret Life of VIDEOTAPEMUSIC』は初の全編ゲストボーカル入りのアルバムです。
V:僕自身からは出てこない要素を取り入れてみたかったというのが大きいですね。一方で、こういうと参加してくれた皆さんへ失礼になってしまうんですが(苦笑)、今までサンプリングで作ってきた感覚ともそう大きくは違わない感覚なんです。
―歌モノとなったことでポップスとしての強度が全体的にぐんと上がった気がする一方、これまでの作品にあったエキゾ的要素も更にアップデートされているように感じました。今エキゾ的なものって、外部から眺めるだけの観光的な姿勢やテンプレート的な文化解釈など、現在のPC的視点から問題を指摘されることもあると思うんです。そういったことについてはどう思いますか?
V:そういった問題意識は常あります。今回生身のミュージシャン達と制作したという部分もまさにそこと繋がっていると思っています。これまで台湾や韓国の風景をエキゾチシズムの対象としてしか考えられていなかったんだとしたら、今度は実際にその国々のミュージシャンと一緒に作ることで、様々なディスカッションが生まれてくる。ただ観光的な視点を端から排除するだけでなく、ちゃんと対話をして折衷するところを探っていく作業というか。なおかつそれを、外から見るだけじゃなく、自分が実際に各地に足を運びながら考えていく。そのことで自分が親しんできたエキゾ的なものを現在の倫理観にあわせてアップデートできないかというのを日々考えています。
―ライブパフォーマンスを行う上でも、「現場に足を運ぶ」という意識がある?
V:はい。ライブを行うとき、自分自身の身体を移動して現場に入っていくというのは、旧来のエキゾ的なものから一歩先に行くための重要なポイントだと思っています。
―話題を変えて、ここ最近ハマっている音楽があれば教えて下さい。
V:最近は自分のツアーで疲れ気味だったこともあって……(苦笑)、気分を上げてくれるよう音楽ばかり聴いてます。BLACKPINKなどのK-POPものとか、強くてカッコいい感じの女の子の音楽をよく聴いてますね。
―欧米のチャートものは?
V:自然に耳に入ってくるのを聴く程度であんまり意識的に聴かないかも。むしろ日本にあまり情報が入ってこない国のヒットチャートものを積極的に聴いてますね。トルコや、インド、アフリカの各国とか……。今はそういったものを聴ける手段も多いですし。
―お勧めがあれば教えて下さい。
V:特にロシアのポップスに興味があって。地理的に日本にも近くてあんなに大きな国なのに、ほとんどリアルタイムのエンタメ系情報が入ってこないから、余計に興味を駆られて。
―最後の質問です。今後のVIDEOTAPEMUSICの活動はどんなふうに展開していくと思いますか?
V:これまでも自分の興味に素直に沿って音楽を作ってきたから、今後もその時々の好奇心に応じた作り方をしていくんだろうなと思っています。実は来年のオリンピックの時期、完全に東京から離れようかなとも考えています。今まで東京で音楽を作り続けて来た一方で、別の土地でも滞在制作みたいなことをやりたいと思っていたんですが、むしろいいチャンスかなって。その土地土地で出会った人からもらうVHSだけを使って、その土地のことを織り交ぜた音楽をつくったり。元々僕の音楽はフォーマット的な縛りの中で出来てきたものでもあるから、制約を自分で課すことで作家としてかえって燃えるというのがありますね。

「Scramble Fes 2019 supported by Rolling Stone Japan」
2019年11月2日(土)東京・渋谷TSUTAYA O-EAST
時間:OPEN 14:30 / START 15:30 / CLOSE 21:30 ※予定
出演:iri・eill・TENDRE・クボタカイ・VIDEOTAPEMUSIC・betcover!!
※2ステージ制
チケット前売り:3800円(税込・別途ドリンク代)
各プレイガイド
イープラス:https://eplus.jp/scramblefes2019/
LINEチケット:https://ticket.line.me/events/3960/
ローソン:https://l-tike.com/scramblefes2019/
ぴあ:https://w.pia.jp/t/scramblefes2019/
イベント公式ホームページ:http://tsutaya.jp/scramblefes2019/

『The Secret Life of VIDEOTAPEMUSIC』
KAKUBARHYTHM
発売中














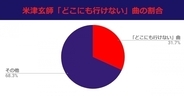




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








