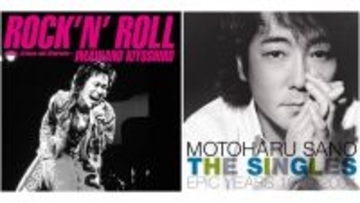田家秀樹(以下、田家):こんばんは。FM COCOLO「J-POP LEGEND FORUM」案内人、田家秀樹です。J-POPの歴史の中のさまざまな伝説を紐解いていこうという60分です。伝説のアーティスト、伝説のアルバム、伝説のライブ、そして伝説のムーブメント。1つのテーマ、1人のアーティストを、1ヵ月に渡って特集しようという、最近のラジオの中では贅沢な時間の使い方をしております。
2020年9月の特集は「佐野元春」。ポップミュージックというのは時代を映す鏡ですね。世の中の動向、若者たちの生活、テクノロジーを含む環境の変化。いろいろなものを反映します。1980年代の前半に佐野さんの「SOMEDAY」が愛唱歌だと言っていた作家の村上龍さんは、ポップの波打ち際という言葉を使っておりました。
今月は、10月7日にリリースされる佐野元春さんの『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』と、『THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020』を中心に、改めてそんなお話をお訊きできたらという1ヶ月です。ファンの方からしたらおさらい編でしょう。
田家:というわけで、デビュー40周年の佐野元春さんです。こんばんは。
佐野元春(以下、佐野):こんばんは。よろしくお願いします。
田家:40周年ということで日々忙しそうですね。
佐野:そうですね。ただちょっと、肩透かしを喰らったようなアニバーサリーイヤーですね。
田家:改めて40周年を辿ってみたいと思っているのですが、実は先日、東京のFM局の開局記念番組の生放送に呼ばれて「ポップスとラジオ」というテーマでお話していたんです。その中で佐野さんはラジオのディレクターだったということに触れたら、Twitterでリアクションがかなりあったんですよ。まずはラジオのディレクターをやっていて、そこからプロのミュージシャンになったという時のことについてお訊かせください。
佐野:自分のことを舞い上がらせるような日本語のポップロック音楽がなかった。だったら自分で作ろうということでやってみました。
田家:その時にはどれくらいの覚悟が必要だったんですか?
佐野:米国の知人のDJが「今曲を書いてるんだったら、今唄った方がいいよ」っていうアドバイスをしてくれて。それもそうだなって思った。帰国してからレーベルと契約しました。
田家:佐野さんが、アメリカで出会ったミュージシャンが「西海岸でダメで東海岸でやり直すんだ」と言っていた話を聞いて、人生はやり直せるんだっていうことに気づかされて日本に帰ってこられたという話もありました。
佐野:当時は十分若かった。とにかくやってみたいことはなんでもやるぞと思っていた。
田家:デビューアルバム『BACK TO THE STREET』というタイトルは、色々なレコード会社に持ち込んだりしている中でもうあったんですか?
佐野:そうだね。何か気の利いたタイトルを、と思い『BACK TO THE STREET』。テーマでもあるし、メッセージでもあった。
田家:曲はもう全部揃っていて、デビューアルバムを飾るにふさわしい自信があった?
佐野:楽しんでもらえるかなっていう自信はあった。ライブでは全国どこの会場も満員でいい感じだったから。
田家:そのデビューアルバムの中にこういう曲があったのも新たな発見ではないでしょうか。デビュー・アルバム『BACK TO THE STREET』から「情けない週末」。
田家:この曲がデビューアルバムに入っていたということで驚かれる方もいらっしゃるんだと思うんです。しかも15、16歳の頃にお書きになったと。
佐野:そうそう。15歳頃の頃にはもう曲を書き始めていました。手本がなかったので、欧米のソングライターの曲を聴いて学んだ。
田家:この「情けない週末」は、言葉の並べ方とか情景の描写という点で、それまでの日本の歌にはなかったんではないかと僕らは思っているんです。
佐野:そうかもしれないね。あの頃、シティポップと呼ばれている音楽があった。ただ、そのシティポップと呼ばれる音楽はたいてい外から眺めた街の歌だった。僕は東京育ちですから、内側から眺めた街の歌を作りたかった。都会的な音楽じゃなくて、都会そのものの音楽。そういう想いで作ったのが「情けない週末」ですね。
田家:それまでの日本語の歌は説明的になってしまう歌詞が多かったんですけど、この曲は説明しないで単語で情景を語っています。
佐野:カットバックだね。カットバックは、映画ではよく使われる。いくつかの違った情景をコラージュして、見る側にその意味を感じてもらうという手法。歌謡曲の世界にも昔からあった。山口洋子作詞、平尾昌晃作曲の「よこはま・たそがれ」だ。
田家:佐野元春さんの話に作詞家の山口洋子さんが書いた曲が出てくるとはなかなか思いませんよね。
佐野:何からでも影響されてる。
田家:その10代の時期に「情けない週末」の歌詞にある"という うすのろ"というのは、どういう感じ方だったんですか?
佐野:僕自身の実生活から出てきた言葉ではない。作家的な自分がイメージした言葉だ。
田家:でも今も10代の少年少女が恋に落ちてこの人と暮らしたいって思う時に、必ず足枷になるのは生活というものなわけで。この歌のリアリティは、今の若者にとっても普遍的なものであると思うんですよね。
佐野:そうだったらいいな。
田家:改めてこの曲で2つのことについてお聴きしたいと思っているのですが、2つの言葉。"ガラスのジェネレーション"でイメージしたものと、"さよならレヴォリューション"という言葉で言おうとしたものについて伺いたいのですが。
佐野:意味よりも最初にライミングだよね。当時はライミングは一般的じゃなかった。「アンジェリーナ」の"今晩誰かの車が来るまで闇にくるまっているだけ"とか、"ガラスのジェネレーション、さよならレヴォリューション"とか。意味よりも響きに注目した。
田家:上の世代と僕らは違うという世代観は、子供の頃からおありになったんですか?
佐野:上の世代が作った音楽や本を読んで、共感したり反発しながら育った。そこから世代観の違いを意識するようになりました。
田家:「さよならレヴォリューション」というのは、上の世代に向けてという大きな意味があったわけでもなく?
佐野:それもあったかもね。これからは自分たちの時代だっていう、粋がりもあったと思う。
田家:あなたたちが口にしたレヴォリューションってのは形にならなかったじゃないかっていうこともあったでしょうし(笑)。
佐野:そうだね、レヴォリューションは外に求めてる物じゃなくて、内側に求めるものじゃないかって言いたかった。
田家:なるほど。ロックミュージックの成長っていうのは当時からテーマとしておありだったんですか?
佐野:成長というのはロックンロール音楽の主要なテーマの一つだ。
田家:でもこの「ガラスのジェネレーション」を歌わない時期もありましたよね。
佐野:自分が大人になった時に、ちょっと歌いづらいなっていう時期はあったよ。
田家:今はそう思っていらっしゃらない?
佐野:今は客観的に見られる。80年代の誰か他人が作ったパワーポップを聴いてる感じ。
田家:では、この曲はどうなんでしょう? 1982年5月発売になった3枚目のアルバム『SOMEDAY』のタイトル曲「SOMEDAY」。
田家:この曲はいわゆるウォール・オブ・サウンドという上の世代の人たちが作った音の作り方でもあるわけです。大滝詠一さんもこのアルバムの前後に登場してくるわけですね。
佐野:当時、僕の敬愛する大滝詠一さんは、フィル・スペクターに影響されたオーケストレイテッドなポップサウンドを作っていた。僕も大好きだったんです。まだ物心つく前から、両親が家の中でレコードをかけていた。特に覚えているのはザ・ロネッツの「ビー・マイ・ベイビー」。街の雑踏を感じるサウンドだった。「SOMEDAY」を作る時に参考にしたのがウォール・オブ・サウンドでした。
田家:大滝詠一さんから学んだものってなんだと思います?
佐野:レコーディングの方法。ある時、伊藤銀次と一緒に大滝詠一さんのレコーディング現場を見る機会があった。その時大滝さんがスタジオで展開していたレコーディング方法にピンときた。それを応用して「SOMEDAY」のレコーディングを始めた。
田家:冒頭でも話しましたけど、作家の村上龍さんが当時「SOMEDAYを歌える作家は俺くらいだ」って仰っていたんですよ。「SOMEDAY」の中にあるイノセンスというのは当時どういう風に意識されていたんでしょう?
佐野:どうだろう。ソングライターとして光栄なことは、その曲を聴いた時に「これは自分の曲だ」って思ってもらうことですよね。尊敬するソングライター、小田和正さんも言っていた。「サムデイ。この曲を聴いて俺の歌だと思った」。それを聴いて嬉しかった。
田家:GLAYのTAKUROさんもそう仰ってましたからね。どんな風に伝わってるんだろうっていう風にはお考えにならない?
佐野:ソングライティングすることに夢中だった。とにかくいい曲を書こうと一生懸命だった。
田家:それが一番ピュアなものを表現したということになったのかもしれませんね。
田家:1984年5月発売、4枚目のアルバム『VISITORS』からのシングル・カット「コンプリケイション・シェイクダウン」でした。佐野さんの40年間の軌跡には、潔い決断とか冒険的で果敢な挑戦など色々な場面があると思っているのですが、最たるもの、そして最初のものが1983年から1984年にかけてのニューヨーク行き。海外レコーディングは1970年代終わりから1980年代にかけて広まってきたのですが、生活体験として向こうに行って、そこでアルバムを作り上げたというケースはなかったと思いますね。
佐野:そうかもしれない。でも自分にとっては国内でレコーディングすることと国外でレコーディングすることに特に違いはなかったんですよね。ただ、自分が求めているビジョンがどこにあるのか? それが大事だった。
田家:ニューヨークに行った時には、レコーディングしようというところまでビジョンがあったんですか?
佐野:ありました。
田家:どんなものになるかというところまでは見えていなかった?
佐野:具体的には見えていなかった。
田家:当時のニューヨークではHIPHOPムーブメントというのが始まっているわけで、ストリートカルチャーが燃え盛り始めていました。そこに入っていくにあたって、自分を変えないといけないなと思ったことってあったんですか?
佐野:自分の出番だなと思った。HIPHOPやラップの様式というのは、メロディよりも言語傾向の強いポップ表現ですから。それ得意だよっていう思いはあった。で、日本語でラップやったら友達が面白がってくれた。「日本語のラップは世界で初めてだよ」って言われて、そうだなって思った。束の間の自由をビートに任せて、転がり続けなっていう感じだ。
田家:アルバムの中の「WILD ON THE STREET」、シングルのカップリングにもなりましたけど、その中に俺を壊してくれっていうフレーズがあったりして、自分を解体しなければならない場面もあったのかなと思ったりもしていたのですが。
佐野:若い時は細胞分裂が激しいからね。自分を乗り越えて新しい未来へ、という感じだったじゃないかなと思います。
田家:そういうドキュメンタリーのようなアルバムっていう風に思って差し支えないですか?
佐野:そうだね、『VISITORS』はニューヨーク生活の中から生まれたドキュメンタリーと言える。
田家:そのアルバムの中からこの曲をお聴きください。4枚目のアルバム『VISITORS』から、「ニュー・エイジ」。
田家:ニューヨーク生活は1983年~1984年なわけですから、デジタルなテクノロジーも今とは比較にならないほど素朴だったわけでしょう?
佐野:そうだったね。「ニュー・エイジ」は未来を思って書いた曲でした。でも、その未来はバラ色な世界ではなく、どちらかというとディストピア的な世界観が僕の中にあった。闇を切り裂いて船を漕ぎ出す、といったイメージ。当時1983年は、社会学者がデジタル・ネットワーキングのことを語り出していた。今でいうWorld WIde Web。僕もニューヨークで暮らしながら歴史が変わっていくのを直感していた。それを曲にしたのが「ニュー・エイジ」です。
田家:新しい文化が続々と誕生している中で、ポジティブな気持ちなだけではなく、そこに流れるディストピア的なものも受け止めながらこの曲に繋がっていったということなんですね。そして1984年6月に帰国されて、アルバムチャートで1位になったんですが、帰国してから精神的に不安定だった時期もあるっていう話も残っていますね。
佐野:逆カルチャーショックだよね(笑)。日本の景色が少し自分の中では奇妙に見えることがあった。特にTVコマーシャル。なんでこんなに白人女性が出てるんだろうって、そういう違和感もあって少し頭が狂っちゃった。
田家:それが形になっていったのが次のアルバムなのかなと思います。
Kickin Asphalt / Duane Eddy
田家:FM COCOLO「J-POP LEGEND FORUM」佐野元春40周年Part1。今週は1980年代前半を辿ってみました。今月はいつもの後テーマ曲、竹内まりやさんの「静かな伝説(レジェンド)」はお休みにして、Duane Eddyの「Kickin Asphalt」が流れています。
佐野:いやあ、嬉しいね。トゥワンギー・ギターの名手だよね。僕のやってたラジオ番組「元春レイディオ・ショー」でも、Duane Eddyをかけてました。
田家:「元春レイディオ・ショー」は、FM COCOLOでも今年7月から9月までレギュラーで流れているんですが、そこでもこの曲が後テーマなんですか?
佐野: いや、Booker T. & the M.G.sの「Time Is Tight」。番組の終わりにはいつもこの曲をかけていた。
田家:「元春レイディオ・ショー」ではご自身の曲をかけたり、40年間を振り返ったり、アルバムの話をされたりするんですか?
佐野:そうそう。DJの野村雅夫さんが色々と話を訊いてくれるはずです。
田家:そこでも野村さんがお訊きになるとは思うんですが、今回のベスト盤にはシングルカットされていない曲もあるわけですよね。今日話した時期の話で言うと、アルバム『SOMEDAY』の中から「Rock & Roll Night」が収録されているわけで。
佐野:そうだね。今までベスト盤が何枚か出てるんだけど、「Rock & Roll Night」はどれにも収録されていなかった。
田家:僕も今日この曲をご紹介できないかなと思ったんですけど、なにせ8分32秒あるので、折角のインタビューの貴重な時間がもったいないかなとも思って(笑)。"友達のひとりは遠くサンフランシスコで仕事をみつけた 友達のひとりは手紙もなく今 行方がわからなくて 友達のひとりは幸せなウェディング 一児の父親さ そして同じ幻を見つめていた"このフレーズは、当時も今も好きですね。
佐野:ありがとう。この曲を聴いてくれた人が、自分なりのストーリーを紡いでくれたら嬉しいです。
田家:その頃にこの曲を聴いた友達が今もコンサートに足を運んでこられているわけですもんね。そういうこの頃の友達について、今どんな風に思ってらっしゃいますか?
佐野:亡くなった人もいる。生き抜いた人もいる。僕は両者の思いをしっかり抱えて唄っていきたいと思っています。
田家:THE COYOTE BANDの歌にはそういう曲もあります。来週もよろしくお願いします。
佐野:よろしくお願いします。
MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004
https://www.110107.com/s/oto/page/sano_collection?ima=0205
THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020
https://www.moto.co.jp/EssentialTracks2005-2020/
<INFORMATION>
田家秀樹
1946年、千葉県船橋市生まれ。中央大法学部政治学科卒。1969年、タウン誌のはしりとなった「新宿プレイマップ」創刊編集者を皮切りに、「セイ!ヤング」などの放送作家、若者雑誌編集長を経て音楽評論家、ノンフィクション作家、放送作家、音楽番組パーソリナリテイとして活躍中。
https://takehideki.jimdo.com
https://takehideki.exblog.jp
「J-POP LEGEND FORUM」
月 21:00-22:00
音楽評論家・田家秀樹が日本の音楽の礎となったアーティストに毎月1組ずつスポットを当て、本人や当時の関係者から深く掘り下げた話を引き出す1時間。
https://cocolo.jp/service/homepage/index/1210
OFFICIAL WEBSITE : https://cocolo.jp/
OFFICIAL Twitter :@fmcocolo765
OFFICIAL Facebook : @FMCOCOLO
radikoなら、パソコン・スマートフォンでFM COCOLOが無料でクリアに聴けます!
→cocolo.jp/i/radiko