
地方銀行が南都銀行のほかにない奈良県で、大和信用金庫(やましん)、奈良中央信用金庫(ちゅうしん)、奈良信用金庫(ならしん)の「奈良3信金」は地域金融として欠かせない存在だ。
3信金の業容は下表のとおりで、大和信用金庫が最も規模が大きいが、「圧倒的に差がある」というものでははない。

新法制定に伴い信用組合から信用金庫へ
まず、それぞれの沿革から見ていこう。
大和信用金庫は1948年7月に桜井町信用組合として創立した。以後、3年は金融関連の新法制定に伴い、組織改変を進めてきた。1950年2月には中小企業等協同組合法により桜井信用組合に改組。1951年10月には信用金庫法にもとづいて大和信用金庫に改組した。
M&Aとしては、1975年11月に生駒信用組合と合併している。その後はM&Aはなく、着実に預金量・貸金料を増やしてきた。
奈良中央信用金庫は1948年8月、田原本町信用組合として創立した。1953年4月には信用金庫法にもとづいて田原本信用金庫に改組。信組から信金へ、という流れは大和信用金庫と同様で、1978年11月に名称を奈良中央信用金庫に変更した。
創立から今日までM&Aはない。
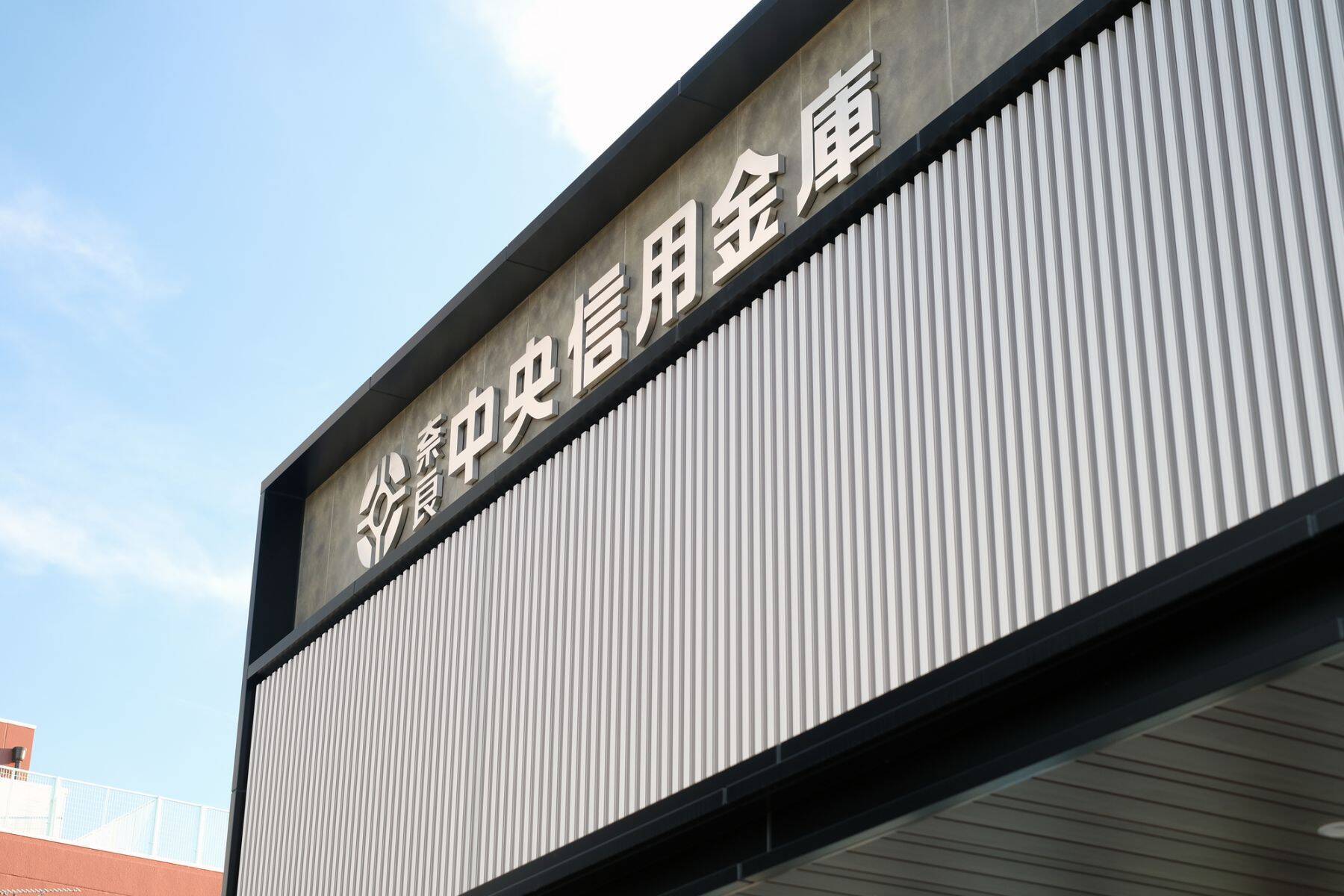
信金M&Aで誕生した奈良信用金庫
大和信金や奈良中央信金とは異なり、奈良信用金庫はM&Aにより誕生した信金である。1951年10月、郡山信用金庫と奈良信用金庫(旧)が合併して誕生した。
両信金のうち郡山信用金庫は1928年9月、有限責任郡山町信用組合として設立した。1934年3月には保証責任郡山町信用組合に改組、1938年8月には郡山町信用販売購買利用組合に改称した。
有限責任は出資額を上限として責任を負うことだが、保証責任は出資額を超えて会社の債務を個人で弁済する責任を負う場合がある、ということ。信用金庫法の制定前に信組であった時代を持つ信金では、その時代に保証責任という態勢で事業を営んでいたところも多い。
ところが郡山町信用販売購買利用組合は1944年3月、農業団体法の制定に伴いいったん解散し、翌4月には郡山町農業会という組織を設立した。農業会とは1943年の農業団体法にもとづいて設立された農業に関する統制機関のこと。第二次大戦中の食糧増産や農業統制を目的として、農地や生産物の管理、配給、労働力の動員などを行ってきた。なお、農業会の機能としては現在、J Aや各自治体の農業委員会に引き継がれている。
郡山町農業会は1948年8月に信用部門を分離し、有限責任郡山町信用組合(2代)を設立した。そして1950年4月、中小企業等協同組合法にもとづき郡山町信用組合に改組、1951年10月に信用金庫法にもとづき郡山信用金庫となった。
合併前の奈良市信用金庫は1934年6月、有限責任奈良市信用組合として創立した。1943年4月には市街地信用組合法にもとづき奈良市信用組合に改組、1950年4月には中小企業等協同組合法にもとづく信用組合に改組。

産業組合法から信用金庫法への変遷
大和信用金庫と奈良中央信用金庫はもともと産業組合法にもとづく組織だった。対して奈良信用金庫は、市街地信用組合法や中小企業等協同組合法にもとづく組織だった。ここで、産業組合法から信用金庫法への変遷について触れておこう。
明治維新後に資本の集中が激化し、農民や中小商工業者などへの金融支援を目的に、1900年(明治33年)に産業組合法が制定され、同法による信用組合が誕生した。ところが、都市部の中小商工業者にとっては制約が多いため、1917年(大正6年)に産業組合法が一部改正され市街地信用組合が生まれた。その後1943年に市街地信用組合法が制定された。
終戦後の経済民主化の中で、1949年には中小企業等協同組合法が制定されたが、協同組織による金融機関の設立を望む声が高くなり、1951年6月に信用金庫法が施行され、信用金庫が誕生した(全国信用金庫協会ホームページ要約)。
県北の盆地で共同態勢をとる
南都銀行の記事でも触れたが、奈良県の県庁所在地・奈良市は県の北端に位置し、県中央部には面積672 k㎡以上を誇る日本一広い村の十津川村がある。奈良県の中部・南部は険しい山に囲まれ人口も多くはなく、いわば銀行の“空白地帯”だ。3信金も県北の奈良盆地で、それぞれ地域に密着した営業を展開している。県内有力信金ながら店舗数が多くはないことは、このような地政も影響しているのだろう。
ちなみに、県内企業のメインバンクの状況を見ると、唯一の県内地銀である南都銀行が1位(7812社、県内シェア59.97%)で、2位は大和信用金庫(799社、同6.13%)、奈良中央信用金庫は5位(717社、同5.50%)、奈良信用金庫は7位(353社、同2.71%)だ(東京商工リサーチ調べ、2023年)。「3信金は、アフターコロナの環境下で地域貢献や企業支援の姿勢を明確にし、微増ながらシェアを伸ばした」とされる。
帝国データバンクの2024年メインバンク調査でも、南都銀行が8071社、60.23%でシェアトップ。2 位は大和信金で932社、シェア6.96%、3位は奈良中央信金で912社、シェア6.81%、奈良信金は6位で398社、シェア2.97%となっている。
南都銀行の牙城を切り崩すとまではいかないが、いずれの調査でも企業支援に注力した3信金がシェアを伸ばしている。このことは、地域の信金にとって明るいニュースだ。
なお、この3信金では2020年4月、磁気ストライプを高抗磁力化した通帳『HI-CO 通帳』の取扱いを共同で始めた。「近年、通帳の磁気ストライプはスマートフォンなど電子機器等の磁力の影響を受けデータが破壊され、読み取れない事象が増加していたが、こうした事象が軽減される」とする。
また、この3信金では、それぞれのATM稼働時間中すべての時間帯で相互に利用する際の手数料が無料だ。
3信金が「しのぎを削る」というより、信金業界の再編が進む中で共同による相乗効果を狙っていると言えそうだ。
文・菱田秀則(ライター)
【M&A Online 無料会員登録のご案内】
M&A速報、コラムを日々配信!
X(旧Twitter)で情報を受け取るにはここをクリック
【M&A Online 無料会員登録のご案内】
6000本超のM&A関連コラム読み放題!! M&Aデータベースが使い放題!!
登録無料、会員登録はここをクリック






















![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
