
東京一極集中を解消するために政府や地方自治体は、支援金などで「移住婚」を促進している。特に東京に住む未婚の女性という特定の人たちの結婚と地方移住を政策的に促すことで、少子化対策や地方創生を達成しようとしているが、移動をめぐる統治の実情とは。
『移動と階級』より一部抜粋・再構成してお届けする。
炎上した「移住婚」
「地方の人と結婚して、東京23区から移り住んだら支援金がもらえるらしい」――こう聞いたら、優れた地方の人口減少対策だと思うか、最近流行りの行政による婚活支援だと思うか、女性の結婚を誘導する気持ち悪い取り組みだと思うだろうか。
2024年8月、政府は東京23区に在住・通勤している未婚の女性が、結婚のために地方へ移住する「移住婚」に対して、自治体から60万円の支援金を出す制度を検討していることを公表し、炎上した。
3日ほどで撤回された制度案に対して、SNSでは「性別で分けることは不公平だ」「たった60万円の補助で東京から出て結婚すると思うか」「目の前にお金をちらつかせたら、国民が思い通りになると思われているみたい」と批判の声があがった。
内閣官房の参事官補佐(当時)は、女性に絞った背景について、「不公平との批判もあるが、何かしら手を打たなければならないと考えている。地方への移住を考える女性の後押しとなるようにしたい」と答えた。
移住婚の事例は、国内の地域を越える――特に地方への人の移動に対する――最近の政策の特徴を教えてくれる。それは、「国や自治体が、金銭的なインセンティブによって、都市から地方への移住者を増やそうとしている」ということである。
移住婚の促進は、女性、中でも東京に住む未婚の女性という特定の人たちの結婚と地方移住を政策的に促すことで、少子化対策や地方創生を達成しようとした。しかし、SNS上の反応は違った。個人の移動にとやかく言われたくないし、男女不平等だし、余計なお世話だし、なんだか気持ち悪いということで炎上したわけである。
移動をめぐる統治
「個人の移動」に対する政策的な介入は、国家権力の根底にあり続けてきたものであり、それ自体は新しいものではない。しかし、新自由主義的な政治が支配的な今日の状況では、自由な移動を促進する・移動の希望を叶えるという理由で、政策が個人の移動にさまざまな方法で介入するようになっている。
国や自治体は、「移動は個人の自由ですよ」と言いつつ、さまざまな仕組み・仕掛けを駆使して、移動を誘導・操作しようと試みることで、「理想的な移動」「良い自由な移動」と「理想的でない移動」「悪い自由な移動」を選別し、国家を維持、発展させようとしてきた/している。
また、移動の価値が高まる一方、グローバル化による社会や共同体の流動性も高まり、新たな不確実性やリスクへの対応を理由に、移動への政策的な介入が「必要」と判断される場面も増えている。
移動への政策的な介入は、移動をめぐる格差や不平等の解消のために必要不可欠であり、良い効果もたくさんもたらしている。田園回帰と呼ばれるような、農山村に惹かれる人々の背中を押したり、その結果として、消滅の危機に瀕した地域の希望になったりしている。
また、地域の公共交通を維持させたり、移動手段が限られる買い物難民を救ったり、感染症の拡大を防いだりといったケースではポジティブな成果も多々出ている。
半数が移動格差解消への政府の支援に同意
では、こうした移動に対する政策的な介入を、人々はどう思っているのだろうか。
今回の調査で、「政府は移動の自由をめぐる差を解消するために支援を行うべきだと思いますか?」と聞いたところ、同意する人は49.0%、同意しない人は33.0%、わからない人は18.0%であった。
つまり、約半数の人は、移動の自由をめぐる格差の解消に政府が介入することに同意しているわけである。一方で、約3人に1人は同意しないという実態も見えてくる。
お金による移動の誘導は立場がわかれる
「政府が個人の移動を金銭的支援によって誘導するべきだと思いますか?」という質問については、どうだろうか。
調査の結果、金銭的な支援による誘導に同意する人は41.2%、同意しない人は42.8%、わからない人は16.0%であった。わからないと回答した人をのぞくと、金銭的な支援での誘導に同意する人と同意しない人は、ほぼ同割合であるようだ。
さらに、金銭的な支援について、さまざまな属性との関連を探ってみると、年収や性別には大きな差はなかったが、年代ごとの回答だと興味深い結果が得られた。それは、若年層ほど政府が金銭的支援によって個人の移動を誘導することに同意する傾向がありそうだというものである(図表13)。最も高い30代と最も低い70代ではかなりの開きがある。
75.4%が移動の制限には同意しない
「政府が個人の移動を制限すること」についてはどうだろうか。調査の結果、同意する人が12.7%、同意しない人が75.4%、わからないと回答した人が11.9%であった。約4人に3人が、移動の制限には同意していないことがわかる。
この結果は当然のようで、よく考えてみると興味深い。わかりやすいのは、コロナ禍における移動制限である。コロナ禍に限定した移動制限については、58.7%が同意すると回答している。つまり、制限に同意する12.7%とは大きな差がある。この差をどう考えるべきだろうか。
一つの説明として、一般的に同意できないと考えられる移動制限でも、コロナ禍のような「緊急事態」「例外状態」であれば正しいと人々は判断し、同意するという説明が導き出される。しかし、例外状態や緊急事態は厳密に定義できるものではない。
どこまでが緊急事態なのか、何をもって例外状態なのか、それは社会的に醸成される雰囲気、政治的な判断、個々人の認識などによる。私たちの多くは移動を制限されることに反対する一方で、特定の条件下であれば意外と移動の制限に理解を示してしまうのかもしれない。
文/伊藤将人 写真/shutterstock
『移動と階級』(講談社)
武田知弘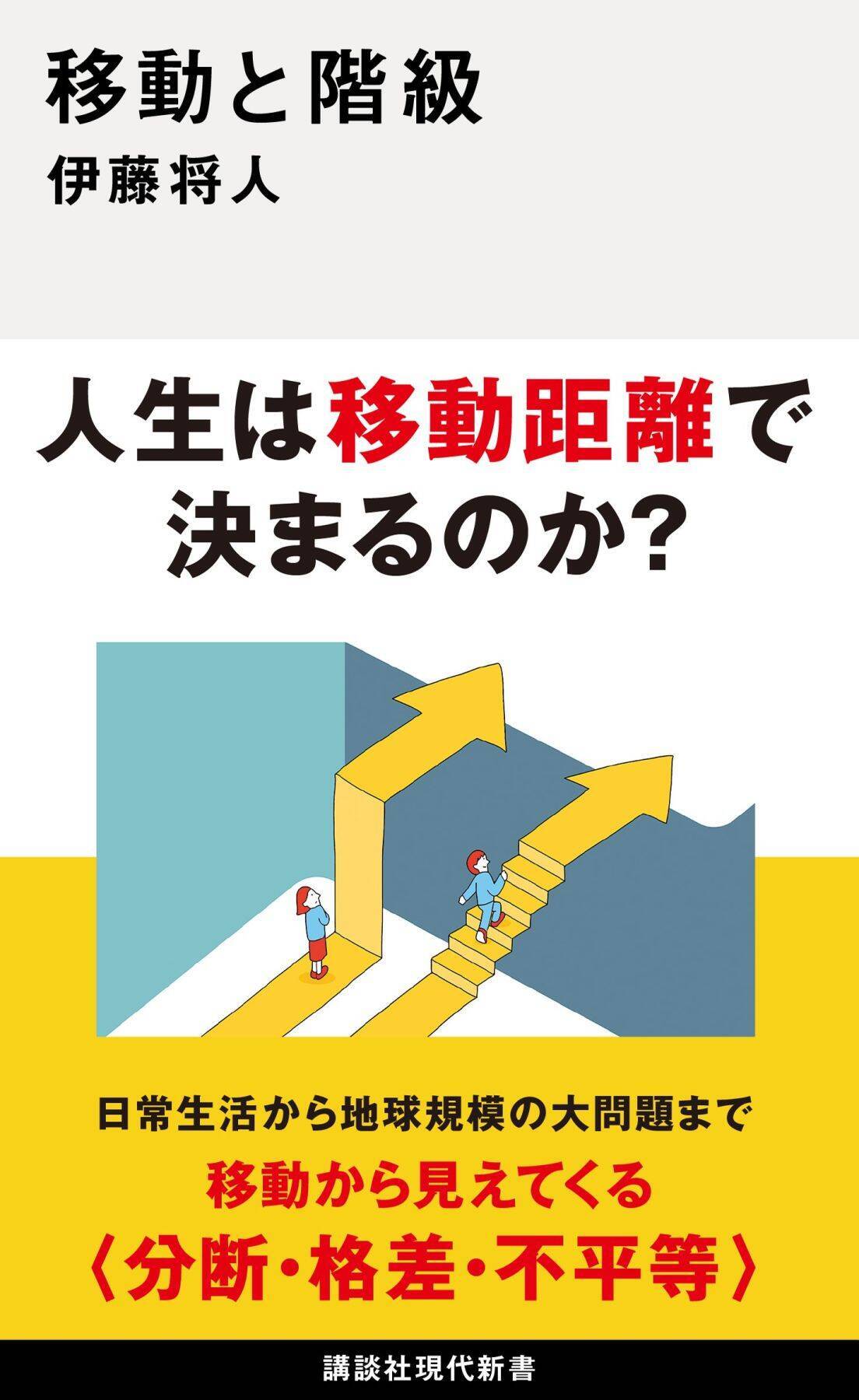
この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。
日本人は移動しなくなったのか?
人生は移動距離で決まるのか?
なぜ「移動格差」が生まれているのか?
通勤・通学、買い物、旅行、引っ越し、観光、移民・難民、気候危機……
日常生活から地球規模の大問題まで、移動から見えてくる〈分断・格差・不平等〉
独自調査データと豊富な研究蓄積から「移動階級社会」の実態に迫る!
【本書のおもな内容】
●「移動は成功をもたらす」は本当なのか?
●半数弱は「自由に移動できない人間」だと思っている
●5人に1人は移動の自由さに満足していない
●3人に1人が他人の移動を「羨ましい」と思っている
●移動は「無駄な時間」なのか?
●移動は誰のものか?――ジェンダー不平等という問題
●格差解消に向けた「5つの方策」とは?……ほか
【目次】
第1章 移動とは何か?
第2章 知られざる「移動格差」の実態
第3章 移動をめぐる「7つの論点」
第4章 格差解消に向けた「5つの観点と方策」
「移動」をもっと考えるためのブックリスト
























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


