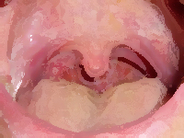「やむを得ず」持ち手を布巾やタオルでくるんで使用していたが、後に、中華鍋とはそういうものだということを知った。
これでも一応主婦なのだから、呆れた話である。
とはいえ、フツウに考えたら、「熱くならないように工夫する」ことが当たり前じゃないか。
人間、放っておいても便利な工夫をしてしまうのが、常。
なぜ中華鍋は、そこで進化を止めてしまったのかは、逆に不思議にも思える。
そんな疑問を話したところ、ある友人は、
「鍋を作るのは工場の人で、料理をするのはお母さんで、鍋を作る人たちはお母さんたちの苦労、熱さをわかってなかったんじゃない?」
などと面白い説を披露してくれた。
冗談はさておき、本当のところ、どうなのか。中国の人にとっては、持ち手が熱くなることなんて、屁でもないのか。
ある高級中華料理店の料理長をしている中国人の男性に聞いてみると、
「もともと両手鍋は『上海鍋』(これを広東鍋としている説もあり)で、片手持ちのは『北京鍋』。日本で多く使っているのは北京鍋だけど、家庭で作る料理なら、本当は持ち手が熱くならないもので十分ですよ」ということだった。
中華料理では「火力」が非常に大事というのはよく聞く話だが、実は中華料理店の料理を作る際の熱量は、7000〜8000キロカロリーにもなるのだとか。
また、温度でいくと、いちばん熱い場所で300〜400度にもなるという。
「プロは300度で、鍋を空炊きしてから使うから、プラスチックの持ち手だと溶けてしまうし、木とかだと熱くなっちゃって、全然ダメね」
つまり、持ち手の「断熱」の工夫をしなかったわけではなく、断熱できる温度の限界を超えているということのよう。
「それに、バーナーでもまだ熱さが足りないときは、火に風を吹きかけて激しく燃やして、3万キロカロリーにもなることもあるんですよ」
そんな激しく熱い中華料理をも作れるようにできているのが、「持ち手が熱くなる」中華鍋というわけだ。
自分の料理の腕前程度では、どっちにしても、「熱々の持ち手の鍋」が活かされないなと思うのでした。
(田幸和歌子)