死のかたちから見えてくる人間と社会の実相。過去百年の日本と世界を、さまざまな命の終わり方を通して浮き彫りにする。
■1937(昭和12)年未完のヒトラーか、早すぎた大川隆法か北一輝(享年54)
北一輝の思想はわかりにくい。当時流行の「国家社会主義」ではあるものの、ヒトラーのナチズムのように実現はしなかった。また、若手軍人の国粋的気分を高揚させつつ、天皇制自体は否定していたりもする。右と左の二元対立構図で考えがちな現代の感覚では、理解できないのかもしれない。
ところが、同時代の人間も彼の思想をわかっていたとは言い難い。親交があり、並べて語られたりもする大川周明などは「魔王」と呼んだ。いわく「是非善悪の物さしなどは、母親の胎内に置き去りに」したような存在なのだと。もしそうなら、そういう人間ほど恐ろしいものはない。昭和11(1936)年に2・26事件が起きたあと、北が理論的指導者として逮捕されたのも、その翌年、クーデターとの直接的な関係が曖昧なまま、銃殺刑に処されたのも、国家がその「魔王」的な影響力を気味悪く感じ、怖れたからだろう。
そんなわかりにくさがよくわかる(?)のが『霊告日記』である。
とまあ、最近でいえば大川隆法みたいな宗教家としての側面もあったわけだが、実際、悟りの境地に達していたのか、銃殺される際も取り乱すことはなかった。ただ、死刑前日、母親と面会するときにはさすがにつらそうだったという。
「男は生きている間好きなことをやって死ぬのが一番幸せだ。お父さんも好きな酒をさんざん飲んで、五十歳で死んで行った。お前も自分の好きなことをして死んで行くのだから幸せだ」(『朝日選書278 北一輝』渡辺京二)
この子にしてこの母あり、と言いたいところだが、彼女とて北の思想は理解できていなかっただろう。明治末から昭和初めを代表する奇人であることは間違いない。
■1938(昭和13)年芸術家をとりこにした昭和の「朋ちゃん」高村智恵子(享年52)
高村光太郎の『智恵子抄』は「愛の詩集」とも呼ばれる。ただ、それは「死の詩集」でもあるかもしれない。高村智恵子というひとりの女性の心身が傷つき、壊れていくのを哀しく美しく謳い上げたものだからだ。
智恵子は福島県の造り酒屋に生まれ、親の反対を押し切って東京で画家修業をしていた。が、独特すぎる色づかい(色覚異常だったとの説も)を師に批判され、そんななか、光太郎の独創的な芸術論に感銘を受ける。自分のアトリエを訪ねてきた智恵子に光太郎も魅力を感じ、ふたりは3年後、事実婚をした。
というのも、智恵子はいわゆる「新しい女」で、平塚らいてうの雑誌『青鞜』の表紙絵なども描いていた。光太郎もそういうところを面白がり、それまでにない夫婦像をふたりで目指したわけだ。とはいえ、芸術家同士の結婚はとかく難しい。自らも吉村昭と結婚して「作家夫婦」として生涯をともにした津村節子は、小説『智恵子飛ぶ』にこんな文章を綴った。
「二人の力が拮抗していれば、最も身近にライヴァルを置くことになる。不均衡であれば、力ある者は無意識のうちに力弱き者を圧してしまう。
実際、結婚後、光太郎は彫刻や詩が評価されるようになったが、智恵子の絵はそうならなかった。ただ、詩についていえば『あどけない話』の書き出し「智恵子は東京に空が無いという、ほんとの空が見たいという」が示すように、むしろ彼女こそ本物の詩人に思われ、光太郎はそれを巧く自らの創作に取り込んでいった印象だ。たとえば『あどけない話』と同じ昭和3年の作である『ぼろぼろな駝鳥』で展開される動物園を題材にした文明批評など、智恵子からの影響なしには生まれなかったのではないか。
その明暗を分けたものは芸術的才能云々以前に、人間力の差だろう。智恵子は婚約中から肋膜炎を患っており、その後、実家の経営も傾く(のち破産)などして、45歳のときに精神に異常をきたした。その翌年には、自殺未遂もしている。そういう心身が不安定な妻に頼られ、ときに反発されながらも庇護していく日々は光太郎に全能感のようなものを与えただろう。これが、著名な彫刻家だった父に対する劣等感を克服することにもつながったと考えられる。
この「全能感」というのは、男女が協力して創作するときなどにちょくちょくカギとなるものだ。平成のJポップにおける小室哲哉と華原朋美の関係なども、これが一時的に奏功したパターンといえる。そういう意味で、光太郎はプロデューサー型で智恵子は歌姫タイプだった。そのコラボの集大成が、彼女の死後に編まれた『智恵子抄』だったわけだ。
「天然の向うに行ってしまった」とか「もう人間界の切符を持たない」といった光太郎の描写はときに残酷ですらあるが『山麓の二人』に出てくる「わたしもうじき駄目になる」という智恵子の言葉ほど、哀しく美しい響きはほかにない。そんな彼女について、光太郎が「主人は正直で可憐な妻を気違にした」(『ばけもの屋敷』)と、自らの責任を認めていたことも付け加えておきたい。
昭和13年、結核が悪化した52歳の智恵子は光太郎の持参したレモンをひとくち齧り、永眠した。「ほんとの空」に憧れ「ほんとのミューズ」となった彼女は、その愛と死が文学になることで永遠の命を得たともいえる。
文:宝泉薫(作家・芸能評論家)
















![医療機器販売の(株)ホクシンメディカル[兵庫]が再度の資金ショート](http://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexnews%252Ffeed%252FTsr%252Fa8%252FTsr_1198527%252FTsr_1198527_1.jpg,zoom=184x184,quality=100,type=jpg)
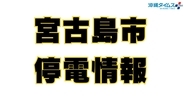











![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)


![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)






