坂崎かおるは2020年から本格的に小説執筆を開始、すぐにいくつものコンテストで結果をあらわした、注目の新鋭だ。本書は初の単行本。
「ニューヨークの魔女」では、19世紀末のニューヨークを舞台として、電力産業化のための異様なデモンストレーションを描く。古屋敷の地下室で発見された不死の魔女を、電気椅子で処刑するのだ。殺されては甦り、そのたびに記憶が混乱していく魔女。
「ファーサイド」は、1962年、アメリカの農村で起こった事件だ。ひとびとは、奴隷としてDと呼ばれる種族(直立したロバのような姿で言葉を話す)をあたりまえのように使役している。語り手の少年はほかのDとは少し違う、思慮深く丁寧なDと出会った。Dは少年の家に雇われ、デニーと名づけられる。
「私のつまと、私のはは」は、擬似現実の赤ん坊に振りまわされる、理子(りこ)と知由里(ちゆり)の物語だ。ふたりはパートナーとして暮らしており、デザイナーである理子が仕事の関係で、クライアントから〈ひよひよ〉を提供される。〈ひよひよ〉はAR技術を応用した子育て体験キットで、リアルタイムで成長し、本物同様にぐずったり笑ったり排泄したりミルクを飲む。
ここに紹介した三篇もそうだが、どの作品もカタルシス的な決着はつかない。読者はどこにも持っていきようのない気持ちを抱えたまま、ページを閉じることになる。
(牧眞司)

















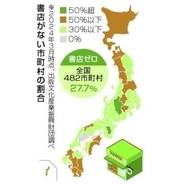


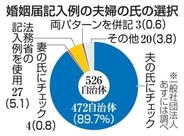





![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)

![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い ダークブラウン/ブラック RYST5040H(DBR/BK4) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41qYUAHcP+L._SL500_.jpg)






