村上春樹の新作『街とその不確かな壁』が発売となりました。とにかく新作が出れば日本中がお祭り騒ぎ。
その盛り上がりたるや、他のベストセラー作家(百田尚樹とか)ですら村上春樹の足元にも及びません。とはいえ、そんなに盛り上がるほどありがたるような代物なんでしょうか。村上春樹とその作品の「薄っぺらさ」を検証したてみました。※こちらの記事は、『騎士団長殺し』発表時に実話BUNKA超タブーvol.19に掲載したものです。
本誌が発売されるころには、にわかハルキストたちやワイドショーなどのテレビ番組が村上春樹の4年ぶりの長編小説『騎士団長殺し』を手に大騒ぎを繰り広げ、春樹フィーバーが巻き起こっているに違いない。もしかすると、本誌読者のなかにもこのビッグウェーブに乗り、『騎士団長殺し』を買ってしまった流されやすい人がいるかもしれない。
最初にはっきり言っておくが、村上春樹を読んで喜んでいるのは、単なるミーハーか、モテないオヤジか、キモオタか、メンヘラ文系女子のどれかだ。
たしかに、村上春樹の新作というのは、とりわけ長編小説の場合、発売そのものが一大イベントとなる。
実際、2009年に発売された『1Q84』や13年の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』では、各地の書店でカウントダウンイベントが行われ、当日の午前0時から販売が開始されるなど、まさにお祭り騒ぎとなった。そして、このにわかファンが大騒ぎする様子をワイドショーなどのテレビが大々的に取り上げるというのがいつものパターンなのだ。
もちろん、今回の新作でもまったく同じ構図が繰り広げられている。『騎士団長殺し』は発売前から計30万部の重版が決まり、すでに累計120万部。
そもそも、現在の村上春樹人気は、大手の出版社が仕掛けて作り出したインチキなブームにすぎない。
じつは、2000年代までの村上春樹はサブカル好きに人気が高いだけの「普通の売れている作家」だった。日本文学というのは基本的に家族の葛藤や貧乏話をベースにした辛気くさいものが多い。
とはいえ、その程度のことだけで、いまどき小説が100万部も売れるわけがない。実際、02年発売の『海辺のカフカ』や04年の『アフターダーク』も多少話題になったが、社会現象にはほど遠く、発売日もお祭り騒ぎにならなかった。
それならなぜ村上春樹の新作発売が現在のような一大イベントになったのか。
その理由は、09年に新潮社から発売された12作目の長編『1Q84』にある。このとき、新潮社はまず「村上春樹の最新長編小説 初夏刊行」とだけ告知し、その後開示したのもタイトルと価格、2巻同時発売という情報のみ。発売日まで作品の内容をいっさい明らかにしなかったのだ。
新潮社の社内でも、最初の情報の段階では営業にもなにも知らせず、発売前に原稿を読んだのは編集幹部と担当編集の数人だけだったといわれる。書店にも詳細を知らせないほど情報統制が徹底していたという。
これはハリウッド映画や米アップルが新製品を発売する際によくやる「ティーザー広告」という手法だ。
断片的な情報のみを小出しにして消費者を焦らしまくり、商品への期待値を上げようという、なんとも必死でセコすぎるプロモーションのテクニックである。
一説には、村上春樹自身がこの手法を出版社に持ちかけたともいわれている。
ところが、この宣伝戦略にまんまとマスコミが飛びつき、大々的に取り上げたことで話題が沸騰。本は爆発的に売れまくり、同時発売された『1Q84 BOOK1』『1Q84 BOOK2』は2カ月後に100万部に到達。翌年に発売された『BOOK3』にいたっては、わずか12日間でミリオンを達成している。そして、このときに誕生したのが、タイトルと発売日がアナウンスされると春樹ファンがネット上で「SFじゃないか」「いや恋愛小説だ」と勝手に内容を予測して盛り上がる風潮である。
発売日のカウントダウンイベントの開催や、その様子をワイドショーが大きく取り上げ始めたのも、すべて『1Q84』が発端だ。
実際、13年に発売された『多崎つくる』でも文藝春秋がまったく同じ宣伝戦略を採用し、その結果、この作品は『1Q84 BOOK3』を5日上回るスピードでミリオンを達成している。もちろん、今回の『騎士団長殺し』も同様だ。版元の新潮社は当初、書き下ろしの長編小説で全2巻という情報しか出さず、その後も発売日までタイトルと副題、背表紙のイメージ以外の情報をいっさい出さなかった。それにより、マスコミとファンがバカ騒ぎを繰り広げたのだ。
つまり、村上春樹の小説というのは「作られたミリオンセラー」なのである。
米国で酷評されている村上春樹しかし、いくら宣伝で売れていると指摘しても、おそらく春樹ファンは小説の面白さを主張するだろう。
ハルキストには「村上春樹は偉大な作家」と真顔で語るおめでたい人たちもたくさんいる。
しかも、いつもは人のことを批判しかしないマスコミや評論家たちも、村上春樹に関してはなぜかベタボメだ。また、仮に文芸評論家が春樹作品を批判しようと思っても、それを掲載してくれるメジャーな雑誌はどこにも存在しない。
なかでも、新潮社と文藝春秋は村上春樹とつながりが深いだけに、天下の『週刊文春』でさえ、新作が出ると他社の本でも気持ち悪いほどヨイショしまくる。
村上春樹は恐妻家で、私生活はもちろん、作品も夫人にコントロールされているのだが、新潮社や文藝春秋のベテラン編集者は夫人に高価な時計やハンドバッグをプレゼントして必死に取り入っているくらいだ。
だから、村上春樹がどれほど自己愛が強くて薄っぺらな人間だとしても、絶対にそんなことは書かないのだ。
こうしたマスコミのベタボメ記事を真に受け、「村上春樹はすごい」「おしゃれ」「春樹作品を読むとモテる」と本気で信じてしまったのが、ハルキストという情弱信者だ。
だが、利権と関係のない海外メディアは、村上春樹や夫人の顔色をうかがう必要などまったくない。そのため、欧米のマスコミには村上春樹をボロクソに批判した記事も少なくはない。
たとえば、2011年にアメリカで『1Q84』が発売された際、日本のマスコミは「ニューヨークでは行列」「アメリカでも話題騒然」などと報じたが、これは大ウソ。書評が出るだけでも価値があるといわれるニューヨーク・タイムズ紙では、女性ジャーナリストが『1Q84』に「失敗作」の烙印を押している。
さらに、このジャーナリストは、日本で村上春樹を直接取材したニューヨーク・タイムズ・マガジンの評論家とポッドキャスト番組で対談し、「いままで読んだ本のなかで最悪の作品」とまで酷評し、一方の評論家も「村上は作家というほどの存在ではなく、人生に対する彼の答えはますます浅はかに聞こえる」と切って捨てているのだ。まさにクソミソといっていいだろう。
日本のマスコミのヨイショ記事しか見たことのないハルキストは信じられないだろうが、これがアメリカのマスコミによる春樹作品への本当の評価だ。ちなみに、件の評論家は村上春樹の英語力もボロクソにけなしている。
そもそも『1Q84』はミリオンを記録したとはいえ、オウム真理教を彷彿とさせるカルト宗教、セックス、ドラッグ、レズ、児童ポルノ、DV、いじめ、家庭崩壊と、まるで少し前のケータイ小説のような安っぽい内容の小説なのだ。
特にエロ描写が異常なほど多く、女の主人公が婦人警官とレズ行為をしたり、性表現を頻繁に使ったりする。まるで赤川次郎の小説をポルノにし、やたらと長くした感じなのである。
これではアメリカで酷評されるのも当たり前。むしろ「いくら作られたミリオン」といっても、そんな小説が社会現象になり、100万部も売れてしまった日本のほうがどうかしている。
モテない童貞が書いた妄想小説もう一度言うが、いくら話題でも村上春樹の新作を読む必要はまったくない。
どうしてもハルキストを気どって村上春樹のことを語りたいというなら、1987年に発売された書き下ろし長編で、代表作でもある『ノルウェイの森』を読んでおけば十分だ。
内容は、どう見ても村上春樹本人としか思えない自己愛の強い37歳のおっさんの「僕」が、心を病んだ最愛の「直子」に振り回された青春時代を陶酔しながら振り返るキモい恋愛小説。
繊細な「僕」は、自分の殻に閉じこもって厨二的ハードボイルドを気どっている。そんないかにも童貞っぽい「僕」なのに、なぜか女にモテモテで、向こうから近づいてきて都合よくセックスさせてくれるのだ。
「僕」は表面上こそ女子たちに冷めたポーズを取っているが、内心では大喜び。ただし、女の主要登場人物は全員が精神を病んでいたりかまってちゃんだったり自殺したりするメンヘラばかりで、最愛の「直子」も日本の恋愛小説のセオリー通り、最終的に自殺する。
村上春樹の小説は、この『ノルウェイの森』に限らず、基本的に全部こういう構造で成り立っている。女にモテる主人公が自己陶酔して「繊細なボク」をアピールするだけで、大事なことはなにひとつ語らない。そして、主人公はどいつもこいつもびっくりするほど精神性が薄っぺらいのだ。
新作を出すごとに難解さとドロドロ感が増しているが、実態はモテない童貞の妄想であり、一種のオタクファンタジー。そこにアメリカの現代文学や音楽、アートを取り入れ、ミステリーの要素を盛り込むから、おしゃれな小説に見えるだけで、本質はラノベと変わらない。
村上春樹の小説など読んでも、モテない男がさらにモテなくなるだけで、いいことは全然ない。おめでたいハルキストたちは村上春樹がノーベル文学賞に落選するたびに大げさに残念がるが、むしろ受賞するほうが大問題だ。
こんなものが、新作が出るたびに社会現象になるほど売れまくるのだから、日本という国もホントに困ったものである。やれやれ。
初出/実話BUNKA超タブーvol.19














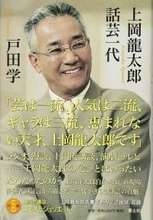







![【Amazon.co.jp限定】ゴジラ70周年記念 怪獣王シリーズ ゴジラ(2023)ゴールドカラーver.[完全生産限定] ※この商品にはBlu-ray&DVDはつきません(フィギュアのみ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51yxeR5I4oL._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ARIEL -エリアル- Blu-ray Archive BOX 地球最強の女神再臨セット (購入特典:”巧緻を極めた原作絵師 鈴木雅久”の原作絵キャンバスアート) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51TWZjmwxKL._SL500_.jpg)
(Amazon限定グッズ:ムービーモンスターシリーズ (クモオーグ、コウモリオーグ、ハチオーグ、サソリオーグ、カマキリ・カメレオン(K.K)オーグ)+Special 収納 BOX(Amazon ver.)付き)(メーカー特典:クリアしおり(ランダム 全 3 種)付き) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/316mitukrDL._SL500_.jpg)






![[山善] 32V型 ハイビジョン 液晶テレビ (裏番組録画 外付けHDD録画 対応) QRT-32W2K](https://m.media-amazon.com/images/I/516WFLybmIL._SL500_.jpg)
