馬頭琴やホーミーの流れるバックトラックの上に頭韻・脚韻を踏みまくったラップが乗り、ミュージック・ビデオ(以下、MV)の撮影場所は時に大草原。
しかし、「なぜそうなったのか?」をひとつひとつ解きほぐしていくことでモンゴル社会の背景が見え、それが私たちの固定観念に対する問い直しを投げかける。『ヒップホップ・モンゴリア 韻がつむぐ人類学』(青土社)を著した文化人類学者の島村一平氏(国立民族学博物館准教授)に訊いた。

政権総辞職の一翼を担ったラップ
――モンゴルではヒップホップはどのくらいポピュラーなのでしょうか?
島村 一番人気な音楽ジャンルがヒップホップです。ただ、これはモンゴルに特殊な現象ではなくて、今や多くの国でそうですよね。
――いくつか有名どころを教えてください。
島村 最近だとトラップ(米アトランタ発のラップ・ミュージックのサウンド/スタイル。2010年代以降、世界のボップ・ミュージックに浸透した)が流行っていて、人気のあるWOLFIZMというラッパーはポリティカルな内容も歌っています。
2000年代半ばから活動していて今も人気のグループにTATARがいますが、リーダーのザヤーが中堅ラッパーGINJINや女性シンガーMagnetとコラボした「it’s okay」。この曲は「君がいないと寂しい」と切ない片思いを歌ったラブソングのラップです。
――本の中には「モンゴルではラブソングじゃないと売れない」と語るラッパーも出てきていましたよね。
島村 実際、今はラブソングが多いです。
モンゴルでは、コロナにかかった産婦さんを隔離する際、真冬のマイナス30度の屋外を防寒着を与えずに移動させたという事件があり、保健大臣などへの批判が高まりました。そのとき、彼は報道されて3日くらいで歌詞に盛り込んだ「Give Me Justice 2」という曲を作ってYouTubeで発表し、それが1週間ほどで40万回再生(3月末時点で約90万回再生)もされました。ちなみに、モンゴル国の人口は330万人です。
ウランバートルの政府庁舎の前の広場に人々が集まって抗議のデモがあったときにはPacrapも参加しました。
――Pacrapは遊牧民出身とのことでしたが、モンゴルでは大きく分けると遊牧民系(ゲル地区出身)のラッパーと、近代的な都市生活者のラッパーとが対立してきたんですよね?
島村 モンゴル・ヒップホップでは第1世代、第2世代とジェネレーションが分かれていて、第3世代まではゲル地区出身の貧しい階層のラッパーと高層アパートに住んでいる中産階級のラッパーとのビーフが続いてきました。ただ、例えばPacrapは第4か第5世代になりますが、この世代になると分かれていた派閥のラッパー同士が一緒にサイファーをやったり、曲を作ったりするようになっています。その背景までは取材できていませんが、前の世代とは違う動きを見せているのが興味深いところです。
――『モンゴリアン・ブリング』というモンゴル・ヒップホップを題材にした映画の中で、口承文芸の詩人が語った「ヒップホップはモンゴル起源だ」という言葉が本の中で紹介されていました。そう自負しておかしくないくらい現在のラップ隆盛につながる歴史がモンゴルにはあって、例えばモンゴルの遊牧民にはディスり合うバトルの伝統もあったそうですね。
島村 ええ。遊牧民は牧歌的な存在だと思われがちなんですが、決しておとなしく羊を飼っているわけではありません。遊牧社会では、近隣のライバルに対して、交渉や情報操作をすることで、いかに良い牧草地を先に獲るかが重要です。遊牧民は広い大草原を移動しながら、植物や家畜に基づいてどこが良い牧草地か見定めていく。
例えば、モンゴルのじゃんけんは指5本で言葉を言いながら出して勝敗を競うのですが、相手をけなしながら手を出します。そして負けると、馬乳酒を一杯飲まないといけない。
ですから、ラップ・ミュージックはアメリカのブロンクスで生まれたもの、あるいはジャマイカにルーツがあるものかもしれないけれども、並行して世界にはほかにも韻を踏みながら即興で自己表現する文化が存在していたんですね。だから、彼ら目線で「ヒップホップはモンゴル起源だ」と言い出す人がいても無理はないかなと。もちろん断っておくと、その認識がモンゴル国民に共有されているわけではありません。アメリカ由来の文化であることを彼らもよく知っています。ただ、「自分たちのヒップホップはモンゴルの文化だ」という認識を彼らは持っていると思います。
――というと?
島村 日本のポピュラー音楽では、最初に欧米からロックなどの音楽が入ってきたとき、日本の音楽的な伝統と切り離して「いかに泥くささを消して欧米に近づけていくか」を課題とするミュージシャンが少なくなかったように思います。でも、モンゴル人の場合、1992年に社会主義体制が終わってポピュラー・ミュージックがどっと入ってきたときに、欧米に憧れ欧米の音楽を受容していくベクトルと同時に、「自分たちのものにしていこう」という「モンゴル化」のベクトルも強く働いた。
例えば、2000年代からヒップホップの中に伝統的なホーミーを導入し、「オルティン・ドー(長い歌)」と呼ばれるフリーリズムのうねるような歌唱法を採り入れたり、馬頭琴を使ったりし始めました。驚いたことに国宝級の伝統音楽の演奏家が当たり前のようにヒップホップのMVに参加しているし、偉大な詩人の書いた詩をラップや歌で歌うことも当たり前に行われてきました。
――世界のワールド・ミュージック市場を意識してエスニックな要素を採り入れているわけではないと。
島村 モンゴルは社会主義国時代には西側の文化は基本的に入ってきませんでした。そのため、80年代にパリやロンドンで始まったワールド・ミュージックのムーブメントを彼らは経験していません。むしろ、ワールド・ミュージックが下火になった頃に欧米からポピュラー音楽が入ってきた。実際、ラッパーたちが「ワールド・ミュージックのマーケットでウケるかどうか」と語るのを少なくとも私は聞いたことがありません。そうではなくて、カッコいいと思ったアメリカのラップ・ミュージックに対して「どうやったら自分たちの音楽ができるのか」と考えたときに、もともと存在していた頭韻で韻を踏む口承文芸の伝統や、民族楽器を採り入れていったのだと思います。
文学の詩とラップのリリックを区別しない
――モンゴルではいわゆる現代詩をラップしたものも普通に受け入れられているんですよね?
島村 ええ。モンゴル語では「リリック」と「ポエム」に区別がありません。詩/詞を表すのは同じ単語なんです。社会主義国家時代には現代詩を生み出そうとロシアの影響で教育現場でも詩を書く授業が生まれたけれども、そこでも韻を踏む伝統は残りました。ですから、書き言葉の表現においても、話し言葉や音楽表現でも、ずっと韻を踏む文化がありました。
例えば、「中原中也が現代に生まれていたらロック・ミュージシャンになっていただろう」とは日本人はなかなか思わないですよね。ところが、モンゴルのラッパーたちはみな「反逆の詩人」といわれたレンチニー・チョイノムをリスペクトし、「彼が現代に生まれていたらラッパーになっていただろう」と言います。ラップに限らず、偉大な詩人の詩をポピュラー音楽の歌手が取り上げることはごく当たり前に行われている。
ただ、近年の世界的な潮流を見てもボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞し、さらに将来的にはケンドリック・ラマーがノーベル文学賞を獲るかもしれないといわれていますよね。結局、近代に入ってから、特に20世紀になってから、文字で書かれたハイカルチャー(高位文化)としての「詩(ポエム)」と、サブカルチャー(下位文化)としての大衆音楽の歌の「歌詞(リリック)」を区別するようになっただけで、そのカテゴライズはフィクションだったと欧米の人たちも気づき始めているんじゃないかと思うんです。さらに言うと本来、詩と音楽は連続的なもので、日本人だって例えば平安時代に歌を詠んで恋する心を伝えるときには音楽、節回しを付けていたはずです。
つまり、モンゴルではハイカルチャーとサブカルチャーを区別するとか、書かれた文字の詩とラップで歌われるリリックを区別するという発想があまりなく、伝統と現代が連続している。そこが面白いところです。
――むしろ、近年行われている文学観への見直しともつながると。
島村 加えて言うと、2000年代以降、特に近年では欧米の文化のほうが偉いとか、経済大国として憧れているといった視点もあまり強くないようです。むしろ「先進国」を冷静に相対化して見ています。もっと言えば、「アメリカの黒人のラップより俺たちのほうがすごいぞ」といったアフリカン・アメリカンに対するディスまで始まっている。これはアメリカに留学して黒人に差別された経験のあるモンゴル人ラッパーたちの「ふざけんなよ、黒人」という気持ちが背景にあるのでしょう。例えば、GinjinがMCITというモンゴル・ヒップホップのオリジネーターに対するオマージュ曲の中でMCITを褒め称える一方、「黒人のヒップホップなんてすごくない」といった意味のことを歌っています。
日本に対しても冷静な目線で見ています。若手ラッパー、Choidog(チョイドク)の「Sumimasen」という曲のMVでは、日本の寿司屋でバイトして怒られている人間が描かれていくんだけれども、「すみません」と言いながらも、なんで怒られないといけないのかわからないと。
「感謝するときは『ありがとう』でしょ。なんで『すみません』なの?」といったやり取りが描かれている。日本はかつてモンゴルに対する最大の支援国で、基本的には日本人に対して悪い印象は持っていないのですが、でもモンゴル人からすると不思議な習慣を持っているように見える部分もあるわけです。
――遊牧民の口承文芸の伝統や欧米文化との距離感が相まって、独自のものになったんですね。
――シャーマニズムに傾倒するラッパーもいるそうですが、島村さんはモンゴルにおいてヒップホップとシャーマニズムは「グローバルなネオリベ・ウイルスに抗するローカルな文化の免疫系」として共通するものがある、と指摘されていました。
島村 モンゴルではヒップホップが流行るのとほぼ同時期にシャーマニズムが流行って、一時期(2010年頃)は人口の1%がシャーマンになったほどです。モンゴルでは日本とは比べものにならないくらい激しい学歴競争があり、貧富の格差がある。どちらも、そういう中で起きた現象です。ある意味では競争から脱落してしまった人たちが敗者復活できるシステムとして、シャーマンになって自他ともに救うという選択肢がある。ラッパーにも通じるところがあって、社会的な役割や位置づけが似ています。
また、シャーマンは半獣半人のような姿をして大きな太鼓を叩きながら、ラッパーはマイクを片手にリズムに乗りながら、共に韻を踏む点も共通している。伝統文化としてのシャーマニズムと外来のヒップホップが、にじり寄るように併走しているのが興味深いところです。
私はもともと2000年頃にシャーマニズム研究からヒップホップに興味を持つようになったんです。辺境でフィールドワークをしていると、シャーマンが韻を踏みながら祈祷して精霊を憑依させている。調査を終えて首都のウランバートルに戻ると、今度はFMラジオでラッパーが韻を踏んでいるのが聞こえてくる。それが印象的で、何か関連があるんじゃないかとずっと思っていたんです。
そんな矢先に、私と長年付き合いのあるドライバーがシャーマンになっちゃったもので、「精霊が入るって、どういうことなの?」と聞いてみたら、「韻を唱えているうちに、自分が考えていることとは別の言葉が自然に口から出てくる。自分でも『何言ってんだ?』と思いながらも口から出てくる。それが精霊なんだ」と。それでヒップホップについて調べてみたら、モンゴルでも日本でもラッパーはフリースタイルをしていると「降りてくる」瞬間があって、そのとき言葉が勝手に紡ぎ出されるというような表現を使っていた。つまり憑依現象とは、韻を使うことで自分が意識的に操作するのとは別の言語を編み出す技法ではないかと思うようになったんです。
――最後に、島村さんが最近注目しているラッパーを教えてください。
島村 女性のラッパーが元気なのもモンゴルの特徴で、例えばNENEという、まだ20歳で心理学を学んでいる学生ラッパーが面白いですね。彼女は韻をあまり踏んでいないんですけど、ものすごいフロウです。
チル系では、馬頭琴とコラボしたNMNの「tsahilbaa(火花)」という曲が非常に気持ちよく、これもおすすめです。
それから、モンゴル北方にはロシアとの国境をまたいで住んでいるモンゴル語系の言語を話すブリヤート人(ブリヤート・モンゴル人)がいて、そこでは日本の東北弁を彷彿とさせるような丸みのある「方言」が使われています。ロシア側のブリヤート人が、ブリヤート語でラップした曲が、モンゴル国の都市部のウランバートルの若者にクールなものだと思われているんですね。
国境をまたいだ現象なので単純に日本と比較できませんが、日本では地方の言葉で歌を唄うことはあまり流行っていませんよね。しかし、ブリヤート人の歌うこの「TONSHIT(手を叩け)」という曲は、モンゴル国の首都でメジャーな存在になっています。これも現象として興味深いところです。
(プロフィール)
島村一平(しまむら・いっぺい)
1969年、愛媛県生まれ。国立民族学博物館准教授。文化人類学・モンゴル地域研究専攻。博士(文学)。早稲田大学法学部卒業後、テレビ番組制作会社に就職。取材で訪れたモンゴルに魅せられ制作会社を退社、モンゴルへ留学する。モンゴル国立大学大学院修士課程修了(民族学専攻)。総合研究大学院大学博士後期課程単位取得退学。滋賀県立大学准教授を経て2020年春より現職。著書に『増殖するシャーマン モンゴル・ブリヤートのシャーマニズムとエスニシティ』(春風社)、編著に『大学生が見た素顔のモンゴル』(サンライズ出版)などがある。

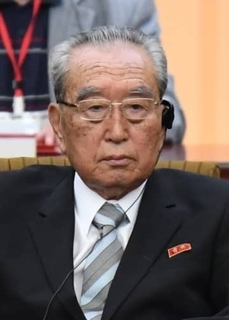




















![【Amazon.co.jp限定】カラオケ行こ! Blu-ray豪華版(特典DVD付)(クリアしおり&ポストカード付き) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51vRbNoDqRL._SL500_.jpg)
![『ゴジラ-1.0』 2枚組 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41lU7cnz6-L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ゴジラ70周年記念 怪獣王シリーズ ゴジラ(2023)ゴールドカラーver.[完全生産限定] ※この商品にはBlu-ray&DVDはつきません(フィギュアのみ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51yxeR5I4oL._SL500_.jpg)




![SCIENCE FICTION (生産限定盤)(3枚組)[Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/31rt4g7gE9L._SL500_.jpg)



![[山善] 32V型 ハイビジョン 液晶テレビ (裏番組録画 外付けHDD録画 対応) QRT-32W2K](https://m.media-amazon.com/images/I/516WFLybmIL._SL500_.jpg)