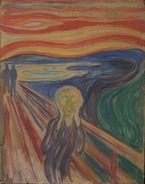学校の水泳用タオルといえばいま、ゴムとスナップボタンがついているタイプが一般的だと思う。ラップタオル(巻きタオル)などと呼ばれ、スカートやてるてる坊主みたいに体へ巻くことで、ちっちゃな更衣室になる。
でも30~40年前まで、このタオルはなかった。子どもたちは風呂上がりみたいに、普通のバスタオルを巻いて着替えていた。
そこで、調べてみた。ゴムのついたタオルは、一体どう生まれて、どう広まっていったんだろう? と。企業や文献、当時を知る人の話などからまとめた歴史は、以下の通り。
まず前提として、昔の小学校では、男女一緒に教室で着替えることが多かったことを頭に入れておきたい。
そんなあるとき、水泳のタオルは生まれた。1970年代ごろ、着替えに不満を抱いていた子の親が、ゴムをつけることを考案したらしい。
一気に広まったのは、1980年代。手作りの方法が少しずつ広まる中、キャラクターものが市販されたことで人気は爆発した。商品化したのは、当時子ども服やタオル地の商品を扱っていた企業。バンダイやサンリオなどと提携して作られたラップタオルは、子どものハートをつかんでヒットした。
その影響で、ラップタオルの存在は誰もが知ることとなり、市販品が売れただけじゃなく、親が手作りするケースもさらに増えた。しかも子どもは、友だちがいいものを持っていたら、自分も欲しくなっちゃうから、親にねだる。
そうして、水泳のタオルといえば、ゴムとスナップがついたラップタオルが一般的になったみたいだ。
ちなみに学校は、ラップタオルを使うよう指導してるんだろうか? 文部科学省に伺った。
「ゴムの入ったタオルを持ってくるようにという指針は、今も昔も特に示していません。各学校の事情や配慮で推奨する場合があるかもしれませんが、基本的にご家庭の判断に任せているかと思います」
とはいえ学校用品として、ランドセルなどと一緒に売られてるわけで、学校からの指導がなくても、もはや必需品といえるかもしれない。
ゴムをつけるというちょっとした工夫で、着替え時間をかなり平和にしてくれたラップタオル。
その歴史を見てみると、大きな発明品だったような気がしています。
(イチカワ)
でも30~40年前まで、このタオルはなかった。子どもたちは風呂上がりみたいに、普通のバスタオルを巻いて着替えていた。
そこで、調べてみた。ゴムのついたタオルは、一体どう生まれて、どう広まっていったんだろう? と。企業や文献、当時を知る人の話などからまとめた歴史は、以下の通り。
まず前提として、昔の小学校では、男女一緒に教室で着替えることが多かったことを頭に入れておきたい。
タオルがハラリとはだけて、中の人がチラリしないよう、細心の注意を払う必要があった。男の子の場合、タオルを奪うワルガキもいた。さらにその対策として、タオルなしでも着替えられる、パンツ脱ぎのテクニックを習得する子もいた。うまく着替えることは、子どもたちにとってプールがある日の大きなテーマだった。
そんなあるとき、水泳のタオルは生まれた。1970年代ごろ、着替えに不満を抱いていた子の親が、ゴムをつけることを考案したらしい。
詳しい考案者は分からないけど、家庭から生まれた知恵だったようだ。小学生が、より男女に気を遣う時代になったことも、関係しているかもしれない。
一気に広まったのは、1980年代。手作りの方法が少しずつ広まる中、キャラクターものが市販されたことで人気は爆発した。商品化したのは、当時子ども服やタオル地の商品を扱っていた企業。バンダイやサンリオなどと提携して作られたラップタオルは、子どものハートをつかんでヒットした。
その影響で、ラップタオルの存在は誰もが知ることとなり、市販品が売れただけじゃなく、親が手作りするケースもさらに増えた。しかも子どもは、友だちがいいものを持っていたら、自分も欲しくなっちゃうから、親にねだる。
そうして、水泳のタオルといえば、ゴムとスナップがついたラップタオルが一般的になったみたいだ。
ちなみに学校は、ラップタオルを使うよう指導してるんだろうか? 文部科学省に伺った。
「ゴムの入ったタオルを持ってくるようにという指針は、今も昔も特に示していません。各学校の事情や配慮で推奨する場合があるかもしれませんが、基本的にご家庭の判断に任せているかと思います」
とはいえ学校用品として、ランドセルなどと一緒に売られてるわけで、学校からの指導がなくても、もはや必需品といえるかもしれない。
ゴムをつけるというちょっとした工夫で、着替え時間をかなり平和にしてくれたラップタオル。
その歴史を見てみると、大きな発明品だったような気がしています。
(イチカワ)