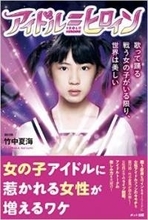1991年に登場し、いまだに続編がリリースされつづけている落ちゲー「ぷよぷよ」の生みの親、米光一成。
この二人が対談するイベントに行ってきた!
「行ってきた!」っても、これを書いているのは米光一成本人なので、そりゃ行きます。
2010年8月21日、東京工芸大学特別講演。
岩谷徹さんは、東京工芸大学芸術学部ゲーム学科の教授なのだ。
タイトルは「ゲームの未来と教育」。
「ゲームを作りたいな」というときに、自分が遊んだゲームの延長線だけで考えると視野が狭すぎる。
そんな話題から、パックマンのキャラクターを思いついたときのエピソードが披露された。
岩谷「丸いピザを一切れたべた形が、口を開けたキャラクターに見えて、パックマンのキャラクターが誕生したんです。食べるというキーワードでアイデアを探していたんですよ」
米光「視点を持って見てるのって大切ですよね。「ゲーム」「食べる」っていう視点で世界を見ている。そうすると、たんなるピザも、世界的なキャラクターになっていく。ぼんやり見てると、ただのピザ。ぼくだったら、うめぇってバクバク食べて終わってるw」
岩谷「問題意識を持って動いていると、かならず何かに結びつくんです」
米光「『リブルラブル』(妖精を線で囲って捕まえるゲーム:1983年)って、ディスコで……」
岩谷「そう。
米光「実際にやったわけじゃないですよね?」
岩谷「やってないですよ!」
米光「妄想した」
岩谷「発想しただけです」
米光「そういうふうに嫌な状況でも、イヤじゃなくなる力が発想力にはあると思うんです。やらなくても、思いつくだけで、ちょっと嬉しい」
岩谷「必要は発明の母。困ったな、イヤだなってところからアイデアは生まれます」
その後も、話題はどんどん転がって、「ゲーム作りのおもしろさ」「ナムコ、驚きの朝礼」「失敗は勲章」「影響を与え合う喜び」「チョイスすることの楽しみ」「マリオは何人死んでもだいじょうぶ」「プレゼンは場数」「ゲームの悪影響って?」「リカバーできる社会」「パックマン30周年」「ゲームを作ることは人を知ることだ」「手近な楽しみだけだと飽きるよ」などなど、さまざまな話題が飛び交うスリリングな時間を過ごした。
あっという間に、時間オーバー。それでも盛り上がって、もうちょっと話しを続けてしまった。
岩谷「人を楽しませるには覚悟がいると思うんですよ。なんとなく楽しませたい、ちょっとゲームを作りたい、ってダメだと思うんですよ」
米光「そうですね。ラクして何か作るってできない。でも、うーん、だからといって、苦しいとかじゃないんですよ。どう言えばいいのかなぁ」
岩谷「かかわっているということが形になる。
米光「はい。パワーはいるんです。パワーがいるけど、苦しいパワーじゃなくて、楽しいパワー」
岩谷「真剣に楽しませる覚悟がないと大学で学べない。厳しい言い方だけど、強く言っておきたいです」
岩谷徹教授の数々の言葉に、ぼくも背筋伸びる思いでした。(米光一成)