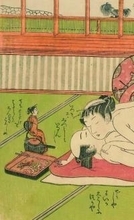「東大○○名、京大○○名、……」と合格者人数が書かれており、その下には3つの建物の写真。
日本を代表する総合大学といえば、東京大学(東大)、京都大学(京大)、大阪大学(阪大)。海外の様々な”世界大学ランキング”でも、常に日本のトップ3とされている。しかしながらこの中で、阪大だけはどうもイメージが湧かない。シンボル的な建物のイメージも同じく湧かない。
東大の「安田講堂(東京大学大講堂)」は、正面に時計塔を持つ、その堂々とそびえ立つ姿が、赤門と並び東大のシンボルとして広く知られている。昭和の学生運動の史料映像に出てくることも多い。
京大の「時計台(百周年時計台記念館)」も誰もが知っているシンボルで、正門入って正面に大きなクスノキとともにそびえ立つ姿は、京大のエンブレムの図案にもなっている。
どちらも大正14年(1925年)竣工で旧帝国大学の趣を残しつつも、近年改修工事が施された、名実共に現役のシンボルだ。
では、同じく旧帝国大学の阪大は?
結論をはっきりいうと「古い時計台のようなシンボルはない」。
東大と京大は、日本の最高学府の役割を担い、都心部のメインのキャンパスに堂々と構える、というスタイルが戦前から現在まで基本的には変わっていない。
対して阪大は、同じく旧帝国大学であるが、両者に比べてると大学設置時期は遅い。戦後の相次ぐ学部増設、本部・各学部の郊外にある豊中と吹田の両キャンパスへの移転・集約などを経て、大きく成長した歴史を持つ。大学本部建物は大阪万博の時代、吹田キャンパスにできたものだ。
歴史が浅いとはいっても、旧制高校時代からの豊中キャンパスには、昭和初期建造の「イ号館」や「待兼山修学館」など、国の登録有形文化財に登録されている建物もある。ただ、それらがシンボルとして大々的に扱われることはない。
結果として、阪大の風景として「大学本部建物」、「各キャンパスの門」、「イ号館」など、時々によってバラバラのものが使われ、「まさに阪大」と印象に残る風景・建物がないわけだ。
さて、大阪大学本部の担当者はシンボルについて、
・時計塔や赤門の「モニュメント系」に対し、阪大は「空間系」のシンボル形成を目指す
・空間系シンボルとは、面する建築による演出や、人々により生み出された記憶などが重層して成り立つもの
・空間系シンボルは、周囲の街を包含する「大学都市」の結節部
・3キャンパス(吹田・豊中・箕面)で、キャンパス内のプロムナード的な広場や中央軸を空間系シンボルとして育てるべく、様々な改善を進めている
と語っておられた。
つまり、文化財的な建物をシンボルとして有名にするのではなく、キャンパスの空間を魅力的な地域のシンボルとして常に育てていくことを目指してるようだ。
都市の中心部にあるキャンパスに憧れる阪大生は多いものの、広い敷地に建物が建ち並ぶキャンパスは研究や教育にはとても良い環境。郊外だけど極端に交通が不便ということもなく、周辺地域の住民にも親しまれている。その空間こそ、阪大のシンボルなわけだ。
威厳ある古い建物がシンボルの東大と京大。
(もがみ)