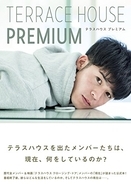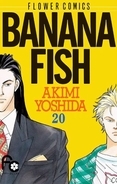安政2(1855)年、江戸一帯を大地震が襲った。夜間、推定マグニチュード6.9といわれる大きな地震が起こり、家屋倒壊や長引く火災によって1万人以上が亡くなったのではないかと考えられている。鯰絵は地震直後に大量に発行された多色刷り版画で、地の底で地震を起こすと迷信で言われていたナマズを、地震の守り神である「鹿島大明神」がこらしめるような絵などが描かれている。
この鯰絵登場したのは地震の翌日だというからビックリ。一気に民衆の間で大ブームになって、色々なバリエーションが登場した。200種類以上が2ヶ月間の間に発行され、飛ぶように売れたという、ちょっと今からでは考えられない状況だ。2ヶ月経って幕府が取り締まり、発行禁止処分となり、ブームは一瞬で終わった。当時浮世絵などの多色刷り版画には幕府の検閲を通って「極め印」と呼ばれる印がなければ流通できないシステムだったのだが、鯰絵はどれもこれも無許可だったのだ。
鯰絵は最初、前述したとおり「ナマズをこらしめる」系の絵柄に「こんな地震は二度と起きるなよ!」みたいな文章が添えられ、ナマズが「マジ反省してます」みたいな絵の物が多いのだが、しだいに変種が展開していく。
当時の日本はペリー来航(1853年)直後、社会情勢が急激に変化し、社会全体に不安が漂っていた事もあって地震を「世直し」、つまり新しい時代へのリセットであるという解釈をした鯰絵が登場した。ナマズが壊れた家屋から人を助け出している絵であったり、ナマズがヒーローとして描かれている。
また、鹿島大名神が「いつもは地震起きないように見張ってるんだけど、10月(神無月)だからオレ出雲行ってて留守にしちゃってたんだよね、ホントごめん」と言い訳するかわいらしい神の一面を描いたもの、厄除けの札としてさまざまな絵を売って人々を安心させた鯰絵もあった。
さらに震災復興で仕事が繁盛した大工や鳶(とび)職人がナマズと一緒に儲かったお金で宴会する、いたずらユーモア的な絵柄も多く、本当に多種多様な内容に感心する。中には8年前(1847年)長野県で起こって同じく1万人以上の死者を出した「善光寺地震」や頻発していた他の地震を結びつけて考察するものもあり、興味深い。
安政の大地震があったのは150年前。ずいぶん昔の事とも思えるし、たった150年前とも言えるだろう。今とは社会を取り巻く環境や科学技術レベルも違う。環境によって人々の震災に対するリアクションは変わるだろうし、それは偶然で決まる事もあるだろう。だけど事実として、こういう歴史があった。そしてその当事者たちは僕らの比較的近い先祖だと思うと、色々考えさせられる。
展示は4月10日まで、印刷博物館内「コレクション展」で観る事が出来る。一般300円・学生200円・中高生100円。当時のリアルさが伝わってくるし、どの鯰絵も江戸時代の多色刷り版画であり、そのレベルが高く美術的鑑賞価値が高いのは言うまでもなく、おすすめです。
(香山哲)