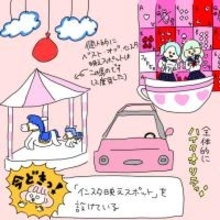千葉県長生郡長柄町に、陶芸家中野純さんの工房『立野窯(たてのがま)』はひっそりと佇んでいます。
そんな中野さんの作品の2大特徴が、電動ロクロではなく“蹴(け)ロクロ”を使っていることと、中野さん手作りの100%天然の灰釉薬を使っているということ。
“蹴ロクロ”というのはまさに文字通り足で蹴る力で回すロクロのこと。最初は電動ロクロも使っていらっしゃったということなのですが、蹴ロクロと出会ってからはずっとこちらを愛用されているそうです。蹴ロクロは時には膝を痛めることもあり、また電動ロクロほどパワーもないのですぐ止まってしまうこともあります。そのため粘土が固いと挽きにくいので電動ロクロより粘土を柔らかめに調整する必要があるけれど、やわらかすぎると今度はへたりやすくなってしまうので、粘土作りだけでも気を使う作業。パワーのある電動ロクロを使って固めの粘土で一気に作り上げるのに比べると時間も労力もかかるのですが、中野さんは「蹴ロクロで作った形はどこかやさしい感じ」に仕上がるような気がする、何より自分が楽しいからと蹴ロクロにこだわって制作されていて、まさにエコな作品です!
また器に独特の艶や色味を与える釉薬ですが、中野さんは様々な植物を燃やした灰から独自の灰釉を作って作陶されていて、まさに中野ワールドともいうべきナチュラルでやさしい色のコレクションを展開していらっしゃいます。ご想像の通りなんの灰から作った灰釉かで器の色が変わるのですが、緑色の植物の灰で作ると緑色に焼けるというように単純ではありません(笑)。さらに焼く工程で酸素を多くするのか減らすのかによっても色味がまったく違ってくるんですよ!
ぜひ写真を見比べていただきたいのですが、例えば藁や竹から作った灰釉を使い、酸素を与えて“酸化”で焼くとうっすらと赤みがかったやさしい白色に焼けるのが、酸素の足りない状況を作って“還元”で焼くと青みが強くなってきたり、松や楢は酸化だと黄色っぽく色づくのが還元だと緑色から青色に仕上がったり。他にも椿は酸化で黄色、還元できれいなさらっとした緑、藍は酸化でややクリームがかった黄色、還元で白。変わったところでは、お茶農家の友人から分けてもらった茶葉を燃やして作った灰では、酸化でとろりとした品のいい黄色が出たのだとか。
まるで化学の実験のようにトライ・アンド・エラーで緻密な実験をいろいろ試してみた結果、どうやら竹や藁などのイネ科の植物を始めとする草の灰釉を使うと乳濁したような色合いになることが多く、樹木から作られた灰釉では透明感のある色合いに焼き上がることが分かってきたとか。
ではなんでこのように灰の違いや焼き方の違いで色が不思議に変わるのでしょう?
驚いたことに「それぞれの植物から作った灰の中に含まれる鉄分や珪酸分によって主に決まるんですよ」と中野さん。え、植物の灰に鉄分が含まれるの??? と質問してみると、灰は有機物の燃えたものなのでミネラルが豊富。つまりカルシウムやカリウム、ナトリウム、そして鉄分など無数の成分がすでに微妙なバランスで調合された“自然の贈り物”なわけです! さらに焼きあげる工程である一定温度の間酸素が足りない状態を作って不完全燃焼させると(還元)、酸素が十分にある場合(酸化)とは違った化学反応を起こすので違った色味になるようなんですよね。ちなみに深く美しい緑色が特徴の織部焼ですが、これは銅が酸化反応した結果の色で、同じものを還元で焼くと赤い色になるんだそうですよ!
もちろん安定的に同じ色を得るためには市販されている化学的に鉄分含有量がコントロールされている釉薬を使った方がいいのかもしれませんが、中野さんは自然灰釉の無限の可能性にすっかり虜になっているとか。
「灰釉づくりは本当に手間がかかって大変で、短くても半年から1年、長いと2年ほどかかります。また灰1グラムを取るためにはその何百倍もの重さの植物などの原材料が必要なのですが、大きめの花器全体にまんべんなく灰釉をかけなければいけないような場合は約100リットルの灰釉に浸けるので、このためだけに約20~30キロの灰が必要……。昔むかしは灰屋さんという商売があったのですが現代ではそのようなお店もなくなってしまっているので、僕は薪窯でピザを焼いているお店にお願いして灰を分けていただいたりしています。こちらのピザ屋さんは楢を使っているので楢灰を、あちらのお店はくぬぎ灰をという風に……(笑)。他にも竹灰は自分で竹林を開いて竹を燃やして作ったり、藍灰は藍氏の方に分けていただいたり、単味の灰はいろいろ工夫して入手しています」と中野さん。では今まで失敗した灰はありましたかとお伺いすると即座に、「赤坂の焼き鳥屋さんで“植物性プランクトンの灰”というのをいただいたんだけれど、これはだめだったね~(苦笑)」とのこと。う~ん、いつかグアムの椰子の木にも挑戦していただきたいです!
このような中野さんの作品には、昔ながらの製法で作られているおいしいお醤油やお味噌、手間暇かけて作られている有機野菜などに通じるぬくもりややさしさが感じられ、作品を手にするとなんだかほんわかとした気持ちになることができます。
ぜひこの目で中野さんの作品を観てみたいとおっしゃる方は、次回個展が松屋銀座7階美術画廊にて『第12回中野純作陶展』として6月8日から14日まで開かれるので、中野さんが今もっとも注目している“くぬぎ”を中心に、藁、竹、松、楢、藍などの灰釉の世界を楽しむことができますよ。食器などの日常使いのものから、花器、茶器、陶板など100点あまりを出品されるご予定ということで、見ごたえたっぷりのはず!
また今回の個展では松や藍、くぬぎなどいろいろな灰釉で色とりどりに焼きあげられた“チャリティー箸置”がお目見えします。小さくても食器や花器に釉掛けするのと変わらない手間のかかった作品ですが、ひとつ1000円で販売し、この箸置きの売上金は全額日本赤十字社に寄付されるそうです。
とにかくエコでオーガニック、昔ながらの製法で作られているのに新しい、そんな素敵な器をぜひ発見してみてくださいね。
(鶴賀奈穂乃)
中野純プロフィール:
72年生まれ。麻布高校から東京大学文学部入学。在学中に偶然陶芸と出会い、瞬間的に一生の職業にしようと決心。95年に『立野窯』開窯。96年に大学卒業後、作陶の傍ら集英社に勤務。雑誌編集に携わり3年後に退社。作陶に専念する。