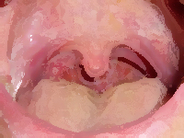「笑顔で満足した結果を残すことが、応援してくれた方への一番の恩返しだと思ったのですが、頑張った結果がこれでした。
神戸百年記念病院で看護師として働く野村真波選手。日本で初めての義手の看護婦だ。「兄弟は3人。子どもの頃から誰かが怪我をしたり病気になると、母がバタバタと慌てている姿を見ていて、小さい時から母を安心させ頼られる看護師になりたいと言ってたみたいです」。静岡で看護学生として夢に向かっていた20歳のとき、好きで乗っていた中型バイクで交通事故。激痛に泣き叫びながらも「右腕は腐っても切らない」と断固として切断を拒んだ。
「今、考えると、障害者になることに対して偏見があったと思う。
「『腕を切るなら自分の口で言いなさい。限界なの気づいているでしょ。動かない腕切って、看護師になるんでしょ』と毅然とした態度で母に言われました」。「もう切らないと間に合わない」と先生に言われ、母が精一杯口にした言葉だった。
「『無理に看護師にもならなくてもいいし、お嫁にもいかなくてもいい、一生面倒見る」と言われ家族の思いを知り、言うこと聞かなきゃだめだなと、先生に自分から『腕を切ってください』と言いました」
その後、「看護師になるための義手」を作りに、単身、静岡から神戸の病院へ。「『前例がないと、どの病院でも断られたのですが、兵庫県立総合リハビリテーションセンターの先生のおかげで、看護師として必要な動作ができる『看護師専用の義手』を一緒に作っていくことができた。見た目は良くないけど私にとっては一番の相棒。その子がいないと私は看護師とはいえない」と笑う。今では、肩甲骨を動かして、フックを開閉させ注射や点滴、何でもこなす。
リハビリの最中、車椅子バスケットの選手が転んでも起き上がって前に進むという姿を見て、「私もそういう風になりたい!このままではいけない」と前を向いた。そんなときに出会った水泳。野村選手の水泳人生がスタートした。
「2年前、パラリンピック代表を目指すため勤務時間の短縮を願い出ると、職場は午後からプールに送り出してくれた。義手の看護師を雇うだけでも大変なのに、お金で変えられない時間を与えてくれた。また、選手が遠征などの活動費捻出のため、スポンサーを見つけるのは大変難しいことなのに、たまたま、同じジムに通っていた株式会社関西環境保全センターの大森繁夫会長が、北京パラリンピック前から、スポンサーとしてサポートしてくださった。多くの人に支えられ、水泳に打ち込める環境に恵まれた私は本当に幸せです」
看護師になって6年目。「水泳はずっと続けるけど、一線で活躍するかは分からない。これからは、看護師として患者さんにもスタッフにも自分の出来ることはもちろん、仕事に専念して恩返ししていきたい」
「痛くてしょうがなくて、未来が真っ暗だったあの頃。たくさんの人に支えられ逃げ出さなくて良かった。帰国したら早速、講演会などで子供たちに会うので、今大会を通じて知った『負けを知ること』『泣くこと』も大切なんだということを、伝えていきたい」野村選手の笑顔がはじけた。
(山下敦子)